小6外国語「思考・判断・表現」の見取り方を教科書編集委員が解説
- 特集
- 評価と見とり方特集

小学校外国語科検定教科書の編集委員でもある元神奈川県公立小学校の長沼久美子先生による好評連載! 前回に引き続き今回も、外国語学習における「思考・判断・表現」の見取り方についての疑問にお答えします。
執筆/元神奈川県公立小学校教諭・長沼久美子
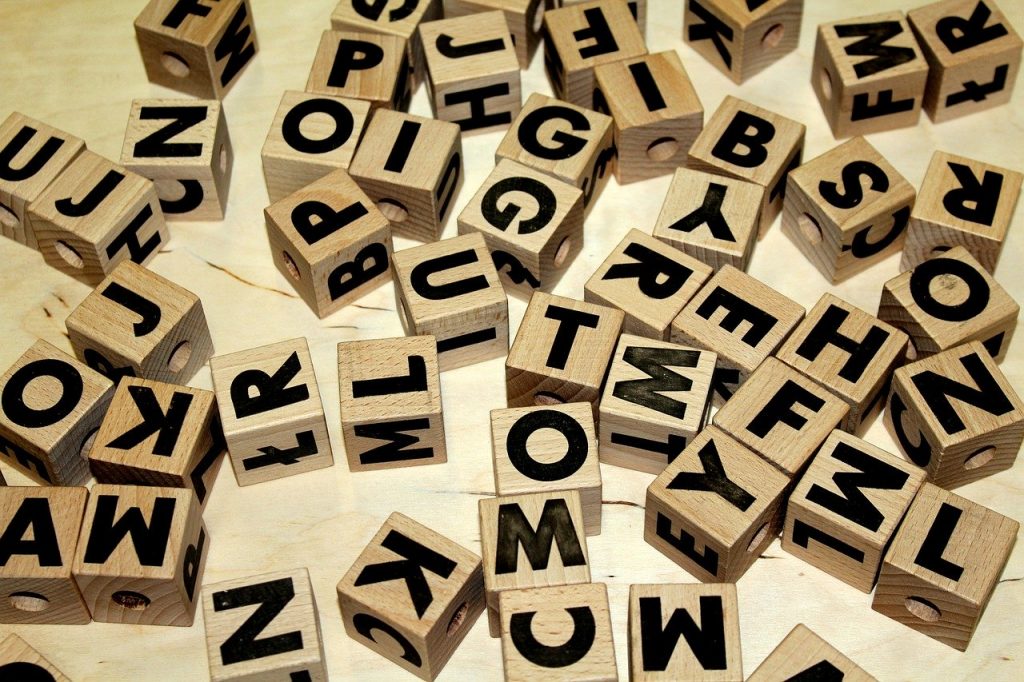
目次
Q1「世界で活躍する人を紹介しよう」の学習では、どのような様子から子どもの思考・判断・表現を見取るとよいのでしょうか。
(光村図書『Here We Go!6』P.66・67)
A.クイズの問題に答えようと、あれこれ回答を思い浮かべる姿から、思考・判断・表現を見取れます。
クイズ問題は、思考・判断しないと答えることはできません。ヒントとなる文章を聞いたり、挿絵や写真を見たりしながら、それらの情報を頼りに、瞬時に頭の中でいろいろと考えます。そして、「○○かもしれない」と分かった瞬間にクイズの答えを出すことができるわけです。
このとき、はじめのヒントで答えの見通しをもった子どもは、残りのヒントを自分の思い描く答えと結び付けています。見通しを持てていない子どもは、今までのヒントとの共通点を見つけながら、答えを考えます。このように、クイズは、常に思考・判断が繰り返されています。
しかし、これらのプロセスは頭の中で行われるので、見取ることが難しいのです。そこで、正解できた子どもに、「どうしてそうだと思ったの?」と聞いてみてください。子どもが表現するそのプロセスから、思考・判断を見取ることができます。
例えば、
He is an athlete.って言っていたから、Heだから男の人だね。athleteだから、運動選手かもと思った。
と話す子どももいれば、
He can play tennis.と聞こえた。テニスだ。男の人でテニスと言えば○○だ。
と話す子どももいるでしょう。
また、この活動で一人ひとりの思考・判断を把握したい場合は、メモを作って、1問1問に対して「なぜそう思ったのか」を書いてもらう方法もあります。
外国語学習における「思考・判断・表現」について、こちらの記事でも解説しています! → 小6外国語:「思考・判断」の見取りのポイントを教科書編集委員が解説
Q2「食物連鎖 (フードチェイン)について発表しよう」では、どのような様子から子どもの思考・判断・表現を見るとよいのでしょうか。
(東京書籍『New Horizon Elementary6』P.46・47)
A.発表する内容を膨らませて考えているところがポイントとなります。
このアクティビティでは、食物連鎖についての発表に向けて、「わたしのせりふ」を書きためます。この「わたしのせりふ」をもとにして発表するとき、単に書きためたものを読むだけでなく、「わたしのせりふ」を軸に話を膨らませて発表する内容を工夫するところに、思考・判断のポイントがあります。
たとえば、事例にある「bear」について話を膨らませるならば、
Bearは強そうだから、そのことを付けたそう。「強い」は、「strong」だった。ほかに何を言おうかな。そうだ。冬眠することも付けたそう。
と、いろいろと考えながら文章を組み立てます。膨らませていく話は、生活経験や既存知識により子どもそれぞれになるでしょう。そこが、このアクティビティの魅力です。
そこで、あらかじめどのような文章を付け足すか、想定しておきましょう。定型文を示してしまうと、自由な発想が生まれにくくなることもあります。ぜひ時間をたっぷりと設けて、子どもが自分で調べたり考えたりしながら文章をつくっていけるように支援してみてください。

