保護者からの好感度UP! 「授業参観」万全の準備と工夫
1年間、スムーズに学級経営を行うためにも、保護者との良好な関係づくりが大切。保護者と直接かかわる「授業参観」を楽しく乗り切るポイントを紹介します。
執筆/東京都公立小学校指導教諭・小島大樹、東京都公立小学校副校長・下里鮎乃、兵庫県公立小学校教諭・桔梗友行
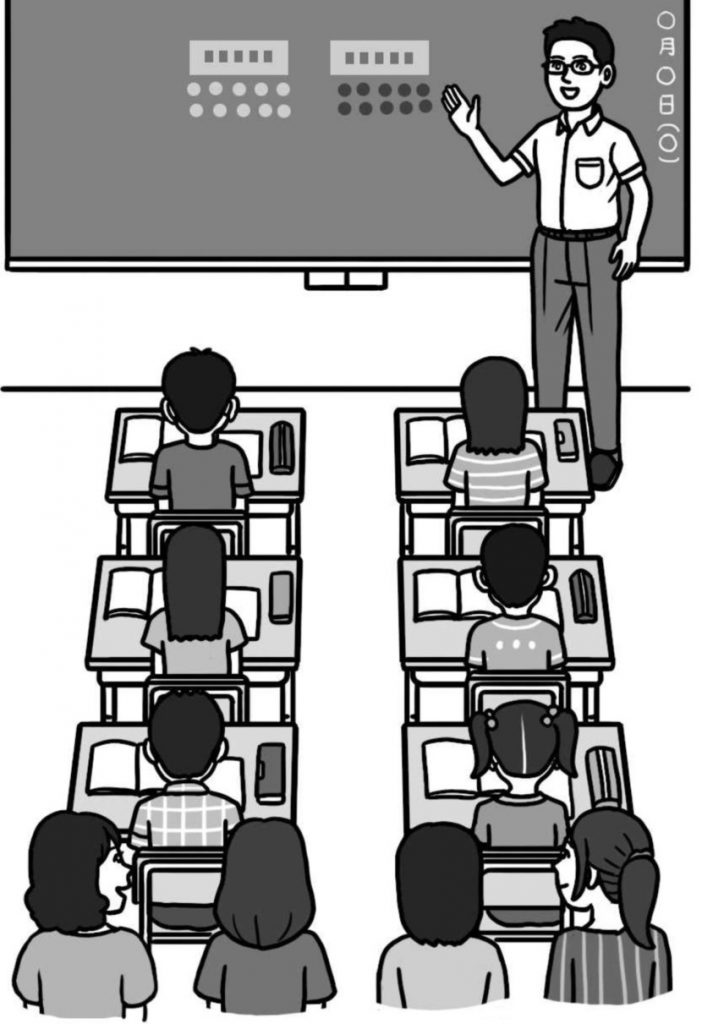
目次
授業参観・参加率アップのアイデア
保護者参加型の授業を学級通信でお知らせ
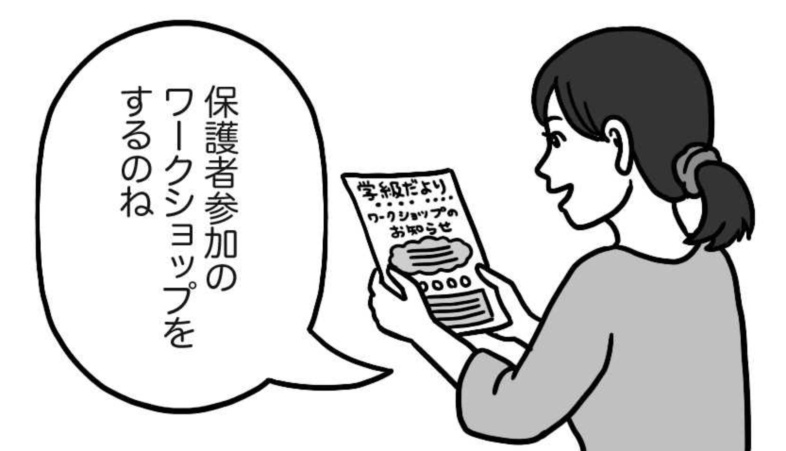
授業参観については、学級通信で事前にお知らせします。その際、授業内容のほか、保護者の方にも一緒に考えてほしいことなどを書くと、興味をもち、参加してくれる人も多くなります。
また、保護者が子供と一緒にワークショップするような授業参観を計画します。中学年なら社会科。スーパーや公共施設の工夫を見付けるワークショップなどを企画し、大人も一緒に考える内容にするとよいでしょう。(桔梗友行)
事前に保護者にアンケートをとる

学級だよりで授業参観予定表とともに、授業の見どころを記載します。単に授業内容の予定を書くのではなく、子供たちの学習活動を分かりやすく案内する内容にするとよいでしょう。
一学期はじめの保護者会などで、保護者がどんな子供の様子を授業参観で見たいのか、アンケートを実施するのもよいでしょう。学級通信の下に切り取り欄を設け、アンケートを書いて提出してもらうこともあります。(下里鮎乃)
1年間の授業展開の工夫
基本の授業から発表形式まで段階的に企画する
①一学期は基本の授業
算数の計算や国語の漢字など、基本的な授業を見ていただきます。さらにこの後1年間、家庭でも見てほしいポイントを伝えます。
②二学期は保護者参加型の授業参観
道徳の授業や社会、理科の実験などの授業で、保護者も一緒に参加し、子供と話し合えるような授業を仕組みます。
③三学期は発表形式の授業参観
1年間の集大成として、子供の発表を保護者に見てもらうような授業を計画します。総合的な学習の時間や国語などで、ワークショップ型やポスターセッションなどを行います。
大切なのは、授業参観のためだけに慌ててやるのではなく、1年間かけ、発表までの力を育てることです。
例えば三年生なら、社会で調べたことや資料をポスターにまとめて発表。四年生なら、「10歳を迎える会」のために仕事調べをしたことなどを発表します。(桔梗友行)
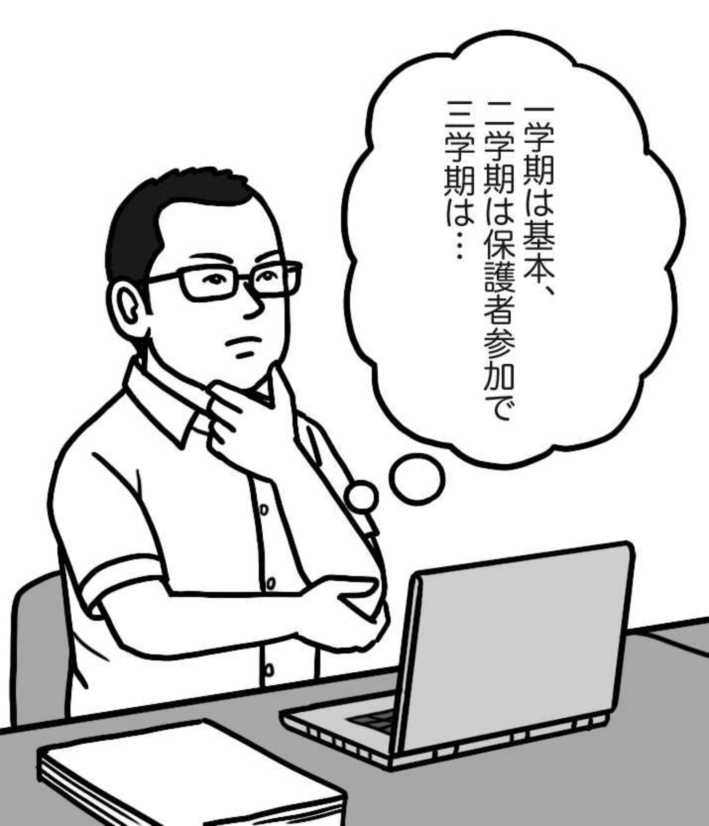
「結果」だけでなく「過程」を見てもらう工夫
保護者にとって、自分の子供が成長した姿を見るのはとてもうれしいことです。ですから、発表形式の授業参観は、保護者を喜ばせるためには非常に有効です。
しかし、発表がうまくいかない場合もあります。そして結果だけをほめすぎると、うまくいかなかった原因を他人や環境のせいにする子供も出てきます。「今回、うまくいかなかったのは人がいっぱいいたから。緊張しなければ、うまくいくはずだったのに」といった具合です。
環境のせいにせず、具体的に自分がどのように改善すればよいのかを考え、努力する子供に育てるためには、結果に至る過程をほめることが有効だと言われています。
そういう観点からも一学期は、子供たちが発表に向けて、試行錯誤しながら取り組んでいる様子を見せる授業参観がおすすめです。
そして学校の行事や日程によりますが、発表形式のものはビデオに撮り、次の保護者会で見せたり、二学期以降の授業参観で見せたりするのもよいでしょう。
例えば7月の授業参観では、秋の音楽会で行う歌の練習の様子を見てもらいます。おそらく、完成度という視点で見れば、高いとは言えないでしょう。しかし、秋の行事当日のできを見れば、保護者は完成度の高さに驚くはずです。さらに7月の様子を思い出し、「子供たちはこんなにも成長したのだ」「きっと子供たちは授業の中でがんばったんだな」と、結果だけでなく、過程に目が向くのではないでしょうか。また、学校で普段教師がどれくらい子供と向き合って指導しているかも理解してもらえる機会になると思います。
一学期の授業参観の段階で、保護者に結果ではなく、過程をほめてほしい旨を伝えておきたいものです。(小島大樹)

学び合いや教え合いの時間を設ける
授業参観では、一年を通し、各単元で必ず学び合い、教え合いの時間を入れます。
さらにグループで学習のまとめをさせたり、個人でまとめをさせたりするなど、教科内容に応じて、「単元の終わりのまとめ」を大切にし、この学びをどんな部分で生かしたいか、子供に考えさせるようにします。(下里鮎乃)

