発達心理学の専門家が教える 低学年の特性と伸ばし方
不安と期待でいっぱいの新学期。低学年の子供たちが、いきいきと学校生活を送るためには、教師が子供たちの特性をしっかりと把握することが大切です。発達心理学の専門家・渡辺弥生先生に、低学年の特性と上手な指導方法をお聞きしました。
わたなべ・やよい●法政大学文学部心理学科教授。同大学院ライフスキル教育研究所所長。教育学博士。専門は、発達心理学、学校心理学。著書に、『小学生のためのソーシャルスキル・トレーニング』(明治図書)、『感情の正体 発達心理学で気持ちをマネジメントする』(筑摩書房)など多数。

目次
特性① 緊張と不安感でいっぱい
保育園や幼稚園の生活と違って、低学年では学習という時間が加わります。環境ががらりと変わり、子供たちは緊張や不安感でいっぱいです。そんなとき、接する担任の教師自身がピリピリしないようにしたいものです。
醸し出すピリピリした空気は、話し方や表情から敏感に子供に伝わり、不安感を大きくしてしまうことにもなりかねません(情動感染)。
学級全体に和やかな雰囲気をつくり上げていく工夫が大切

「分からないことやできないことは、すぐに先生に聞いてね」と、登下校の際や休み時間に、優しく伝えるのがよいでしょう。そのうえで、「今何してるの?」「これが好きなの?」と、声をかけながら、学級の一人ひとりに関心をもっていることが伝わるようにします。存在を認めてあげることは、子供たちを安心させます。
コミュニケーションをとりながら信頼関係を築こう
その場に応じて、目線、声の高さや大きさなど話し方を意識して、的確なアプローチを心がけてください。まずは、できるだけ具体的に、シンプルで、分かりやすい言葉で話しかけるとよいでしょう。
「礼儀が大切」というよりは、「朝は、よく聞こえるような声で、おはようございますってあいさつしようね」といったように、子供たちがすぐに理解し、行動できる話し方にします。
また、新たなスタートを前に、緊張でガチガチの保護者もいます。担任教師は、入学式や懇親会などで保護者と顔を合わせた際、子供に声がけするように、保護者の気持ちを和らげ、穏やかに接することを心がけましょう。
特性② 感情のコントロールが未熟
低学年は、保育園・幼稚園児と比べて、自分の感情(怒り、恐れ、喜び、驚き、悲しみ、嫌悪など)を理解し、ある程度、自分でコントロールできるようになってきています。騒いではいけない場面では静かにしようとしたり、悲しいときに泣きじゃくらずに言葉である程度伝えられるようになってきたりします。
しかし一方で、感情が多様で複雑になってくるため、それに適した表現方法が見付けられなかったり、集団生活で上手に感情コントロールができなかったりする場面も見られます。このような場合、ソーシャルスキルを身に付ける指導が有効です。
ソーシャルスキルを身に付ける
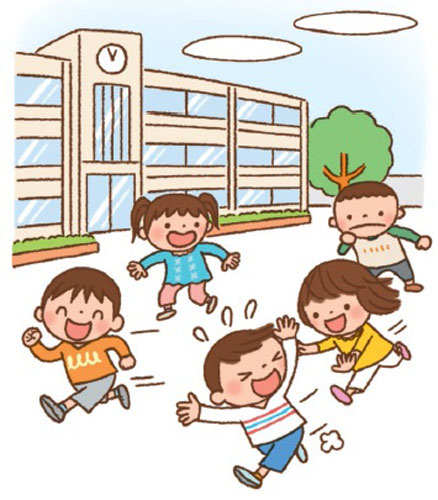
ソーシャルスキルとは、「他人と上手に関わるための技術やコツ」のことをいいます。これを身に付けることで、経験を重ねながらも円滑な対人関係を築き、維持することができるようになります。
かつては、人生に必要なソーシャルスキルを、子供たちは遊びを通して学んでいました。しかし現代では、少子化や子供たちの生活スタイルの変化により、自由に遊ぶ絶対量が減り、「友達を思いやる」「がまんする」「へこんでも立ち上がる」といった、人間関係を築くためのスキルを学ぶ機会が減ってきています。
教師は、そのような子供たちの状況を理解し、他人と上手に関わるための技術やコツを子供たちに伝えていく役割があります。学級が、日常的にソーシャルスキルを安心して伸ばすことのできる場所になるようにしましょう。子供たちに望ましい考え方や行動のしかたを具体的に教えていくとよいでしょう。

