ドリルで得られる知識は決して、今、求められているものではない【矢ノ浦記者が語る「教育取材余話」④】
先日、ネット上のある記事で、子供たちにもっと知識を覚えさせ、ドリルさせるような訓練が必要だという趣旨のものがありました。今回は、そのことについて現場の先生の取材体験も交えながら、少し考えてみたいと思います。
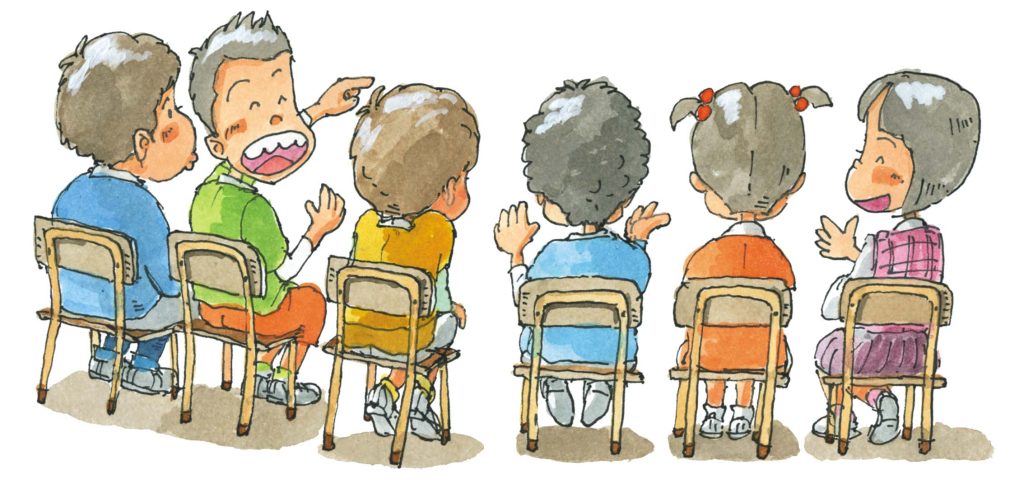
執筆/教育ジャーナリスト・矢ノ浦勝之
目次
保護者世代の意見は知識の刷り込みを肯定するものばかり
先日、ある現場の優秀な先生との取材中に、子供たちに真剣に学習内容に向かわせ、思考させることの重要性や、そのような授業をつくるための工夫についてのお話を伺った後のことです。ちょっとした余談から、ネット上の記事に、子供たちが探究したり思考したりすることよりも、もっと基礎的な知識を覚えさせる訓練をさせたほうがよいといった趣旨のものがあったことに話が及びました。
その記事には多数の、保護者世代らしき方たちのコメントが付いていたのですが、それらはみな同意する意見で、訓練による知識の刷り込みを肯定するものばかりでした。もちろん、記事内容と同意見ばかりの中では、反対意見をもっておられる方がいても書き込みにくかっただけなのかもしれません。しかし、あまりに多くの方が、「探究よりもドリル」「思考よりも訓練」といった意見を書かれていたことに驚いたのです。言うまでもありませんが、子供たちがより主体的に学びに向かうため、単元の仕掛けを工夫されているその先生も、私と同意見でした。
一般的に、保護者も教師も含め、大人の世代は自身の子供時代の教育体験から離れ難い場合が多いと言われます。その教育を通して社会的に成功したという自負があれば、それは仕方ない面もあるのは分かります。しかし、少し冷静になって子供の立場で考えてみたら、気付けるのではないかと思うのですが、どうでしょうか?
子供の頃、「こんな勉強に何の意味があるのだろう?」と思った経験がある方も少なからずいるのではないでしょうか? しかし、それはもう成功体験の彼方に忘れ去ってしまったのかもしれません。あるいはドリル重視、訓練重視を強調される方は、「何のために学ぶのか」などとは考えることなく、人に言われた通り、素直に取り組んできた方なのかもしれません。
もちろん対話し、思考するためには一定の知識が必要なことは言うまでもありません。しかし、「探究や思考よりもドリル」となると、訓練で得られるレベルの知識のみを重視し、対話や新たな(人・もの・こととの)出会いを通して多面的・多角的に思考を働かせること、つまりそれまでに得た知識や思考を総動員することを忌避するわけですから、「何のための知識なの?」ということになってしまいます。
やはり、一般的に言われる学力のイメージが非常に古いまま、これからの時代を生きる子供の学びを語っているようにしか見えません。
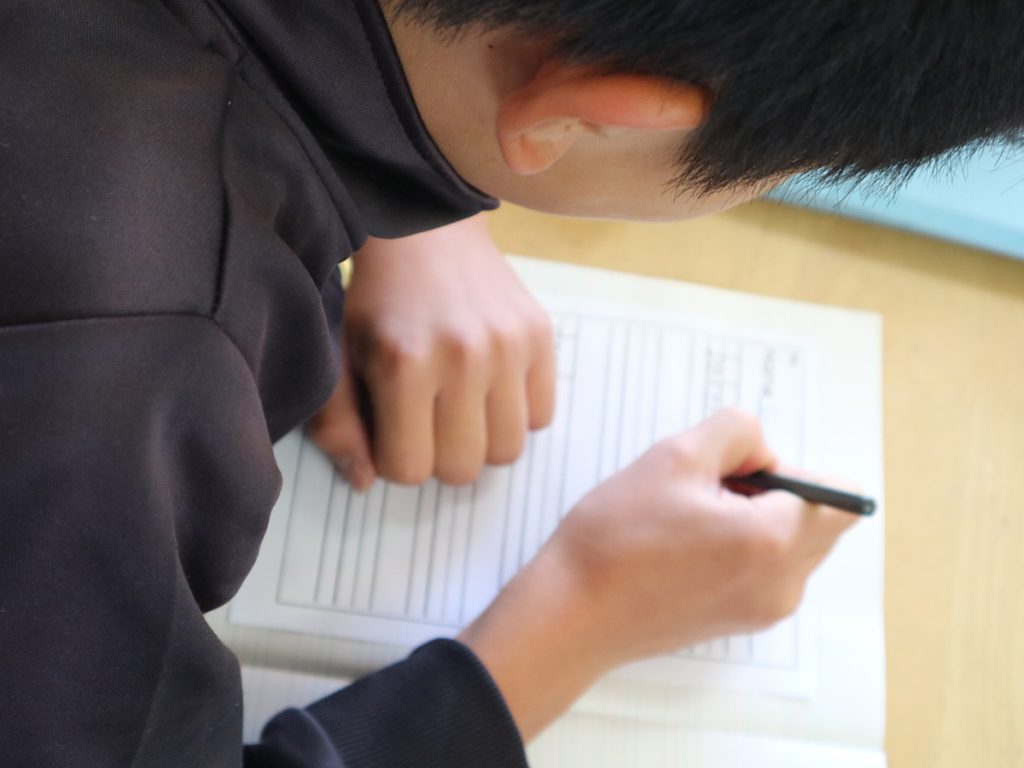
中央教育審議会教育課程企画特別部会で提言された「記号接地」
ここで考えておかなければならないのは、ドリルなどの繰り返し練習の中で得られる知識は決して質の高いものではなく、今、求められているものではないということでしょう。
現在、進められている学習指導要領改訂の議論の中では、知識について何もかも同じ知識と捉えるのではなく、いくつかの階層で捉えるという話が出てきています。1個1個の事実レベルの知識や、それらによって形づくられるより深い(あるいは高次の)概念的知識、さらにそれらを統合するような教科独特の原理など、階層があるわけです。当然、単純な1個1個の知識であれば覚えればよいわけですが、概念や原理はただ覚えるものとは質が異なります。
中央教育審議会教育課程企画特別部会で、次期学習指導要領の方向性について議論を行っていく中で、「記号接地」ということについて、ある委員の先生がその重要性について提言をしておられました。「記号接地」とはごく乱暴に言えば、言葉などの記号と実社会の事物などを結び付けながら意味理解を図ることであり、特に概念についてはこのような理解が求められます。つまり、単純にドリルをすることで記憶できるものとは質が異なるわけです。
さらに言えば、この「記号接地」は(現時点では)AIにはできないことだとされており、今後さらに多様な情報処理がAIによって代替されるようになっていく社会においても、人に求められるものでしょう。
ですから、「ドリルをもっと増やして知識を!」という保護者世代がもっている考えは、これからの時代に求められているものとは大きく異なるわけです。


