ごく日常の授業を見る場合には、何を見たらよい? 【矢ノ浦記者が語る「教育取材余話」③】
前回、授業の見方ということで少し取材体験をお話ししましたが、それに関係ある内容について、ごくごく最近の取材でさらに体験したことがありました。それに関して、ごく最近のことなので少しだけフェイクを入れながら、話の本質部分だけを語っていきたいと思っています。
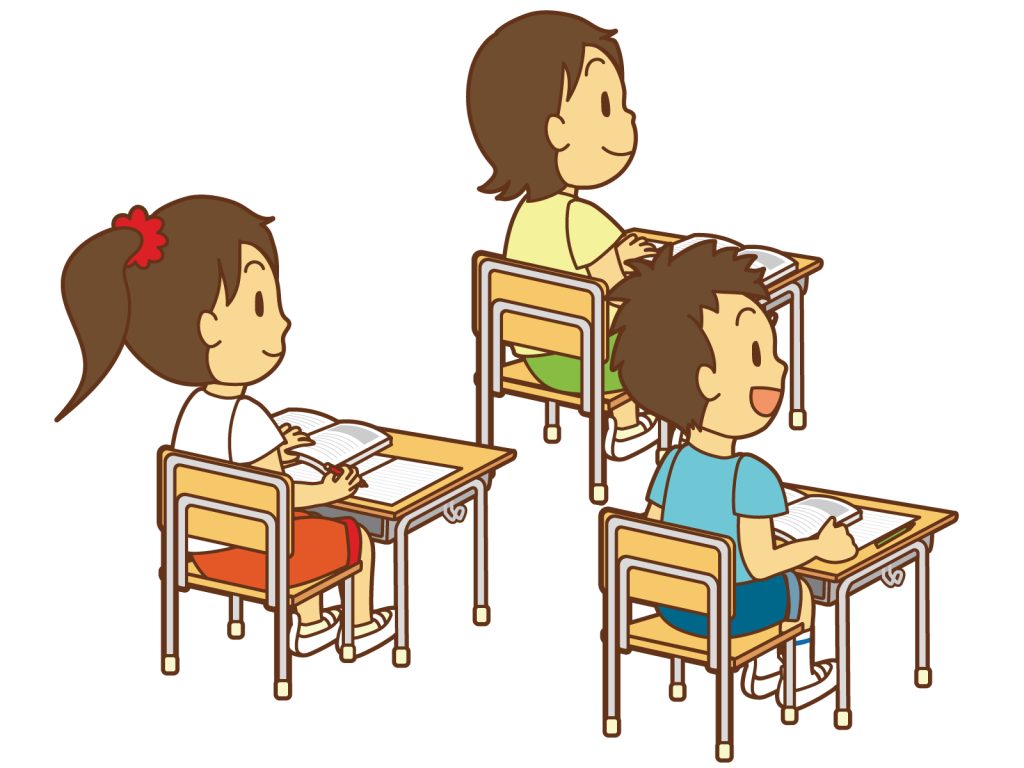
執筆/教育ジャーナリスト・矢ノ浦勝之
目次
授業から子供の思考の変容や知識の変容を読み取っていく
先日、ある学校へ研究授業の取材に伺ったときのこと、若手の先生と同席する機会がありました。その先生は授業者であるベテランの先生に直接のつながりがある方で、どうしても授業を見せてほしいと熱心にお願いして、その学校まで出かけてこられたのだそうです。
その授業自体、よく練られたものでしたし、子供たちも集中して教材に向き合っており、授業後の取材もごくスムーズに終えることができました。
取材終了後、最寄りの駅までの道すがらその若手の先生が私に、「たくさんの授業を見てこられているようですが、授業ではどんなところを見て、よい授業か悪い授業かを判断されてるんですか?」と尋ねてこられました。もちろん、前回お話をしたように、授業中、指導案と睨めっこをするのではなく、子供たちの学ぶ姿を見るというのが大前提でのご質問です。
そこで私が、「子供たちの学ぶ姿を見ています」とごく簡単にお答えすると、「子供たちのどんな様子を見ているんですか?」とさらにお尋ねになります。それに答えて、「もちろん言動を見ているわけですが、それを通して子供たちにどんな変容が生じるかということですね。子供たちの思考がどれくらい動いたか、友達との話合いをしているときの内容や書いたものの変化などから、思考の変容や知識の変容を読み取っていきます」と私。
それに対して、その先生は「単元を通して見なくてもその変容は見えるものですか?」と鋭い質問を返してこられます。そこで、「おっしゃる通り、特に資質・能力ということで言えば、学習指導要領の改訂議論でも、『単元を通してということを改めて強調する必要がある』との指摘もなされていたくらいですから、単元を通して見ることが大前提ではあります。しかし、ご想像の通り、私たちの立場で単元を通して見せていただくことはまずありません」と正直にお答えします。
その上で「とは言え、私たちが取材をお願いした場合、多くの先生は子供たちの思考が大きく動く場面の授業を見せてくださることが大半です。研究授業でも、そういう場面を見せてくださることが多いのではないでしょうか? ですから、その授業における子供たちの知識や思考の変容を見ているのです」とお答えしました。
さらに、ある地方で子供たちが一生懸命に意見を交流していて、思考が動きかかっているのに、残り5分になったところで「それでは今日のふり返りを書いていきましょう」と指導案通りに進めてしまった例に触れ、「そんな指導案通りの時間配分で授業を進めるのではなく、時間いっぱい対話させてあげたほうがもっともっと子供の変容が見られただろうに」と感じたことなども話をしました。

