小4理科「季節と生物」×図画工作科|紅葉の美しさを感じる心を大切にする教科横断授業【理科の壺】

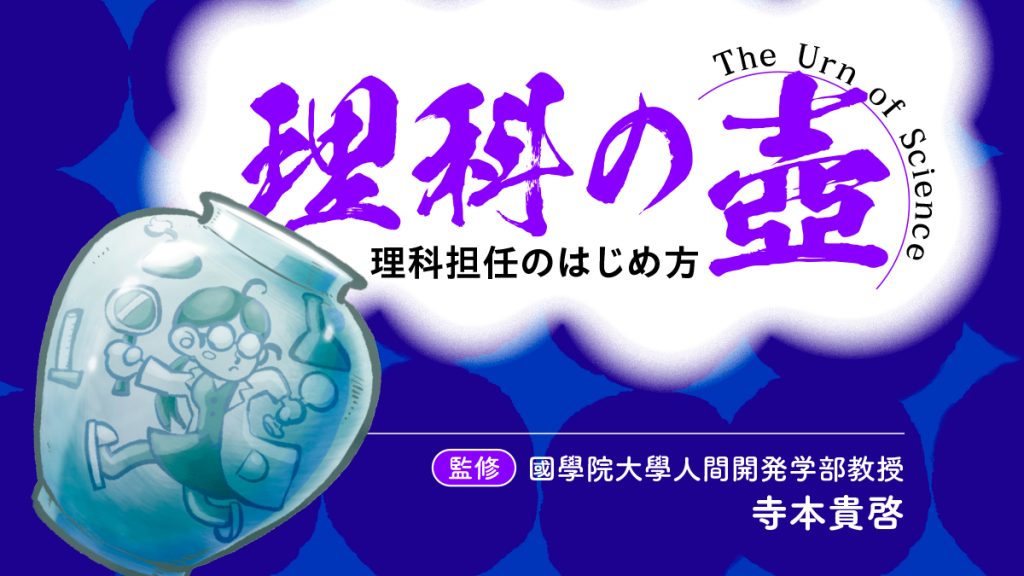
理科では、自然の不思議さ、偉大さ、美しさなど、子どもたちが感じることも大切にしています。科学的な「追究する力」を身につけることも大切ですが、小学校のこの時期でしかできないこともあります。今回は、「紅葉の美しさを感じる心」を大切にするために、他教科と接続して深く学んでいく実践の紹介です。これを読むと、我々大人こそ、このような気持ちを忘れていないかと考えさせられます。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?
執筆/栃木県公立小学校教諭・田名網恒介
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.「もっとやりたいのに、時間の余裕がない」
子どもたちにじっくり観察させ、分かったことを思う存分表現させたい。
でも、なかなか時間に余裕がない⋯⋯!
理科の授業をしていて、そう思ったことはありませんか。
私もその一人です。
理科授業を頑張ろうとする先生ほど、そう感じるのかもしれません。
そこで今回は、第4学年『季節と生物』の中でも特に「秋の植物」を例に、教科の資質・能力の育成を目指しつつ、子どもたちの表現のための活動時間を確保する方法を紹介します。
2.秋の自然の特徴
学習指導要領に示されている第4学年『季節と生物』で目指す目標および内容は次のとおりです。
身近な動物や植物について、探したり育てたりする中で、動物の活動や植物の成長と季節の変化に着目して、それらを関係付けて調べる活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のことを理解するとともに、観察、実験などに関する技能を身に付けること。
(ア) 動物の活動は、暖かい季節、寒い季節などによって違いがあること。
(イ) 植物の成長は、暖かい季節、寒い季節などによって違いがあること。
イ 身近な動物や植物について追究する中で、既習の内容や生活経験を基に、季節ごとの動物の活動や植物の成長の変化について、根拠のある予想や仮説を発想し、表現すること。
小学校学習指導要領(平成29年告示)解説【理科編】第3章 第2節 2「第4学年の内容」(p.54)より
これまで、春、夏と植物の観察をしてきました。校庭や公園など、同地点で同一の対象を定期的に観察していると思います。
春と夏では、「どのようなようすなのだろうか」という問題に対して、子どもたちは、今までの生活経験から知っている「(冬と比べて)芽が出てくる」、「(春と比べて)より成長する」といったことを確かめるために、実際に観察し、記録をしてきました。例えば、気温や草丈などを継続的に記録し、数値化して様子を表現していると思います。
すなわち、成長に着目して調べる活動をしてきました。
秋の植物の様子についても、これまでと同じように「夏と比べて、植物のようすはどのように変わったでしょうか」と発問します。
「夏より気温が低くなったから成長しにくくなる」
「落ち葉が増える」
これが、今までと同じように「成長」に関する意見です。
ところが秋は次のことが加わることが多いと思います。
「葉が赤くなったり黄色くなったりする」
今まで注目してきた「成長」とは少々視点が異なるかもしれません。
しかし、ぜひともこれを生かしたい!と思いませんか?


