子どもたちの自己肯定感を高める、具体的な『褒め方』の技術

新人教員のための学級安定実践13選⑨
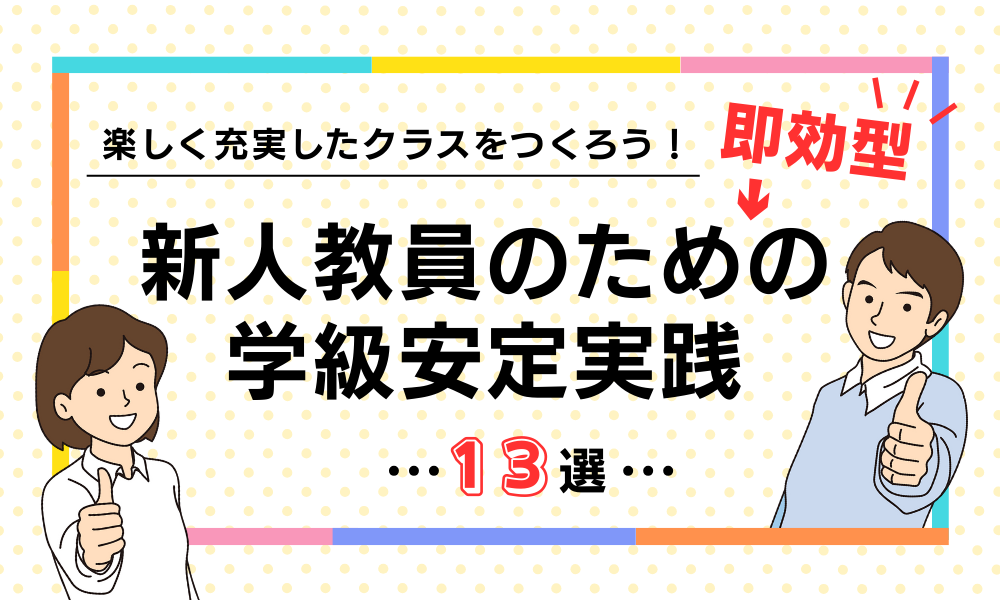
褒めることの大切さは誰もが知っていることと思います。しかし、効果的な褒め方となると、多くの教師が悩むところです。「すごいね」「がんばったね」といった抽象的な褒め言葉では、子どもの行動変容や自己肯定感の向上は期待できません。それどころか逆効果になることもあります。子どもの心に響く褒め方には、具体性と戦略性が必要なのです。
執筆/私立小学校教諭・熱海康太
目次
結果より過程を褒める
多くの場合、私たちは結果に注目して褒めがちです。「テストで100点を取れたね」「かけっこで1位になったね」といった結果重視の褒め方は、一見効果的に思えますが、実は子どもに「結果が出なければ価値がない」というメッセージを送ってしまう危険があります。 効果的な褒め方は、結果に至るまでの過程に焦点を当てます。「毎日コツコツ漢字練習を続けていたもんね」「最後まであきらめずに走り切ったね」といった声かけにより、努力そのものに価値があることを伝えます。これにより、結果が出なかったときでも、子どもは自分の努力を肯定的に捉えることができるのです。
具体性のある褒め方
「よくできました」「素晴らしいです」といった抽象的な褒め言葉は、子どもにとって何が良かったのかが分かりません。効果的な褒め方は、具体的な行動や変化を指摘します。 「今日は友だちが困っているのに気づいて、すぐに声をかけていましたね」「昨日より丁寧に字を書くようになりましたね、特に漢字のとめはねの部分が丁寧です」「分からない問題があったときに、すぐにあきらめずに考え、質問にも来ましたね」といったように、何が良かったのかを明確に伝えることで、子どもは自分の良い行動を意識し、それを継続しようとします。
成長を可視化する褒め方
子どもの成長は、日々の小さな変化の積み重ねです。これらの変化を見逃さずに声にすることで、子どもは自分の成長を実感することができます。「先月と比べて、発表するときの声が大きくなりましたね」「4月の頃より、友だちとの話し合いが上手になりましたね」といった比較を交えた褒め方は、子どもに明確な成長実感を与えます。
また、成長の記録を残すことも効果的です。子どもの良い行動や変化を写真や文章で記録し、適切なタイミングで振り返ることで、成長をより実感しやすくなります。
自己肯定感は他者と比較すると下がってしまうことが多いそうです。比べるのは他者ではなく、自分自身とするのが良いでしょう。もし、過去の自分と比べて、勝っていたとしたらそれは「自分が頑張ったからだ」というように評価でき、もし劣っていた場合でも「あのときの自分は頑張れたのだから、きっと今回も頑張れるはず」と励みにすることができるでしょう。

他者との関係性を意識した褒め方
子どもの行動が他の人にどんな影響を与えたかを伝えることで、社会性の育成にもつながります。「○○さんが整理整頓をしてくれたおかげで、みんなが気持ちよく過ごせています」「○○さんの優しい言葉で、△△さんが元気になったね」といった声かけにより、自分の行動が他者に良い影響を与えることを学びます。
これにより、子どもは単に自分のためだけでなく、他者のためにも良い行動を取ろうとする動機を持つようになります。
タイミングを意識した褒め方
褒めるタイミングも重要な要素です。良い行動を見つけたら、できるだけその場で褒めることが効果的です。時間が経過してから褒められても、子どもは何について褒められているのかが分からなくなってしまいます。
バナーイラスト/futaba(イラストメーカーズ)
イラスト/池和子(イラストメーカーズ)

著者:熱海康太(あつみこうた)
一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事
大学卒業後、神奈川県内の公立学校、私立学校で教鞭を取る。
大手進学塾の教育研究所を経て、現職。
10冊以上の教育書を執筆し、全国10,000人以上の先生方に講演を行うなど、幅広く活動している。

