学級目標を見直す『絵に描いた餅にしない3つの秘訣』

新人教員のための学級安定実践13選⑥
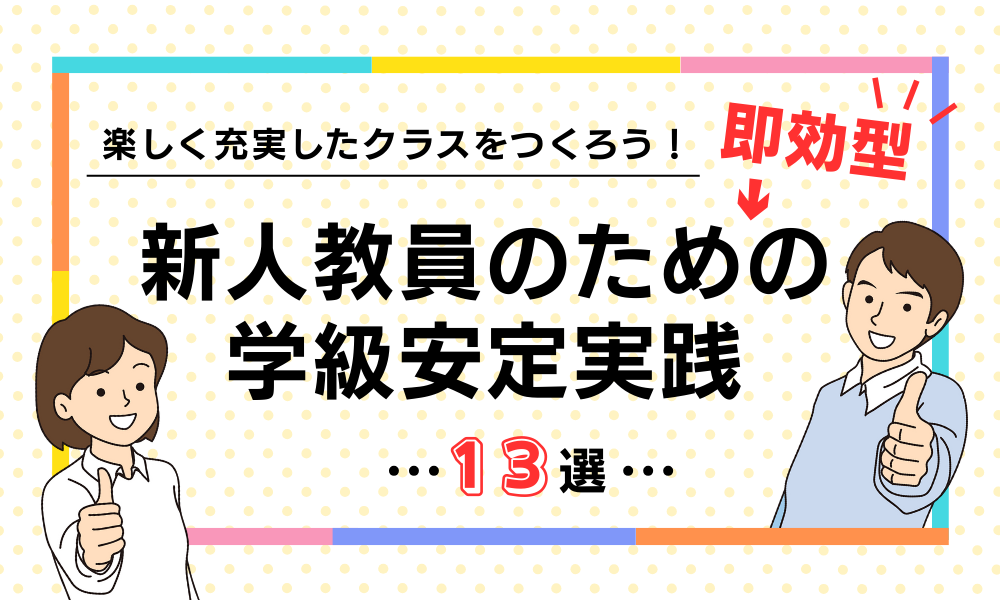
学級目標を4月に決めたきり、学期末まで振り返ることがない。そんな「絵に描いた餅」状態になっていませんか。学級目標は、子どもたちと教師が共に向かう方向性を示す重要な指針です。しかし、適切な設定と継続的な活用がなければ、単なる装飾品になってしまいます。大人でも、たとえば学校目標や研究目標などはそうなっていないでしょうか。学級目標を生きた指針として機能させるための実践的な方法をご紹介します。
執筆/私立小学校教諭・熱海康太
目次
目標設定のタイミング:6月がベスト
多くの学級では4月当初に目標を設定しますが、私は6月頃の設定をお勧めします。なぜなら、4月の段階では子どもたちの実態や課題が十分に見えていないからです。2か月間の観察により、「この学級の子どもたちには何が必要か」「どんな成長を目指すべきか」が明確になります。
目標というのは、動機があって成立するものです。初日に、教師から「この一年間はこの目標で頑張ろう」と言われても、子どもたちは自分事になっていません。逆に、様々なトラブルがあった後やクラスの良いところが見えてきたりした後で、「ここは改善したい。ここはもっと良くしたい」という思いがあれば、目標は自分事になりやすいです。
6月くらいには、「もう少し静かに話を聞けるようになりたい」「友だちともっと仲良くなりたい」といった思いが自然に生まれ、目標設定への動機が高まります。
子どもの困り感に寄り添う目標
効果的な学級目標は、子どもたちの困り感に直結している必要があります。教師が一方的に理想を掲げるのではなく、子どもたちが「これができるようになりたい」と心から思える目標でなければ意味がありません。
目標を考える前に、まずは学級の現状について子どもたちと率直に話し合います。「今、困っていることは何だろう」「もっと楽しい学級にするには何が必要だろう」といった問いかけから始めることで、子どもたち自身の言葉で課題を表現させます。ここでは抽象的な話し合いにならないようにすべきです。「もっと優しいクラスにしたい」と言うのであれば、「その優しいと言うのは、どんな行動が増えていくことなのかな?」と問い返して、具体的にしていくことで、より多くの子どもたちが描く目標を共有できるようになります。
全員参加の目標作りプロセス
学級目標の設定では、全員が参加できる仕組みが重要です。声の大きな子だけの意見が反映される状況を避けるため、まず個人で考える時間を設け、次にグループでの話し合い、最後に全体での合意形成という段階を踏みます。ここでも具体的な投げかけが大切です。
付箋を使ったKJ法なども効果的です。一人ひとりの思いを可視化し、似た意見をまとめながら、学級全体の願いを整理していきます。この過程で子どもたちは、自分の思いだけでなく、他の人の思いも大切にすることを学びます。
そして、様々な具体を十分に共有できた後は、それを一言で表す抽象的な言葉にしていきます。「太陽のようなクラス」「優しさに気づけるクラス」などがそうです。ここでも、太陽とはどのような行動が多い状態なのか、優しさとは何をもって優しさなのかは明確にして、目標と共に掲示して思い出せるようにしておくのがいいでしょう。

常に立ち返る最上位目標
設定した学級目標は、あらゆる場面で活用します。運動会の練習でも、学習発表会の準備でも、日常のトラブル解決でも、常に学級目標に立ち返って判断します。「私たちの目標は○○でしたね。この場面はそれに当てはめると、どう行動すべきでしょうか」という問いかけにより、子どもたちは目標を意識した行動を取るようになります。
教師自身も、指導に迷ったときは学級目標を基準に判断します。これにより、一貫性のある学級経営が実現できます。
振り返りシステムの構築

著者:熱海康太(あつみこうた)
一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事
大学卒業後、神奈川県内の公立学校、私立学校で教鞭を取る。
大手進学塾の教育研究所を経て、現職。
10冊以上の教育書を執筆し、全国10,000人以上の先生方に講演を行うなど、幅広く活動している。

