友達ができない子供への対応とは?「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #30

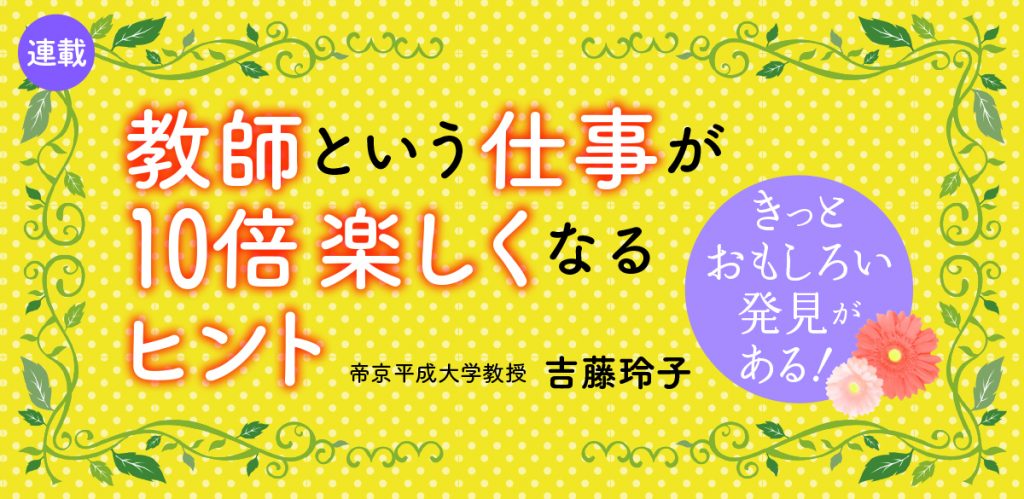
「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」の30回目のテーマは、「友達ができない子供への対応とは?」です。学級にいつも1人でいるという子供が気になりませんか。学校には来ているのだけれど、いつも1人、なかなか友達がつくれないという子供への対応について、様々なヒントをお届けします。

執筆/吉藤玲子(よしふじれいこ)
帝京平成大学教授。1961年、東京都生まれ。日本女子大学卒業後、小学校教員・校長としての経歴を含め、38年間、東京都の教育活動に携わる。専門は社会科教育。学級経営の傍ら、文部科学省「中央教育審議会教育課程部社会科」審議員等、様々な委員を兼務。校長になってからは、女性初の全国小学校社会科研究協議会会長、東京都小学校社会科研究会会長職を担う。2022年から現職。現在、小学校の教員を目指す学生を教えている。学校経営、社会科に関わる文献等著書多数。現在、日本・中国・韓国の初等教育において、異文化理解教育の推進に関する実践と研究にも携わっている。
目次
いつも1人の子供を見かけたら
私は、この数か月、自分の研究分野でもある初等教育における国際理解について学ぶことが多く、海外諸国の人とどう向き合うか、異文化理解コミュニケーションなどについて研修に参加していました。しかし日本では海外諸国の人とどう付き合うかの前に、昨今は同じ日本人同士でもうまく付き合うことが難しい大人も増えています。日本の学校現場は、遠足や移動教室、学校行事など集団で行動することが多くあります。いつも1人でいる子供を見かけたら、教師はどうしたらよいのでしょうか。
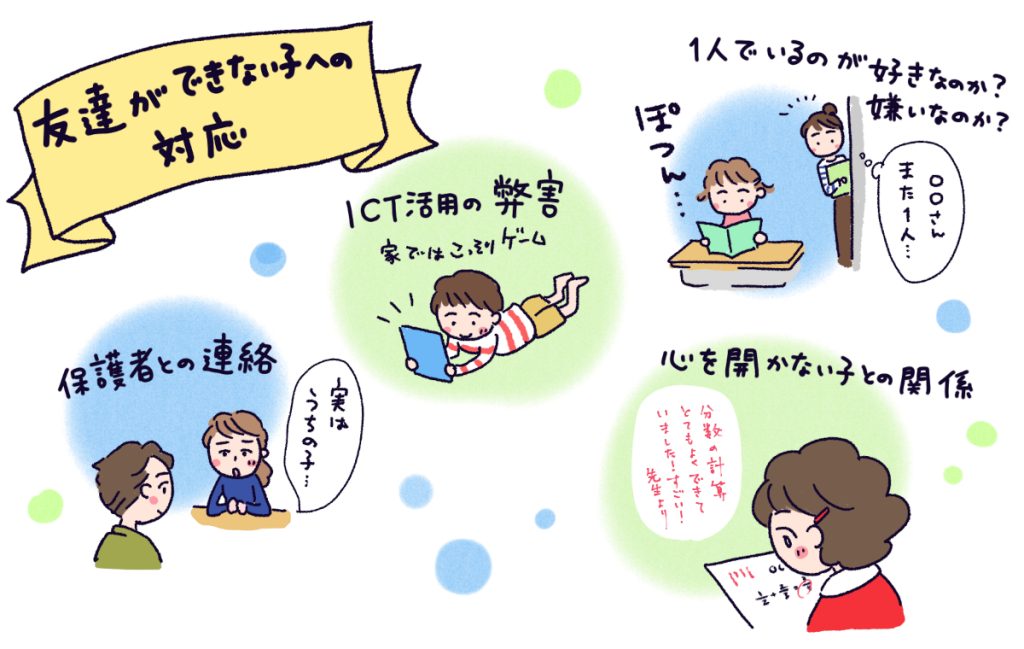
1人がいることが好きなのか、嫌いなのか
多様化している学校現場では、以前なら1人でいるのは仲間はずれがあったとか、うまくコミュニケーションが取れないのかと判断していましたが、1人でいることが楽な子供もまれにいます。
校長をしているときに、「1人が好きなんだ」と言う子供に会ったことがあります。彼は、休み時間は教室か図書室で本を読んでいました。そんな彼にクラスの皆と遊ぶことを強制してもかわいそうです。移動教室や運動会などでグループをつくらなくてはいけないときに様子を見ていると、なんとなくみんなと一緒になっていました。それならば大丈夫かなとあえて休み時間に「みんなと一緒に遊んだら?」と聞いてみるのはやめました。1人でいる子供を見付けたら、「今、何をしているの?」とまず声をかけてその理由を聞いてみてください。その反応ですぐに指導が必要なケースか、そうでないケースか判断をしてください。
「1人でいるのが好きなの」と言う場合はそれでよいですが、誰も遊んでくれない、実は、1人でいたくないんだと言われた場合は、学級での指導が必要になってきます。もしクラスの中で仲間はずれなどになっていた場合は、すぐに事実確認をして学級全体への指導が必要です。場合によっては、いじめが発生しているかもしれないので、同僚の先生や管理職に相談して対応しましょう。とくに女子の場合は、一見仲良く友達のように振舞っているようでも、陰で仲間はずれにしている場合があります。1人でいる子供だけでなく、その子供の今までの人間関係を知っている子供や先生方からの事情聴取も必要です。
私は、高学年の担任をすることが多かったです。単学級での6年担任などの場合は、人間関係が低学年のときからできあがってしまっていて、解決するのが難しかったことがあります。でも解決の糸口はあります。なぜその子供が1人にされてしまったのか、自分勝手な行動など嫌われてしまう理由があったのかもしれません。またクラスの中で力をもっている子供が嫌いだからと言って仲間はずれにしてしまったのかもしれません。いずれにせよ、1人でいたくないのに1人ぼっちという子供がいたら、担任の力が必要になってきます。すぐに動いてください。
ICT活用の弊害
「個別最適な学び」と言われ、1人1台のタブレット端末活用が日常的になり、調べ学習などでも自由選択が言われ、個人の意向に沿って学習活動を選択することが奨励されるようになりました。1人で学ぶ時間だけでなくグループで学ぶ時間を意図的に設けた授業を取り入れればよいのですが、まったく個に任せっ放しになると、子供が人と関わって学ぶ機会がなくなります。
学校と家庭との大きな違いは、学校現場にはたくさんの子供がいて、人との関わりを学べるところです。しかし、最近の授業を見ていても、個の調べ学習の時間が充足され、班や学級全体での話合い、学び合いの時間が少なくなっているような気がします。
多くの学校では、子供たちは毎日タブレット端末を持ち帰り、家で充電して翌日持参するという形を取っています。家でゲームや不適切なネットのページを見ないようにフィルターが入っていても、保護者が共働きで家に自分しかいない時間が多くある子供は、タブレット端末でYouTubeを見たり、ゲームをしたりしてしまいます。ICTは確かに便利です。でも使い方と管理は十分に指導しないといけません。1人でいることが多い子供を見かけたら、1日でパソコンに向かっている時間やゲームをしている時間を聞いて、指導していく必要があるかもしれません。
心を開かない子供との関係
1人でいる子供はあまりしゃべらない子供の場合が多いようです。そういう子供に向かって、矢継ぎ早に教師が声かけをすると、教師と子供との関係がうまくいかなくなってしまう場合があります。まずは、その子供に寄り添うことが大切です。「今、何をしているの?」からでよいと思います。それでも話すことができなかった子供とは、授業の中で提出してくれたプリントや宿題などにメッセージを添えてみてはどうでしょうか。宿題の中に今日の振り返りのコーナーなどがあれば、交換日記のように連絡を取り合ってみるのも1つの方法です。話さない子供は絵を描いたり、気持ちを文字にしたりすることが得意な場合があります。図書室で一緒に本を探したり、図工の時間などに絵を褒めたり、なんらかの形で関わりをもつように工夫してみましょう。
面接も大事です。子供と時間を取って面接してみましょう。1人でいる子供のみを対象にするのでなく、5分程度の短い時間でよいのでクラス全員の子供たちと面談をしてみてもよいでしょう。子供は本来、担任の先生が好きなのです。声をかけてほしいのです。でも、「先生は忙しいから今日話しかけてくれなかった」とか思います。クラスの実態を知る上でも個人面談は大切です。給食や図書の時間、調べ学習のときなど上手に時間をつくって積極的に子供と関わってください。
保護者との連絡を
先日、インド人の友人と話していたら、日本で分からないのが「引きこもり」という現象だと言っていました。「インドに比べて、生活も豊かで仕事も探せばあるのに、身体が健康な大人がなぜ家の自分の部屋から出てこないんだ」と言うのです。彼はデリーの近くで生まれ育ったのでいろいろな貧困を見てきたと言います。貧困という意味で考えれば、日本は恵まれているのかもしれません。蛇口から水も飲めるし、食べ物がなくて困ることもありません。でも家から出ることができなくなってしまった人は大きな悩みを抱えているのだと思います。小学校のときに教師ができることは、少しでも人と関わる糸口を見付けてあげることだと思います。
不登校のときもそうですが、保護者は、学校へ行かない、友達がいないということにとても不安になります。場合によっては、学校での様子を保護者が全く気付いていないこともあるので、1人でいる様子が見られたら、子供と話した結果をもとに保護者に伝えることも大切です。友達ができないことを話せば、何か思い当たる要因を保護者から聞けることがあるかもしれません。
以前、1人っ子の男の子の保護者に1人でいることが気になることを伝えたとき、実はその子供のお父さんもコミュニケーションが苦手だということが分かりました。人とどう関わってよいのか分からず、他の人と関わりが少ない職場へ転職し、元気になったということでした。お母さんはとても社交的な人だったので、子供の事情を話し、保護者会などで他のお母さんと関わりをもってもらうなかで、スムーズに話すことができる同じマンションの親子との交流ができ、状況は改善されてきました。
保護者が友達同士のいざこざを心配していた場合もあります。保護者から悩みを聞くつもりで、いろいろな情報を得て、解決策を見いだしたいものです。
学校は、子供に取って楽しい場所、来たいところでありたいものです。先生たちが忙しいのは本当によく分かっています。でも自分の生きがいや仕事のやりがいをどこにもつかを考えて、子供の様子をよく観察してみてください。
構成/浅原孝子 イラスト/有田リリコ

