教科か「探究」かではなく、教科も「探究」も、でなければならない【次期学習指導要領「改訂への道」#特別版03】
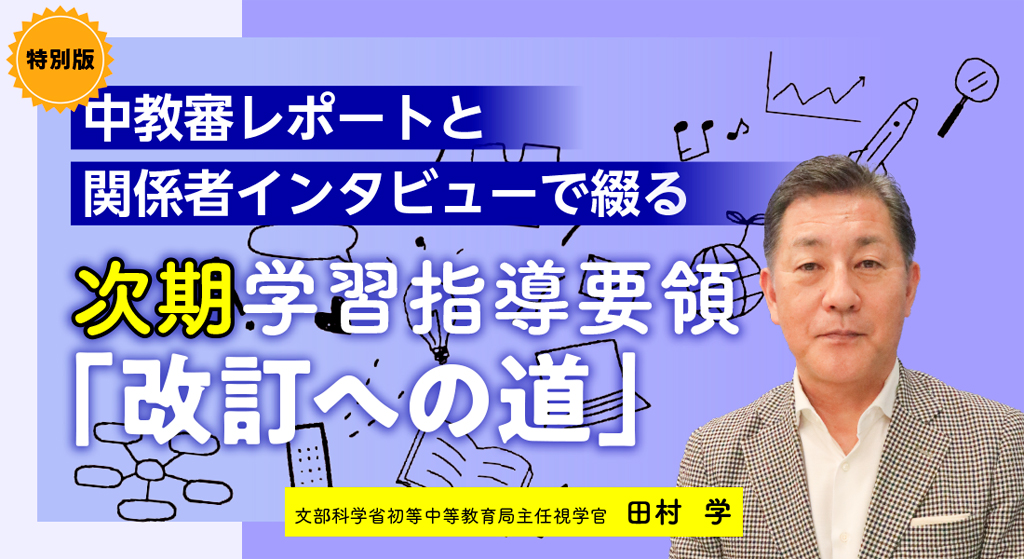
この連載の特別版として、前々回から文部科学省の田村学主任視学官に、「探究」と次期学習指導要領というテーマでお話を伺っています。今回は、改めて学習指導要領における総合的な学習の時間(以下、総合学習)の位置付けを簡単にふり返りつつ、現在明確になってきている「探究」の意味や意義、今後の社会の中でいっそう必要性の高まる「探究」のあり方などについてお話を伺います。
▶「探究」への意識変革には「インパクトと手立てと手応え」の 3 点セット【次期学習指導要領「改訂への道」#特別版01】
▶「探究」の充実と情報活用能力の育成を実現する【次期学習指導要領「改訂への道」#特別版02】
目次
カリキュラム上、よりいっそう総合学習の「探究」が重みを増している
そもそも「探究」を担う総合学習の時数は、導入された平成10年改訂の学習指導要領では105(小学校3、4年)と110(小学校5、6年)でした。それが平成20年改訂のときに、70時間に減りました。ただし、当初は総合学習の中に外国語活動も入っていたため、その少し異なるものを外して、純度を上げていったというイメージでしょう。ですから20年改訂では、外見は減ったけれども、純粋に「探究」を行う時間は確保されていたのです。それだけに、今回の改訂の議論の結果がどのようになっていくかにも注目してほしいと思います。
いずれにしても、カリキュラム上、「探究」の位置付けがどんどん重みを増している状況だと思います。
導入当初は、教科等横断的に総合的な学習の時間を行い、学校の特色ある学習をしていこうというイメージで始まりました。20年改訂で「探究」が明確になって、学びとしての確かさを求めるようになってきて、それが有効であり可能性をもつことが分かる中で、平成29年改訂(現行)では、総則の第2の1に、学校の教育目標を定める際に、総合学習との関連を図ることが示されました(資料参照)。つまり、教育課程の中核に総合学習があるということに近くなったわけです。
【資料】学習指導要領総則の第2の1より
第2 教育課程の編成
1 各学校の教育目標と教育課程の編成
教育課程の編成に当たっては、学校教育全体や各教科等における指導を通して育成を目指す資質・能力を踏まえつつ、各学校の教育目標を明確にするとともに、教育課程の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも共有されるよう努めるものとする。その際、第5章総合的な学習の時間の第2の1に基づき定められる目標との関連を図るものとする。
そして今回の議論では、さらに「探究」をいっそう質的に高めていこうという話が出てきていますから、カリキュラム上、よりいっそう総合学習の「探究」が重みを増しているということは明らかだと思います。この時間を各学校がどのように使うかが、各学校の独自性のある教育課程や子供に期待する資質・能力の育成という点で、外すことのできないものになっています。
カリキュラム上、各教科、道徳、総合学習、特活があるわけですが、総合学習は、これら全体をうまくintegrate(統合)するポジションにあると思います。これが日本のカリキュラムの強みだと思うので、各教科等で学んだことの成果が、ここで統合されてより確かなものになっていくという全体の位置関係が見えてきていると思います。
各教科等と総合学習、Win-Winの関係であり、例えば、国語の時間に学んだ、「立場や意図を明確に話し合う」とか「目的や意図に応じて書くこと」といったことが、教科の中の整えられた場面だけではなく、実社会に近い複雑な場面で使えることが実感できれば、それは国語科でめざすことにもつながるし、その力があるから「探究」も充実するということです。
数学の学習をいつも実社会の場面に合わせて行うとか、国語の学習をいつも地域の方に向けて発表するとなると、それは非常に大変なことになってしまいます。もちろん、そういう学習に価値はあるし、そのような単元もあってよいと思いますが、教科書を基に教室で学ぶことも大事だと思います。
そうなると、総合学習で地域の問題を扱うとか、社会現象に対処する、自らの関心事を探究するというときに、数学で学習した統計を使ったり、国語で学んだ表現を使ったりする場面が設定されることの意義は大きいと思います。
ですから、二者択一の教科か「探究」かではなく、教科も「探究」も、でなければならないのだと思います。

