人体の神秘を実感! 身近な現象を再現する実験の手引き【理科の壺】

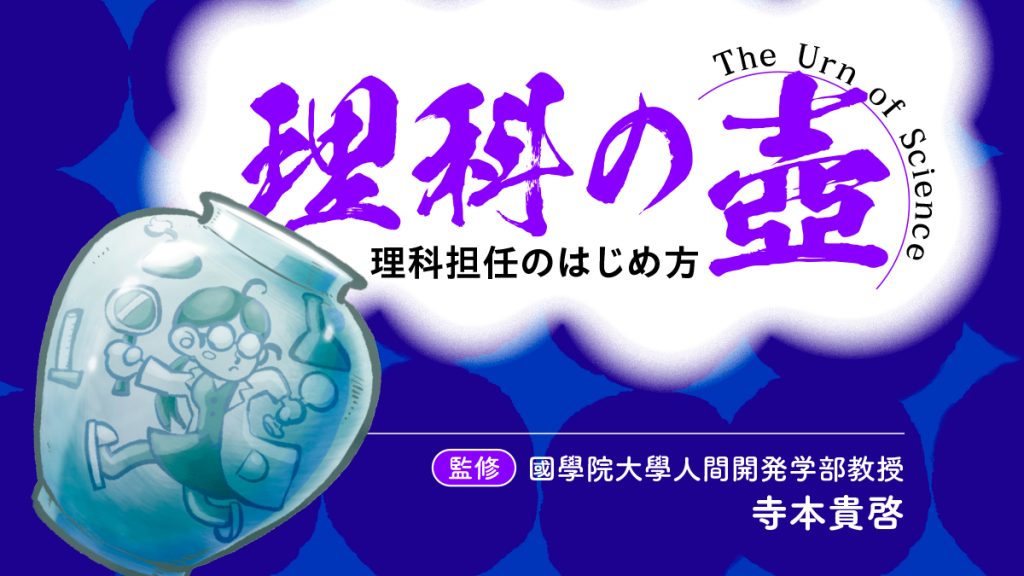
「だ液」の授業は、自分の唾液を使ってご飯のでんぷんがどう変わったかを調べる実験を行うことが一般的ですが、今回は唾液を使わずに行う実験の紹介です。唾液を使いたくないという思いから生まれたこのアイデア、胃腸薬を使って「分解」を再現します。子どもたちの「消化」という“人体のしくみ”への実感を得るために、授業では唾液を使って実験し、その後「分解」という視点で胃腸薬の役割を日常生活とつなげる事例としても面白いです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?
執筆/和歌山市立貴志南小学校教諭・和田慎也
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
“人体のしくみ”を実感をもって学ぶために
6年生の「ヒトや動物の体」の学習では、ヒトや他の動物について、体のつくりと呼吸、消化、排出および循環の働きに着目して学習を進めます。
自らの体の中の不思議を解明していく身近な教材ですが、実験をしていても、どこか実感を得られにくいと感じていました。
今回はその中でも「消化」について、実験を通して実感を得る学習にしていくために取り組んだ実践を紹介します。
1.ご飯を食べてみよう!
身近に起こっている消化の第一歩は口の中ですが、子どもたちの中には漠然と「消化はお腹の中で起こっているもの」というイメージがあります。
そこで、給食の時間に「ご飯を一口食べて、20回ぐらいかんでみて」と声をかけました。すると、普段は意識していない口の中でのご飯の変化に気づく子が出てきます。
昼食後の学習タイムに、米の味の変化、粒の変化、唾液の出方など、その気づきや疑問を話し合う時間を設けると、「口の中で行われていることは消化なのか、どのような変化をしているのか」という問題を考えるきっかけが生まれました。


