トラブルシューティング『冷静な対応で育む問題解決力』

新人教員のための学級安定実践13選⑦
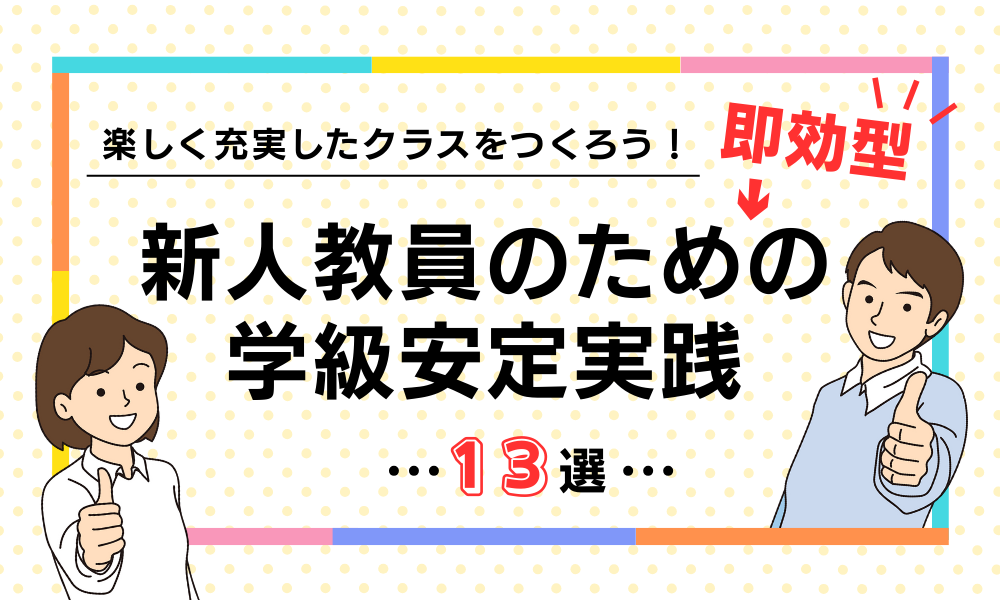
学級内でのトラブルは避けて通れません。しかし、トラブルが発生した時の対応次第で、それは子どもたちの成長機会にも、学級崩壊の原因にもなり得ます。重要なのは、教師が感情的にならずに戦略的に冷静に対処し、子どもたち自身が問題解決能力を身につけられるよう支援することです。
執筆/私立小学校教諭・熱海康太
目次
トラブル対応の基本原則
トラブル対応の基本は「安全確保」「事実確認」「関係修復」の3段階です。まず何よりも、子どもたちの身体的・精神的安全を確保します。けがをしている子がいないか、興奮している子を落ち着かせる必要がないかを最優先で確認します。
次に、感情的にならずに事実を確認します。「誰が悪い」という犯人探しではなく、「何が起きたのか」を冷静に把握することが重要です。一人ひとりから話を聞き、可能であれば目撃をした子の話も集めます。話を聴くときには、一人ずつ聴くことが鉄則です。場の雰囲気に流されてしまったり、力関係があって言いたいことを言えなかったりすると、トラブルが余計に複雑になってしまうことがあります。
最後に、関係の修復を図ります。これは単なる謝罪の強要ではなく、お互いの気持ちを理解し合い、今後同様の問題が起きないようにするための話し合いです。そのために、加害者、被害者というくくりをなくして、両者に指導を行います、被害者に指導することはないように思えるかもしれませんが、今後、同じような被害に合わないためにできる対策については一緒に考えることができます。また、最終的には被害を受けていても、その前には不快になる行動をしてしまっているのであれば、そこを振り返らせることが大切です。

子どもの感情に寄り添う技術
トラブルに巻き込まれた子どもたちは、多くの場合感情的になっています。「なぜこんなことをしたの」と問い詰めるのではなく、まずは感情を受け止めることから始めます。
「悔しかったんだね」「怖い思いをしたんだね」と気持ちを言語化してあげることで、子どもは自分の感情を整理することができます。感情が落ち着いてから、具体的な事実確認と解決策の検討に移ります。
問題解決プロセスの可視化
トラブル解決を単なる「その場しのぎ」に終わらせないために、問題解決のプロセスを子どもたちと共に確認します。「何が問題だったのか」「なぜそれが起きたのか」「どうすれば防げたのか」「今度同じようなことが起きそうになったらどうするか」を順序立てて考えます。
このプロセスを通じて、子どもたちは問題を多角的に捉える力と、建設的な解決策を考える力を身につけることができます。トラブルは、問題解決能力を育む絶好の学習機会なのです。
学級全体での共有と学習
バナーイラスト/futaba(イラストメーカーズ)
イラスト/池和子(イラストメーカーズ)

著者:熱海康太(あつみこうた)
一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事
大学卒業後、神奈川県内の公立学校、私立学校で教鞭を取る。
大手進学塾の教育研究所を経て、現職。
10冊以上の教育書を執筆し、全国10,000人以上の先生方に講演を行うなど、幅広く活動している。

