クレームを申し立てる保護者の本音を引き出す質問力 〜追質問で真意をつかむ〜

保護者クレーム対応の実践スキル 危機を絆に変える技術⑦
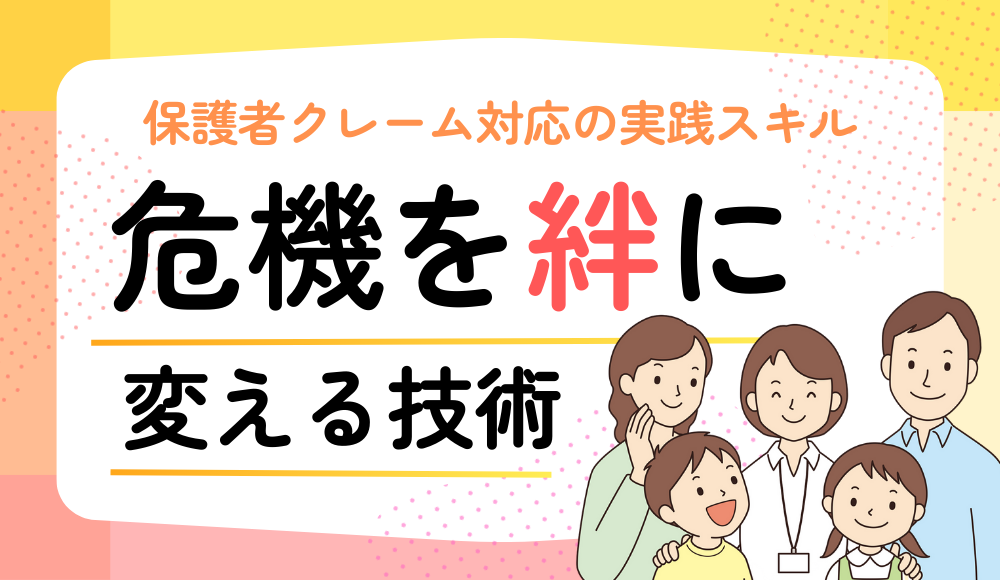
クレーム対応において最も重要なスキルの一つが、相手の本音を引き出す質問力です。多くの場合、保護者が最初に表明する苦情や要求は、真の問題の表面に過ぎません。その奥には、より深い悩みや不安、期待が隠れているものです。
執筆/一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事・熱海康太
目次
表層の訴えと深層の悩みの構造
保護者からのクレームには、必ずといってよいほど表層と深層の二重構造が存在します。表層の訴えは、具体的な出来事や要求として表現されますが、深層の悩みは、より根本的な不安や期待として存在しています。
例えば、「保護者会で先生は『高校から入った子も、内部進学の子もみんな仲良しです』と言っていましたが、それって中学3年間のアドバンテージがないということですよね。3年間は無駄だったんですね」という訴えがあったとします。これは一見、「?」と思う事例ですが、実際にあったクレームを元にしています。表面的には中高一貫教育の価値に対する疑問として表現されていますが、その奥には様々な深層の悩みが隠れている可能性があります。
深層の悩みとしては、子どもの勉強に身が入らない状況への心配、子どもの将来への不安、友人関係でのトラブルの可能性、私立学校に通わせる経済的負担への疑問など、多岐にわたる要因が考えられます。これらの真の悩みを把握せずに表面的な説明だけを行っても、保護者の納得は得られません。
追質問の基本原理
追質問の目的は、相手の表面的な訴えの背景にある真の関心事や悩みを明らかにすることです。効果的な追質問を行うためには、まず相手の訴えを受容し、その上で「なぜそう感じるのか」「どのような期待があったのか」を探っていく姿勢が重要です。
追質問は決して尋問ではありません。相手を問い詰めるのではなく、相手のことをより深く理解したいという姿勢で行うことが大切です。「○○についてもう少し詳しく教えていただけますか」「どのような点がご心配でしょうか」といった、相手への関心と配慮を示す表現を使うことで、相手も安心して本音を話してくれるようになります。
理由と目的を問う技術
効果的な追質問の中でも特に重要なのが、理由や目的を問う質問です。「どのような期待がありましたか」「どのあたりにギャップがありましたか」「何が原因になっているのでしょうか」「もともとの目的は何でしたか」といった質問により、相手の根本的な思いや動機を探ることができます。
先ほどの中高一貫教育の例では、「どのような部分のアドバンテージを期待されていましたか」と追質問することで、保護者が本当に求めていたものを明らかにすることができます。学習面でのアドバンテージなのか、友人関係での安定なのか、大学受験での優位性なのか、具体的な期待内容が明らかになれば、それに応じた適切な対応が可能になります。
具体的事実を問う重要性
バナーイラスト/futaba(イラストメーカーズ)
イラスト/池和子(イラストメーカーズ)

著者:熱海康太(あつみこうた)
一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事
大学卒業後、神奈川県内の公立学校、私立学校で教鞭を取る。
大手進学塾の教育研究所を経て、現職。
10冊以上の教育書を執筆し、全国10,000人以上の先生方に講演を行うなど、幅広く活動している。

