保護者クレームの雰囲気を和らげる言葉術〜クッション言葉とクッション表現〜

保護者クレーム対応の実践スキル 危機を絆に変える技術④
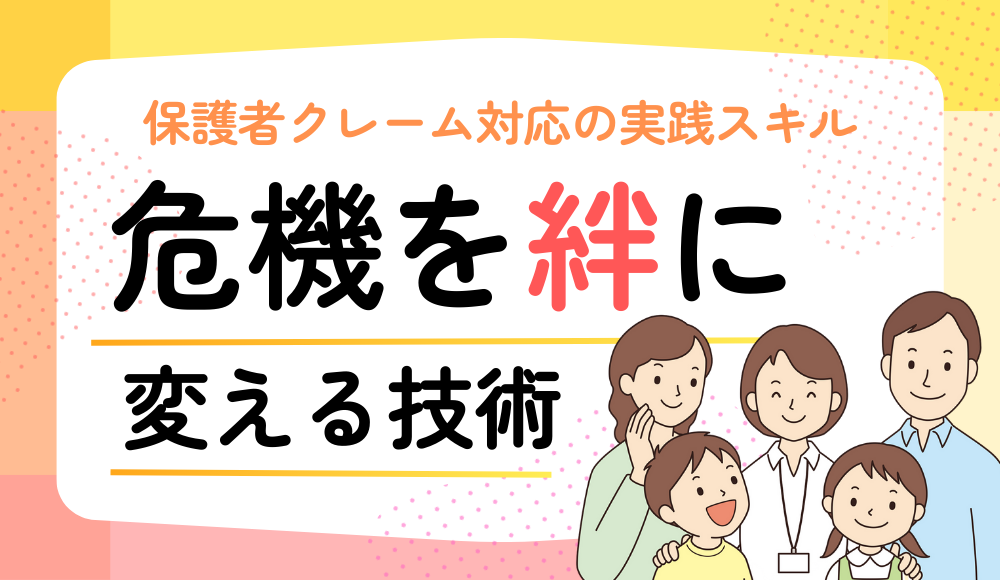
前回は受容・共感・傾聴の3ステップによる初期対応について解説しました。今回は、その基盤の上に築く「言葉の技術」に焦点を当てます。同じ内容を伝える場合でも、使う言葉によって相手の受け取り方は大きく変わります。特に感情的になっている相手に対しては、言葉選びが対話の成否を左右するといっても過言ではありません。
執筆/一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事・熱海康太
目次
クッション言葉の心理学的効果
クッション言葉とは、相手にお願いをしたり、断ったり、難しいことを伝えたりする際に、その前に置く緩衝材のような言葉のことです。これらの言葉は、相手の心理的な抵抗感を和らげ、メッセージをより受け入れやすくする効果があります。
心理学的に見ると、人は突然の要求や否定的な内容に対して、防御的な反応を示しがちです。しかし、クッション言葉を使うことで、相手に心の準備をしてもらい、メッセージを受け取りやすい状態を作ることができます。

場面別、クッション言葉の使い分け
頼みごとをする際には「恐れ入りますが」が効果的です。例えば、保護者に何かを確認したい場合、「恐れ入りますが、お子さんの様子について詳しく教えていただけますでしょうか」と伝えることで、相手に負担をかけることへの配慮を示すことができます。
相手から情報を聞き出したいときには「差し支えなければ」を使います。「差し支えなければ、そのときの詳しい状況を教えていただけますでしょうか」といった形で、相手に選択権があることを示しながら質問することで、プレッシャーを与えずに情報を得ることができます。
何かの行動を求める場合には「大変お手数ですが」を用います。「大変お手数ですが、明日までにご回答をいただけますでしょうか」といった表現により、相手の負担を理解していることを示しつつ、お願いをすることができます。
断らなければならない場合には「あいにくですが」が適切です。「あいにくですが、その日程では都合がつきません」と伝えることで、単なる拒否ではなく、やむを得ない事情があることを暗示することができます。
相手の勘違いを訂正する際には「説明が足らずに失礼いたしました」が効果的です。相手の誤解を直接指摘するのではなく、こちら側の説明不足として処理することで、相手の面子を保ちながら正しい情報を伝えることができます。
クッション表現による印象の変化
クッション表現は、日常よく使う言葉をより丁寧で配慮のある表現に変えることで、相手に与える印象を大きく改善する技術です。これらの表現を使うことで、同じ内容でも相手がより受け入れやすくなります。
「分かりました」を「承知いたしました」に変えることで、より正式で敬意のこもった応答になります。「そんなことないです」を「とんでもございません」に変えることで、相手の意見に対してより丁寧に反応することができます。
「できません」を「いたしかねます」に変えることで、単なる拒否ではなく、やむを得ない事情による辞退であることを示すことができます。「そうです」を「おっしゃる通りです」に変えることで、相手の意見に対してより深い同意と敬意を表現することができます。
行動を制止したい場合、「やめてください」を「お控えください」に変えることで、命令的なニュアンスを和らげることができます。「やらないでください」を「ご遠慮いただければと存じます」に変えることで、より婉曲で丁寧な依頼として伝えることができます。

著者:熱海康太(あつみこうた)
一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事
大学卒業後、神奈川県内の公立学校、私立学校で教鞭を取る。
大手進学塾の教育研究所を経て、現職。
10冊以上の教育書を執筆し、全国10,000人以上の先生方に講演を行うなど、幅広く活動している。

