保護者クレームへの、初期対応の黄金ルールとは?〜受容・共感・傾聴の3ステップ〜

保護者クレーム対応の実践スキル 危機を絆に変える技術③
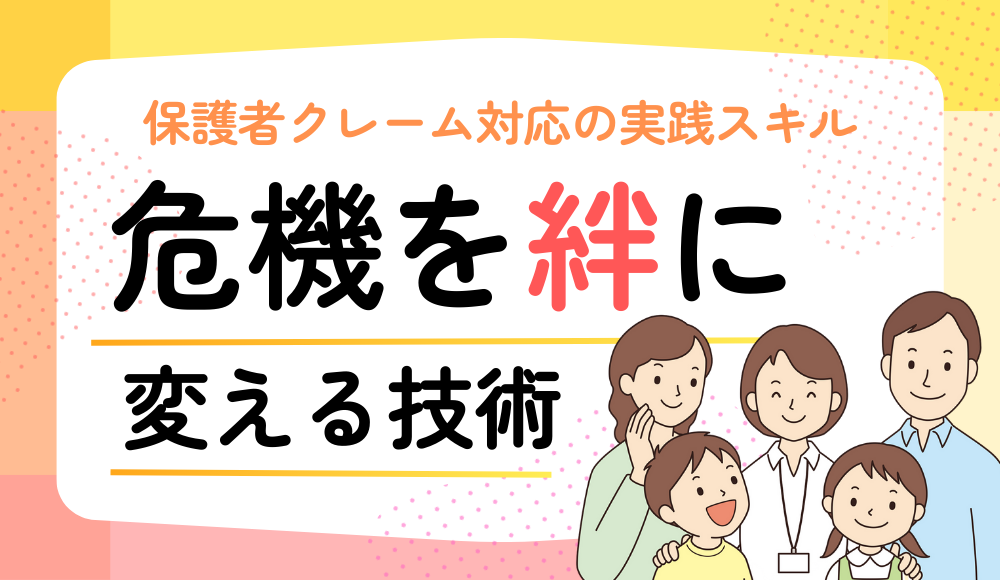
クレーム対応において最も重要なのは、最初の数分間の対応です。この初期対応で相手の感情を落ち着かせ、話し合いの土台を築くことができれば、その後の展開は劇的に変わります。第3回となる今回は、カウンセリングマインドに基づいた「受容・共感・傾聴」の3ステップを中心に、初期対応のルールを詳しく解説していきます。これらの技術を身につけることで、どんなに感情的になっている相手でも、安心して話ができる環境を作り出すことが可能になります。
執筆/一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事・熱海康太
目次
カウンセリングマインドの基本原理
カウンセリングマインドとは、相手の立場に立って理解しようとする姿勢のことです。教育現場でのクレーム対応においても、この考え方は有効です。相手が怒りや不安を抱えているとき、まず必要なのは問題の解決ではなく、相手の気持ちに寄り添うことです。
保護者が感情的になっているからといって、その人を否定的に捉えるのではなく、「この人は子どものことを心配しているからこそ、このような態度を取っているのだ」と理解しようとする姿勢が求められます。
受容の技術とその実践
受容とは、相手の言葉や感情をそのまま受け止めることです。ここで重要なのは、受容することと事実を認めることは全く別だということです。相手が「先生の対応は最悪でした」と言ったとしても、その事実を認める必要はありません。しかし、「そう感じていらっしゃるのですね」と、相手がそう感じているという事実は受け止める必要があります。
具体的な受容の表現としては、「○○さんは、○○と感じていらっしゃるのですね」「○○ということがあったのですね」といった形で、相手の体験や感情を言語化して返すことが効果的です。このとき、相手の言葉をそのまま繰り返すのではなく、相手の気持ちの部分を汲み取って表現することが大切です。
例えば、保護者が「うちの子が体育祭の練習で悪口を言われて、学校に行きたくないと言っている」と訴えてきた場合、「お子さんが悪口を言われて、傷ついていらっしゃるのですね」と受容の姿勢を示すことができます。これにより、保護者は自分の気持ちが理解されたと感じ、感情的な状態から少しずつ落ち着きを取り戻していくことができるのです。
共感の深い理解と実践
共感は受容よりもさらに深いレベルでの理解を意味します。相手の感情に寄り添い、その気持ちを自分のことのように感じ取ろうとする姿勢です。ただし、教育現場での共感には注意が必要です。なぜなら、安易に「分かります」と言ってしまうと、「何が分かるんですか」と反発を招く可能性があるからです。
効果的な共感の表現は、相手の感情を認識し、それに対する心配や申し訳なさを示すことです。「ご心配をおかけして申し訳ございません」という表現は、相手の心配という感情に共感しつつ、教育者として申し訳ないという気持ちを伝える優れた共感のフレーズです。

著者:熱海康太(あつみこうた)
一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事
大学卒業後、神奈川県内の公立学校、私立学校で教鞭を取る。
大手進学塾の教育研究所を経て、現職。
10冊以上の教育書を執筆し、全国10,000人以上の先生方に講演を行うなど、幅広く活動している。

