おもしろ実験を学びに変える! 6年生「ものの燃え方」【理科の壺】

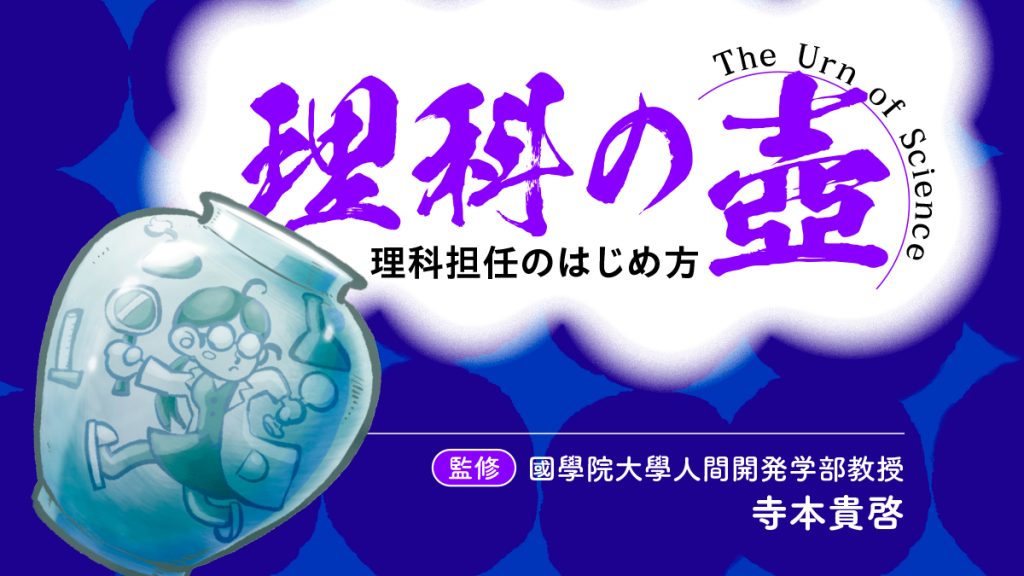
理科の授業の学習内容でないものでも、理科的な内容はたくさんあります。身近なものの中には、子どもたちの興味を掻き立て、授業への導入となる内容もあります。今回は、「酸素は燃えるのを助ける」という既習事項と、「宇宙には空気がないのにどうしてロケットは燃えるの?」という一見相反する日常の事象をつなぎながら、発展的にその理由を確認して学んでいく事例です。子どもたちの断片的な知識と既習事項をどのように広げていくのか、日常の事象とどのようにつなげられるのかが見どころ! 優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?
執筆/森村学園初等部教諭・野村健太
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
おもしろ実験で終わらせない! 学びが深まる理科授業の工夫
理科授業で子どもたちの盛り上がりをつくる手段の一つが「おもしろ実験」です。実験は理科の最大の魅力ですが、ただ「わあ、すごい!」で終わってしまうのはもったいないですよね。
実験をきっかけに、子どもたちが自分で疑問をもち、考え、理解を深めていく体験に変えることができれば、理科の授業はもっと面白くなります。
水中で燃える花火
第6学年の『ものの燃え方』で、子どもたちはすでに「ものが燃えると酸素の一部が使われて二酸化炭素ができる」「酸素は燃えるのを助ける」ということを学習しています。そこで、理解をさらに深めるためにロケットの打ち上げ映像を見せました。
「すごい燃えてる!」「酸素の中でろうそくを燃やしたときみたい」と大興奮する子どもたち。しかし、対話を続けていくとおかしなところがあることに気づきます。
「宇宙には空気がないよね」
「じゃあ、どうしてロケットは燃えるの??」
ここで、固体ロケットの仕組み、
燃えるものと“酸化剤(酸素の役割をする物質)”が一緒に積み込まれている
を説明。
すると、「えっ、そんな単純なの?」と驚きが返ってきます。

ここで教師が「宇宙で燃えるロケットを地上でも再現できないかな?」と問いかけます。
子どもたちから「空気のない宇宙は水で代用できるのでは」というアイデアが出るはずです。この発想は、5年生の『発芽の条件』でインゲンマメの実験を経験していたことが背景にあります。

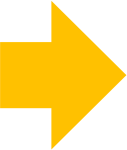

固体ロケットの代用品を子どもたちだけで考えるのは難しいため、教師が手持ち花火が代用できると提示します。

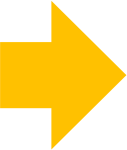

花火を点火し、水の中にいれると、ブクブクと泡を出しながら燃え続ける様子に子どもたちは驚きつつも、「酸素と燃える物があれば、水の中でも燃えるんだ!」と納得(図1)。
この「おもしろ実験」が、「わあ、すごい!」で終わらず、酸素の助燃性をより実感をもって理解するための実験となります。


