教育現場のクレームにはパターンがある?〜注目すべきポイントとその特徴とは〜

保護者クレーム対応の実践スキル 危機を絆に変える技術②
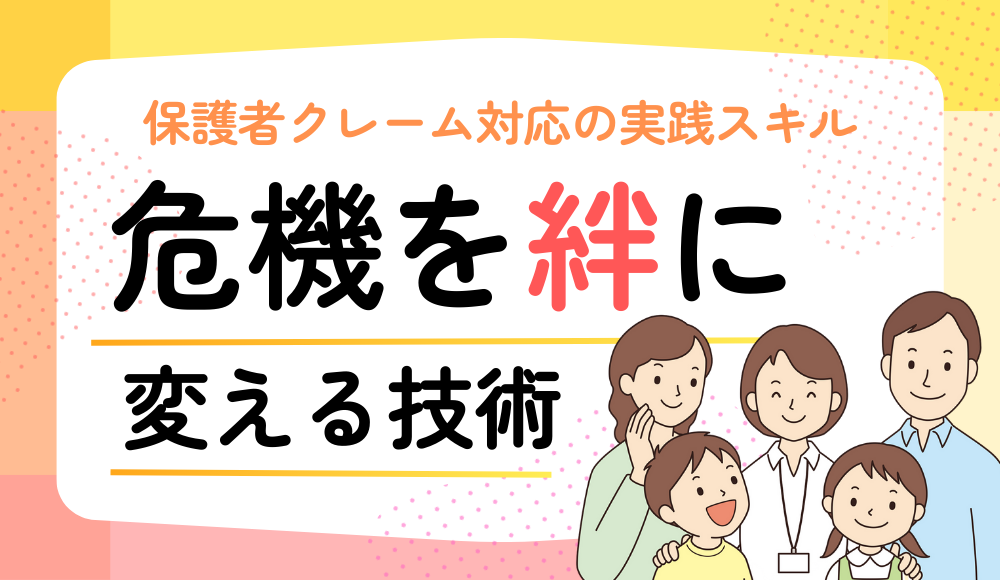
教育現場で発生するクレームは、一見すると理不尽で感情的な訴えに聞こえることがあります。しかし、そのデータを見ると、実は体系的なパターンがあり、注力すべきポイントが存在することがわかります。第2回となる今回は、学校で発生するクレームの種類を確認し、その特徴を理解することで、効果的な対応への見通しを示していきます。問題となりやすいパターンを事前に知ることで、予防的な対応も可能になります。
執筆/一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事・熱海康太
目次
学校クレームの三大分類
東京都教育相談センター「学校問題解決のための手引(令和4年3月改訂)」のデータを見ると、学校に寄せられるクレームは、大きく三つのカテゴリーに分類することができます。まず「態度に関するクレーム」では、教職員の接し方や言動に対する不満が中心となります。「高圧的な態度」「礼儀がない」「だらしない服装」「話を聴かない」といった訴えがこれにあたります。これらは教師の人間性や職業意識に関わる内容であるため、保護者にとって非常に感情的な問題となりやすい特徴があります。
次に「指導に関するクレーム」は、教育の内容や方法についての不満です。「指導が古い」「課題が少ない」「登校渋りが改善されない」「方針が合わない」などが該当します。これらは教育の専門性に関わる内容であり、保護者の教育観や価値観との相違が背景にあることが多く見られます。
最後に「規則、設備等に関するクレーム」は、学校の制度や環境に対する不満です。「校則への不満」「設備の不備」「IT機器の故障」「感染症対策」などがこれにあたります。これらは個人的な問題というよりも、組織や制度に対する改善要求の性格が強いものです。
個人レベルの対応が鍵を握る
学校に寄せられるクレームを種類で見ると、圧倒的に多いのは個人の教職員に対するものです。組織や制度に関するクレームよりも、日々の授業や生活指導の中での一人ひとりの教師の言動が問題となるケースが大半を占めています。一番多いのは、方針に対して異を唱えた際の対応が良くなく(態度が悪いように見えてしまうなど)、さらにクレームに油を注いでしまうパターンです。
これは裏を返せば、個人レベルでの意識と行動を変えることで、多くのクレームを未然に防ぐことができるということを意味しています。
組織的な改革や制度変更には時間と労力がかかりますが、個人の心がけや対応スキルの向上は、今日からでも始められます。一人の教師が丁寧な言葉遣いを心がけ、子どもや保護者への配慮を深めることで、その教師に関わる多くの家庭との信頼関係が向上し、結果として学校全体のクレーム数を大幅に減らすことができるのです。
この現実を踏まえると、組織的な対応システムの構築と並行して、まずは個々の教職員が、管理職も含めて自分自身の言動を見直すことが最も効果的で即効性のあるアプローチといえるでしょう。
受け手の主観が全てを決める時代

著者:熱海康太(あつみこうた)
一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事
大学卒業後、神奈川県内の公立学校、私立学校で教鞭を取る。
大手進学塾の教育研究所を経て、現職。
10冊以上の教育書を執筆し、全国10,000人以上の先生方に講演を行うなど、幅広く活動している。

