「学校サポーター」スキルアップ講座<第3回 学校サポーターになったら確認すること>

近年、先生方の負荷軽減や子供たちの安心・安全な学校生活を支援する目的で学校サポーターを導入する自治体が増えています。活動内容は学校によって様々ですが、学校・学級担任と連携し、子供たちの学習支援や学校生活上の介助、事務的な作業の補助等を行います。今回は、特に学習支援を行う学校サポーター向けに、多様化する教育的ニーズに適切に対応するために事前にどのようなことを確認しておくとよいのか解説します。
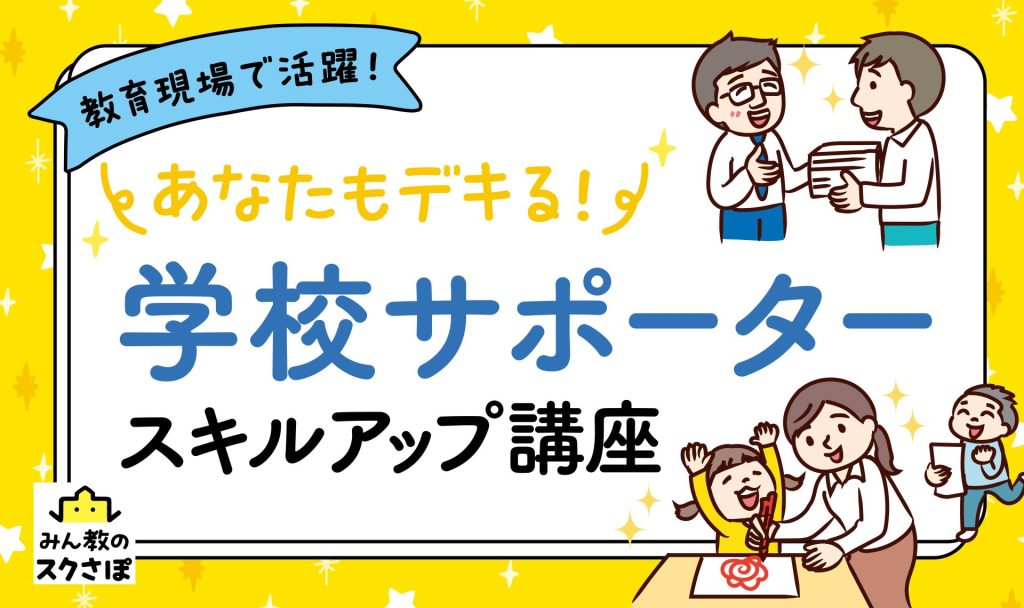
監修/東京都公立小学校教諭 渥美卓哉
※教員以外の立場で学校を支える外部人材は、自治体によって、「支援員」「会計年度職員」「スクール・サポート・スタッフ」「エデュケーション・アシスタント」など様々な名称で呼ばれています。本企画では、教員以外の立場から学校を支える方達を総称して「学校サポーター」と表記しています。
目次
児童・学習支援の学校サポーターが確認しておくべきこと
支援の目的と範囲
- 支援の目的:学校、担任等が重点的にサポートしてほしいことについて、事前にその目的・背景含めできるだけ具体的に打ち合わせしておきましょう。
- 支援の範囲:特に児童・学習支援の場合は、特定の児童を対象とした「個別対応」なのか、「学級全体の支援」なのか、「担任のフォロー」なのかを確認しておきます。
- 休憩時間:事前の打ち合わせ時や面談時に、どこで・いつ休憩をとるのか確認すること。ただし、日常的に休憩時間の変更や調整が発生するため、状況に応じて担任等に確認しながら柔軟に対応します。休み時間=休憩時間ではありません。休み時間は子供たちの見守りや担任との情報共有をする時間であることも多く、急遽対応を求められる作業が発生し実質休憩時間が変動・縮小することもあるので、その都度担任等と相談・調整を行います。
「個別対応」をする場合に確認しておくこと
- 該当児童の学習状況・課題:言葉の理解や表現が難しい、読み書きが苦手など、子供が抱えている課題を把握するとともに、具体的にどのような支援が必要なのかを確認します。
- 性格や特徴:こだわりが強い、音に敏感、衝動的に行動してしまうなど、児童の性格・特徴について把握します。
- 関わり方の程度:常に隣で付き添う必要があるのか、ある程度離れていてもよいのかなど、関わる頻度や距離感、程度などを確認します。
- 支援のゴール:どこまで自立させることを目指しているのか。子供がつまづいている時にどこまで支援してよいのかをヒアリングします。
- 声かけの注意点:声のかけ方やタイミングについてなど、留意点含め確認します。

「学級全体の支援」をする場合に確認しておくこと
- 学級の状況・課題:学級全体の状況、特にどのようなフォローが必要なのかを確認します。
- 特に気を配るべき子供:気になる子、特に配慮が必要な子についてヒアリングすることで、机間指導の時などの際、誰を重点的に支援するとよいのか見通しをもって取り組むことができます。
- 学級全体の回り方、声のかけ方:子供の隣で話しかけてもよいのか、つまづきに気が付いたらすぐに声をかけるべきか、質問された場合にのみ声をかけるのか、担任の指導方針を確認します。
- 支援をする範囲・程度:Aさんには理解するまで教える、Bさんにはヒントだけ与えるなど、授業中に教えてよい範囲、支援する程度を確認することで、子供たちの依存を防ぎつつ適切な支援をすることができます。
- 補助作業の優先順位:子供の安全確保、学習支援、気になる子の心のケアなど学級全体の支援の範囲は多岐にわたります。同時多発的に支援が必要になった場合の為に、あらかじめ優先順位を確認しておくとよいでしょう。
「担任へのフォロー」をする場合に確認すること
- 担任の抱えている課題感や困りごと:各学校、クラスの状況、担任の経験値等によって必要な支援、活動内容は異なります。率直にどのような課題を抱えているのか質問してみましょう。
- 大切にしている教育方針:サポーターはあくまでも担任の補助的役割を担います。担任の教育方針を尊重し、指示に従い活動します。
- 巻き取れる業務がないか観察:どのような業務を、いつまでに終わらせて欲しいのかを確認します。教員は他の人に仕事を委託することに不慣れであることも多いため、教員の業務をよく観察し、単純なデータ入力など、巻き取れる業務をこちらから提案すると喜ばれるでしょう。

理解度をチェックしましょう
【理解度チェック】※答えは記事内にあります!
□支援する範囲・内容については、慣れるまで全体を観察し空気を読んで判断する。(Yes/No)
□休憩時間は、それぞれの授業後の休み時間にとる。(Yes/No)
□「個別対応」の場合は、該当児童の性格、特徴、関わり方の程度を具体的に確認する。(Yes/No)
□「学級全体の支援」の場合は、全員に公平に対応するため、気になる子の把握はしない。(Yes/No)
次回は、学校サポーターとして子供や学級担任と信頼関係を構築するためにどのように関わるとよいのか、子供のトラブルにはどう対応すべきかについて解説します。
【「みん教のスクさぽ」の事業についてご興味のある方はこちらまでご連絡ください!】
「みん教のスクさぽ」準備室 m-sukusapo@shogakukan.co.jp
取材・構成・文/出浦文絵

