クラスでのいじめ。いじめられた子をどうフォローする ?<中高教員の実務>
- 連載
- 中高教員の実務
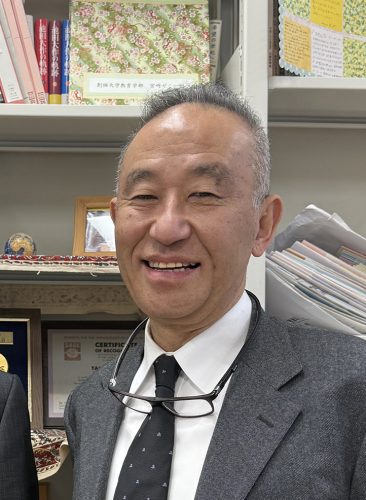

担任は生徒の立場に立って、親身な対応を心がけましょう。保護者や上司、管理職などと連携することも必要です。
編著/小泉博明・宮崎 猛
【特集】中学校・高校教師 実務のすべて#27
クラスでいじめが発覚! いじめられた子はふさぎ込んで、学校にも来られない状態に……。担任として、どう支えてあげればいいんだろう?
生徒のちょっとした変化を見逃さない担任の目が子供を救います。万が一いじめが発覚したら、いじめられた生徒の気持ちを理解し、生徒を全力で守り、学級からいじめをなくしていく熱意を伝え、実行していきましょう。
目次
いじめとは……?
文部科学省が2006(平成18)年度の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」から適用しているいじめの定義は、以下のようなものです。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
(注1)「いじめられた児童生徒の立場に立って」とは、いじめられたとする児童生徒の気持ちを重視することである。
(注2)「一定の人間関係のある者」とは、学校の内外を問わず、例えば、同じ学校・学級や部活動の者、当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人間関係のある者を指す。
(注3)「攻撃」とは、「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわるものではないが、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。
(注4)「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠されたりすることなどを意味する。
(注5)けんか等を除く。
最近のいじめの実態は、見えないところで執拗に行われ、しかも方法や手段がエスカレートしている傾向にあります。生徒のちょっとした変化を見逃さない担任の確かな目が生徒を救うのだということを心得ておきましょう。

また、複雑化・多様化するいじめは、学校だけでは本当のことが見えないことが多くあります。家庭や塾など、学校外での状況についても情報を得ることが望ましいでしょう。
生徒が出すサインを見逃さない
● 笑われる
● 無視される
● 持ち物がなくなる
● 落書きされる
● 一人でいる
● 表情が暗く、おどおどしたところも見える
● 嫌な呼び方をされる
● 付き合う友達が急に変わる
● 保護者から相談される

迅速な対応が鍵! いじめに気づいたら……
1.いじめを受けている生徒の立場に立って、親身な対応をする
イラスト/タバタノリコ・畠山きょうこ

