個の特性に応じることとインクルーシブ教育ー「徹底した個への関心」|インクルーシブ教育を実現するために、今私たちができること #16

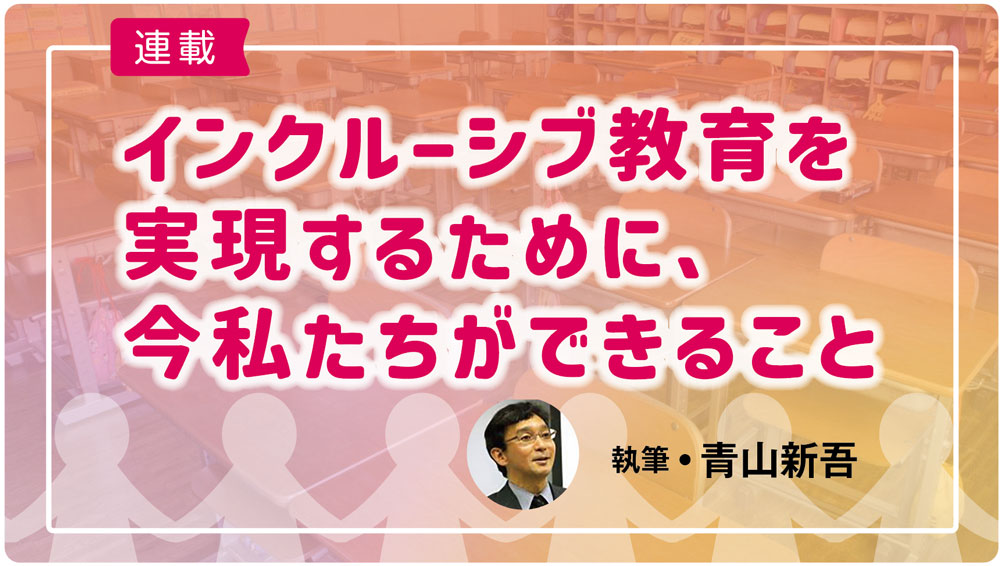
「インクルーシブ教育」を通常学級で実現するためには、どうすればよいのでしょうか? インクルーシブ教育の研究に取り組む青山新吾先生が、現場の先生方の悩みや喜びに寄り添いながら、インクルーシブ教育を実現するために学級担任ができること、すべきことについて解説します。今回は、個の特性に応じることとインクルーシブ教育について考えていきます。
執筆/ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授・インクルーシブ教育研究センター長・青山新吾
目次
インクルーシブ教育とは何か
野口晃菜(2022年)は、「インクルーシブ教育」の対象は虐待をされている子ども、外国にルーツのある子ども、貧困状況にある子ども、性的マイノリティの子ども、障害や病気のある子ども、不登校の子どもなどのマイノリティ属性の子どもを含むすべての子どもたちであるとしています。そして、すべての子どもたちを包摂する教育を目指すプロセスがインクルーシブ教育であり、そのためには、これまでの教育システムを変えていくことが必要だとしています。本連載では、インクルーシブ教育を実現するためには、通常学級の教育が変わっていくことが求められているという前提に立っています。
今回は、「徹底した個への関心」をもち、子どもの特性を大切にした学習指導を行うことでインクルーシブ教育を進めていくヒントを探ります。
個への関わりーある算数の授業でー
ある小学校での話です。算数の時間に1枚のプリントが配られました。
「前からなんばんめ? 後ろからなんばんめ?」と書いてありました。順番に数えることをねらったプリントだと考えられます。切符を買おうとして並んでいる動物のイラストが描かれていました。「うさぎは前からなんばんめでしょう?」という問題が示されました。
ある子どもが元気よく、「1、2、3、4」と描いてある動物を、左側から1匹ずつ指さしながら、4番目のうさぎまで数えることができました。
「そうそう、いいよ!」という先生の声が響きます。

次の問題は、「ぞうは、後ろからなんばんめでしょう?」です。
その子は今回も、「1、2、3、4」と左から動物を指さしながら数えていったのでした。
先生は「問題をよく見て。後ろからなんばんめ? と書いてあるよ」とことばをかけました。子どもはそれを聞きながら、やはり左から数えます。
「よく見て。後ろからと書いてあるところに線を引きましょう」と再度ことばをかけました。子どもは、不思議そうな顔をしながら、フリーハンドで線を引こうとします。
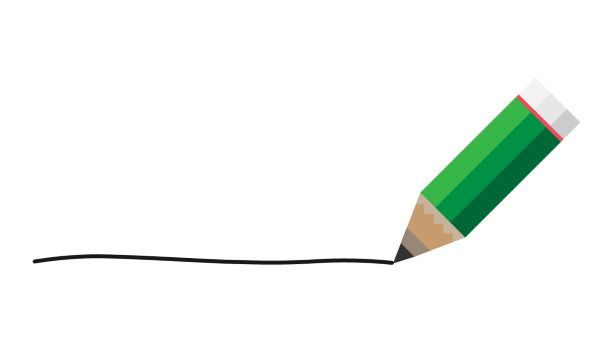
「待って待って。線を引くときはものさしを使いましょうね」と、さらにことばをかけました。
子どもは筆箱の中からものさしを取り出して線を引きます。その後、やはり左から動物を数えたのでした。

