【昭和100年記念リレー連載】昭和世代の教師として、20~30代の教師に伝えたいこと #最終回 野口芳宏 ~こんなことを話し合ってみたい-教師人生を楽しむ仲間へ-

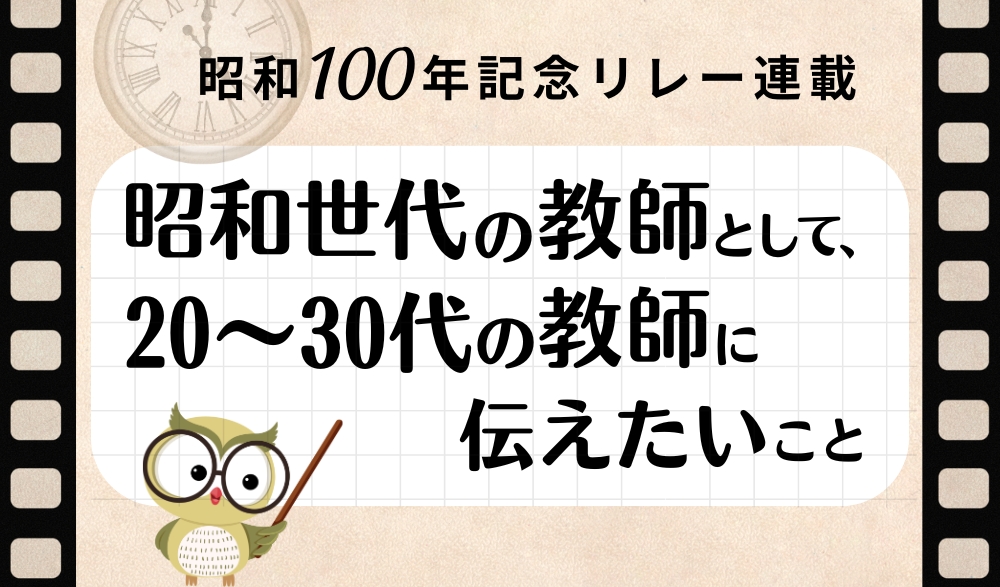
今年は昭和100年。 昭和100年を記念して、今夏、昭和世代の、昭和世代による、令和時代に向けてのセミナーを開催することになりました。そこで、登壇者たちから現在教職に就く皆さんへのメッセージを綴ったリレー連載をお届けします。 昭和世代の熱い想いをお読みいただければと思います。最終回は国語の授業名人、野口芳宏先生によるご寄稿です。
執筆/野口芳宏(植草学園大学名誉教授)
編集委員/堀 裕嗣(北海道公立中学校教諭)
目次
1 「教育現場の現実」の受け止め方
新たな出合いのご縁に感謝申し上げます。
私は満89歳、今回の執筆者の最高齢者でしょう。幸い、健康に恵まれ、今でも求めがあれば国語か道徳の授業を楽しみ、講演活動もし、若い先生方との定期的な勉強会も続けています。66歳から始めた「授業道場 野口塾」は今に続いて22年、通算600回を越えました。嬉しく、有難く、楽しく、感謝いっぱいです。
さて、このリレー連載は「20~30代の現場教員」に向けて「教員としての成長」を目指すためのアドバイスを自由に――との内容です。
そこで、時代を超えて変えてはならない教員としての資質形成について書くことにしました。敗戦後80年を迎え、現在の教育界は残念な状況にあります。不登校、苛め、子供の暴力、子供の自殺等の発生件数が、「過去最多」、それも11年間も続いているという状態です。この現実を貴方はどう解し、受けとめ、対処しますか。以下は、私の考え、受けとめです。
ア、 これらの被害者は「子供」だ。
イ、 加害者は、広くは大人、狭くは教育者だ。
ウ、 どこか教育上の大きな勘違いがあるのではないか。
エ、 被害の現実は子供からの告発、絶叫、悲鳴だ。
オ、 制度いじりでその打開、改善は望めない。
カ、 その打開、改善は教職員の責務だ。
2 何がその元凶か
日本の教員の大方、大多数は、上司や上部機構に対して、忠実、従順、誠実に対し、努力していると、私は信じています。「働き方改革」が叫ばれているのは一つの証左でしょう。教員の努力は限界に来ています。
――とすれば、これは文科省を頂点とする上層、指導部の指示、指令、方針のどこかに問題があるとしか言えなくなります。
忠実、従順、誠実な部下が、限界的努力をしてもなお成果が見られないという指示、指令、方針を、改める動きは目下のところ目立ってはありません。成果の上がらない過去十余年の方針、指示のさらなる継続が学校現場に求められているだけです。
私は、小学校現場でのみ38年間を過ごした実践者です。私も責任を感じ、反省もし、改めたいと考えていることがあります。思いつくままに私の内省と分析を挙げてみましょう。
キ、上層、上司の指示、指令、方針の不備
ク、実践の枝葉、末節、技法への偏向
ケ、根本、本質、原点という不易の軽視
コ、日本の伝統、誇り、自覚の不足
サ、現場の多忙による内省の不足
以上ですが、些か抽象的な指摘に堕したかもしれません。これらを踏まえて、今後具体的に我々実践者は何を、どのようにしていくことが肝要であるかを述べて参考に供したいと考えています。率直な御批判を心から期待し、切望しています。
以下は、全て私の実践を潜らせての、自戒をこめた処方、対策です。なお、以下の論考の文体は、常体分に改めて記述します。
3 常に根本、本質、原点を自問する
多くの場で「授業の主役は誰か」と問い、その解をノートに書いて貰う。結果は、圧倒的に「子供」が多く、「教師」と書く者は例外的に少数だ。今はそう答えないと採用試験では不合格になるのかもしれない。
しかし、これは明らかに誤りだ。学習の主役は子供だが、授業の主役は教員免許の所有者である。プロの教師でさえ「授業」は決して易しくはない。況んや子供に於いてをや、である。
授業のプロである教員に、「授業の本質は」と問い、ノートに書かせると、その解は多様になる。「本質」は、同一になるべきだが、「人間形成」「楽しさ」「集団思考」「発問」「自学」などと、思い思いの解が散らばる。正解は「学力形成」の四文字である。これが書ける教師は極めて少ない。教員の関心は、発問や板書や指示に向けられ、授業の本質や根本が忘れられているのだ。
二つの言葉、「目的」と「目標」のどちらが上位概念か、と問うと、「目標」と答える者が3分の1はいる。「教育の目的」は何か、と問うと、正確に答えられる教員は皆無と言っても過言ではない。これが、日本のプロ教育者の現実である。
海に出るとおびただしい数のボートが浮かび、どのボートも大汗を掻きながら漕がれている。そこで漕ぎ手に向かって「どこに向かっているのか」と問うと、「そんなことは分からないよ。とにかく漕いでいなくちゃ沈んじゃうんだ」という答えが返ってくる。笑いごとではない。これが、現在の日本の教育界の正直な実情である。これでは、教育の実は上がるまい。
日本の子供や青少年の教育は良い成果を上げているかと問うと、圧倒的に「否」という解が多数になる。残念なことだが、これは「正解」と言えよう。これは、家庭、学校、社会の三つともうまくいっていないからなのだが、あえてその中のどこが問題かノートに一つを書けと言ってみるといい。
管理職に聞いても、中間層に問うても、若手に問うてもその傾向は同じになる。圧倒的多数が根本的問題は「家庭」にあると判断して手を挙げる。これは正解か。
解を示すことなく、家庭と学校と社会それぞれの役割の「根本、本質、原点」を問うと、大方が答えられない。家庭の本質は「養育」であり、根本は「安らぎ」「安心」である。社会の本質は「協力」であり、根本は「公共、公益」である。学校の本質は「教育」であり、根本は「心身ともに健康な国民の育成」である。「教育」こそが「学校」の「本質」なのである。この根本を忘れている教育者がいっぱいいる。だから、問題行動「過去最多」という自体が11年間も続くことになるのだ。また、文末の「国民の育成」に着目したい。「心身ともに健康な子供の育成」ではないのだ。「国民の育成」というのは「家庭」や「社会」の構成員そのものを意味する。「根本、本質、原点」を知ること、弁えること、認識し、自覚することがどんなに大切かを改めてお互いに確認したい。
4 「研修」という略語の罪科
「研修」という言葉、用語が日常的に多用されている。「学問・技芸などをみがき修得すること。特に職務に対する理解を深め、習熟するために学習すること」と『大辞林』にはある。
この解説を読む限り、教職員にふさわしい用語のように見える。だが、教育基本法にこの用語は存在しない。実は、これは「研究」と「修養」という二つの教育用語の頭の文字をとって作った「略語」に過ぎない。そして「略語」が多用されることによって、教員としての、教育者としての「根本」が忘れられるようになってしまった。現在の教育の昏迷の大きな一因が、「研修」という略語の多用にもあると私は考えている。「研究」さえしていれば足りる、というのは実は間違いであり、誤解であり罪なのだ。
教育基本法第9条「教員」には次のようにある。「法律に定める学校の教員」は、「自己の崇高な使命」を深く自覚し、絶えず「研究と修養」に励み、その職責の遂行に努めなければならない――と。
「研究」と「修養」が同格で併記されている。「研究」という用語は、学校現場ではいつでも、どこでも多用されている。耳に胝ができるほど多用されている。研究主任もいるし、研究計画も立てられている。
だが、「と」で同格に結ばれて併記されている「修養」なる言葉、用語は、全く、学校の日常には登場しない。忘れ去られ、捨て去られている。私は「全国的な法令違反が日常化されている」と言っている。この重大事に関し、文科省も、地方教委も触れたことがない。敢えて忘れさせているのか、とさえ思いたくなるほど敗戦後80年一貫して無視されている。「研究」という名に於いて教員がやっている内実は、全て子供の教育、改善についての実践である。子供の生活習慣、子供の読書、子供の学力、子供の人間性等々の向上推進である。私はずばり一言で、これを「他者改善」と呼んでいる。
「修養」とは「学問を修め精神を磨き、人格を高めるよう努力すること」である。私は、これを、「教師自身」の「自己改善」と呼ぶことにしている。
「修養」の語に触れる度に思い出されることがある。私が新採用された年の祝賀の式典の折に、然る来賓から贈られた「進みつつある教師のみ、人を教ふる権利あり」という、ドイツの教育学者ジェステルリッヒの言葉の由だ。この言葉を初めて聞いた時、私は背筋を何かが走り抜けるような感動を味わった。「そうだ!教師は子供の誰よりも常に学ばなければならないのだ!」と心の底から思い、そうあろうと密かに誓ったことである。今もその志に変わりはない。他者改善を志すならば、率先垂範、自らこそがまずその体現者たらねばならないとの自戒である。
自らが学ばずして子供を学ばしめようとするのは愚かであり、自ら本を読むことをせずして子供の読書を促すのも愚かであろう。
自らの力不足を知って、不断の学びに励む教師の生き方が子供を引きつけ、子供に良質の感化、影響を生むのである。この根本、本質、原点の忘却、軽視こそが現代の教育の荒廃を生んでいるのだ、と私は思うのだがどうであろう。
思いがけなく、7年余りに亘って私は千葉県の教育委員を拝命したことがある。就任早々「県教委の発出文書には研修の語を排し、研究と修養という正式表記に改めたい」と発言した。当初ほとんど問題にされなかったが、就任3年めにしてこの発言が採用された。修養という用語が県下の学校でちらほら使われ始めたが、今ではどうなっているだろうか。
5 良き師につき、良き師に学ぶ
人間としてのあるべき成長、あるべき姿、を具現する為には三つの縁に恵まれるべきだ、との教えがある。「良き師、良き友、良き書物」の三つである。
私は、この三つの類稀なる良縁に恵まれたことを心の底から嬉しく思っている。有難く思っている。――私の父も小学校の教員だったが、師範学校在学時代に「生涯の師」と出合い、「生涯の幸せ」に恵まれた。私の生母は10歳の私を残して31歳で他界した。敗戦の年の4月のことだ。父に召集令状がくれば、私は孤児になる。父は、恩師に無礼を承知で恩師の娘さんの来嫁を請う手紙を出した。折り返し「迎えに来い」との有難い返信を押し戴いて父は新潟県の新発田市に向かった。
この母の鴻恩によって今の私がある。母は今105歳の超寿で元気である。私もこのような「生涯の師」に逢えることを願いつつ長じたのだが、その師に出合えたのは22歳の新任地でのことだった。詳細は『国語教師・新名人への道』(拙著・明治図書出版)や『教師の覚悟 授業名人・野口芳宏小伝』(松澤正仁/著・さくら社)に譲りたい。
「師を持つ」「師を戴く」ためには、自らの未熟を知らねばならない。伸びたい、学びたいという強い願いが必要だ。慢心や傲りは師を必要としない。
自らが高く伸びれば伸びるほど師を求め、低いままの人ほど師を求めることをしない。人格の高い人ほど師に学び、品性の低い者ほど学ぶことを忘れて慢心する。「進みつつある教師のみ人を教ふる権利あり」なのだ。
6 良き友を選び、親しむ
「朱に交われば赤くなる」「類は友を呼ぶ」と言う。私は、本当に良い友に恵まれた。交友は30年、40年にも及び、中には60年を越す友もある。家内とも60年、昨年はダイヤモンド婚式を祝われた。共に健康に感謝しつつ、105歳の母の介護を楽しんでいる。
私の「友」は、例外なく「学び好き」であり、「読書好き」であり、「酒好き」で「話好き」であり、「一級の教師」「誠実な人柄」の持ち主である。例外は一人とてない。会うことが楽しみで、別れるとすぐまた会いたくなる。お互いに会うと幸せになり、楽しみ、話も弾み、元気が出て、酒も進む。教師人生を楽しむ実感に酔う。
そういう友達が、北は北海道から南は鹿児島、沖縄まで、国内各地にいる。どこに行っても「やあ、やあ」と再会が楽しめる。私は、全ての友達を「仲間」と呼んでいる。「彼も仲間」「彼女も仲間」なのである。「弟子」ではない。「同格」「互角」の「友」である。家族同様の「仲間」や「友」になっている例もある。
89歳ともなると、大方の友はもうこの世にいない。生き残りはごく少数だ。小中学校の同窓会も、高校、大学のそれも解散した。生き残りの幸運者にも、心身の衰えが迫り、生きる辛さも話題になり、それが笑いの種になることもある。残る時間も長くは無い。
お世話になった師も、友も、鬼籍に入ったとなればもはや会うことは叶わない。だが、写真や、書物での出合いならば叶う。
人がこの世を去りゆく時、
手に入れたものは全て失い、
与えたものだけが残る。
大好きな言葉だが今も出典不明である。「全て失う」ことが分かっているのに、それを手に入れようと狂奔する姿は憐れである。「残る」に値する「与えたもの」に大きな意味がある。
7 良き書物との出合い
「出会うべき人には必ず出会う。
しかも、一瞬早からず、一瞬遅からず」
と言ったのは、神戸大学の森信三先生だ。
私は、森先生とはとうとう直接はお会い出来ず終いになったのだが、先生の書物にはいつでも会える。有難いことだ。
改めて思うのだ。「書物ほど安くて、書物ほど価値の高い物はない」という言葉の真実である。電気も要らない。道具も不要。こちらの都合で必要なときに開けばいいし、要らない時には閉じればよい。文句も言わない。本は至っておとなしい。持ち運びにも嵩張らないし、さして重くもない。萎れもしないし腐りもしない。そこに内蔵されている知見、学識の広さ、深さ、重さは計り知れない。本ほど安い宝はない。
生涯の師と仰いだ我が平田篤資先生が、最初に私に紹介して下さった書物は『馬鹿について 人間―この愚かなるもの』(ホルスト・ガイヤー/著、満田久敏、泰井俊三/訳・創元社)という本だった。お借りして読んだのだが、読後に自分でも求めた。今も書棚にある。65年ほども昔のことだ。この本に出合って私は物の見方が少し変わったように思う。
もはやうろ覚えだが、
「教育の成果と思いがちだが、大方は発達の生む成果である。時に教育は人を望ましく育てることもあるが、多くの場合、人は教育にもかかわらず、良く成長するものだ。」
というような意味の一節があった。「教育」をあまり高く買いかぶるなという戒めである。平田先生との出合いがなければ、決して私が出合うことなどなかった貴重な一冊である。この本は、今も手に入る超ロングセラー本である。
人としてまともな成長を願うものならば、「良き師」に出合うのが一番だ。それに匹敵する「良き友」に出合うこともあろう。師にも、友にも会えないのなら「良き書物」になら会える。ブックオフに行くと、価値の低い本は高いが、価値の高い本ほど価格は安い。客のレベルが高いほど金はかからない。「学び心」さえあれば、どこでもいつでも学べるという良き時代が現代である。
8 私を支える私の言葉
私の89年の人生の中で、口癖のように言っているうちに、いつの間にか私を支えることになった私の言葉を、思いつくままに記して稿を閉じることにしたい。詳細は『教育語録・硬派で鍛える』(拙著・明治図書出版)、『教師の心に響く 55の名言』(拙著・学陽書房)ほかの「野口芳宏語録」を参照して下されば光栄である。
インターネットで私の名を入れて検索をされると別の語録も手に入る。
①本音、実感、我がハート
(常に、自分に忠実に生きたい)
② 与えられた世界でベストに生きる
(この世界が私の生きる場所なのだ)
③ 結果幸福論
(今の結果が私にとっては幸福なのだ)
④ 思うようにはならないのがこの世の掟
(既に有ったこの世に、私は後から生まれて来たのだ)
⑤幸せは、感謝の中にしかない
(不平や不満を言っているうちは不幸せ)
⑥頼まれたら断らない
(相手本位、他者本位、利己の末路は破滅しかない)
⑦「観」を磨く
(観とは、物の見方、考え方、受け止め方。豊かな観が人生を豊かにしてくれる)

<今回の執筆者のプロフィール>
のぐち・よしひろ。植草学園大学名誉教授。1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、65年以上にわたり、教育実践に携わる。小学校校長を退職後は、北海道教育大学教授(国語教育)、植草学園大学教授を歴任。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ、著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。

