10のポイントで解説! 新学期にぜひ導入したい、心理的安全性のある学級経営術。

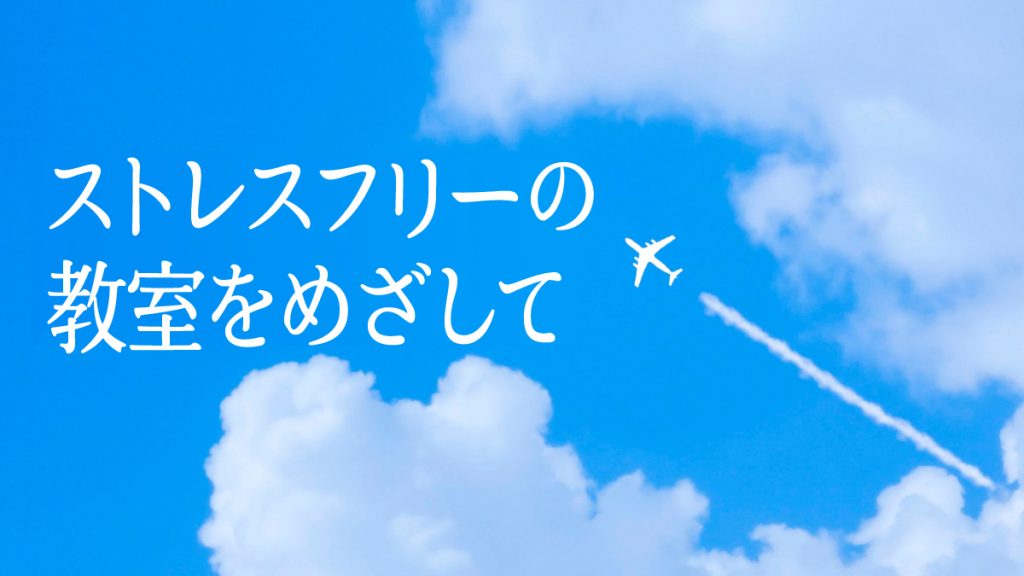
近年、教育現場で「心理的安全性」という言葉が注目を集めています。心理的安全性とは、「自分の意見や考えを自由に表現できる」「失敗を恐れず行動できる」と感じられる環境のことを指します。心理的安全性のある教室では、子どもたちが安心して学び、他者と協力し、挑戦することができます。今回は、教室の心理的安全性を高めるために先生ができることについて考えたいと思います。
【連載】ストレスフリーの教室をめざして #31
執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀
目次
心理的安全性とは?
心理的安全性は、アメリカの心理学者エイミー・エドモンドソンによって提唱され、Googleのプロジェクト・アリストテレス※でチームの成功要因として広く認識されました。この研究では、心理的安全性が高いチームほど、自由な発言やアイディアの共有が活発であり、結果として成果が上がることが報告されています。ビジネスの世界で注目されたこの概念は、教育の現場、特に教室においても「学びの基盤」として重要になります。
※プロジェクト・アリストテレス=生産性が高いチームの共通点を発見することを目指し、Googleが2012年に行ったリサーチ。
心理的安全性が高まると?
教室の心理的安全性が高まることで、子どもたちにはどのような影響があるのでしょうか。
学習面では、子どもたちは「間違えても良い」「意見を自由に発言できる」と感じるため、授業に対する積極的な姿勢が育まれます。また、失敗や挑戦を恐れずに行動することで、難しい課題に対しても前向きに取り組むようになるでしょう。
心理・社会面では、いじめなどの問題行動を防止する効果も期待されます。自分の意見が尊重されるということは、すなわち自分という存在を受け入れられている、という集団に対する受容感が生まれるということです。自分の意見が尊重される経験を重ねることで、自己肯定感や自己効力感が向上し、人間関係があたたかいものへと変容していきます。
このように、心理的安全性の高い教室は、学習だけでなく、子どもたちが未来に向けた成長を実現する基盤となっていくのです。

