「社会的に共有された調整(SSRL)」とは?【知っておきたい教育用語】
これからの学校教育がめざす「子どもの学びの姿」を語るとき、探究する力の育成が重視されています。そのためには、自ら学習を調整しながら学びを進めていく、つまり「自己調整力」が重要です。この”調整力”は自己にとどまらず、他者や属する集団との関係性のなかでの「学びの調整」も注目されています。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴
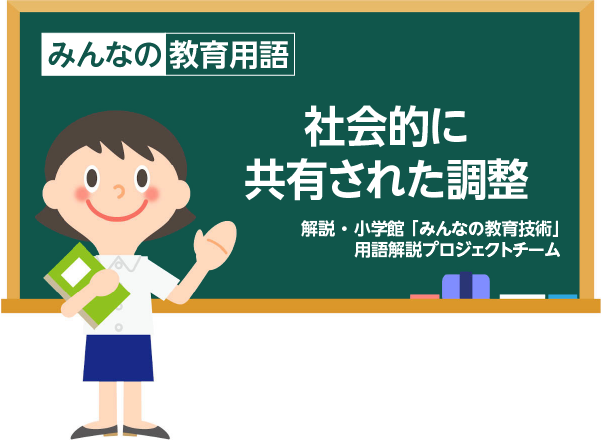
目次
「社会的に共有された調整(SSRL)」とは
【社会的に共有された調整(SSRL)】
社会的に共有された調整とは、学習者がグループ内で相互に影響を与え合いながら、学習の目標設定、進捗のモニタリング、戦略の調整などを共同で行うプロセスのこと。”Socially Shared Regulation of Learning”の頭文字をとって、「SSRL」とも呼ばれる(以下、SSRL)。
「SSRL」は、個人の自己調整学習を超えて、友達や教員など他者との協働的に学習を進める環境において、メンバー全員が学習の調整に積極的に関与することを強調する概念です。
グループ内でのメタ認知的活動や動機づけ、行動の調整が共有されることで、学習効果の向上や深い理解の促進につながるとされています。
「SSRL」を重視する背景
現在の学校現場では、知識の習得への偏重を見直し、思考力や判断力、表現力、その原動力ともいえる「学びに向かう力」といった「生きる力」の育成が求められています。その中で、協働的な学習活動が注目されており、SSRLの考え方は、その中核をなす位置づけにあると考えられます。
これまでの学習活動でも、まず自分の考えや意見をノートなどに書き出し、それをもとにグループで話し合ったり、実験・観察、調査したりすることが行われてきました。その過程では、メンバーがお互いの考えを交流させることで理解を深め合い、学習の方向性を共有しながら進めることで、個々の学習者の能力を最大限に引き出すことをめざしていたはずです。
この状態はまさに「社会的に共有された調整」を図りながら学びを深めている姿だといえます。つまり、これまでも大切にしてきた学びのプロセスを一層重視し、その手だてや成果の振り返りを意識的に工夫していくことが指導者に求められているのです。
SSRLは、学習者が自らの学習過程を意識的に調整する能力、すなわち、メタ認知能力の育成にも寄与するとされています。グループ内での対話やフィードバックを通じて、学習者は自分の理解度や学習戦略を見直し、必要に応じて修正する力(=自己の学習調整力)を向上させるのです。

