【連載】坂内智之先生の 愛着に課題を抱えた子が伸びるアプローチ~学級担任にできること~#6 愛着の課題を乗り越える授業、どうつくる?<前編>―実践編その2―
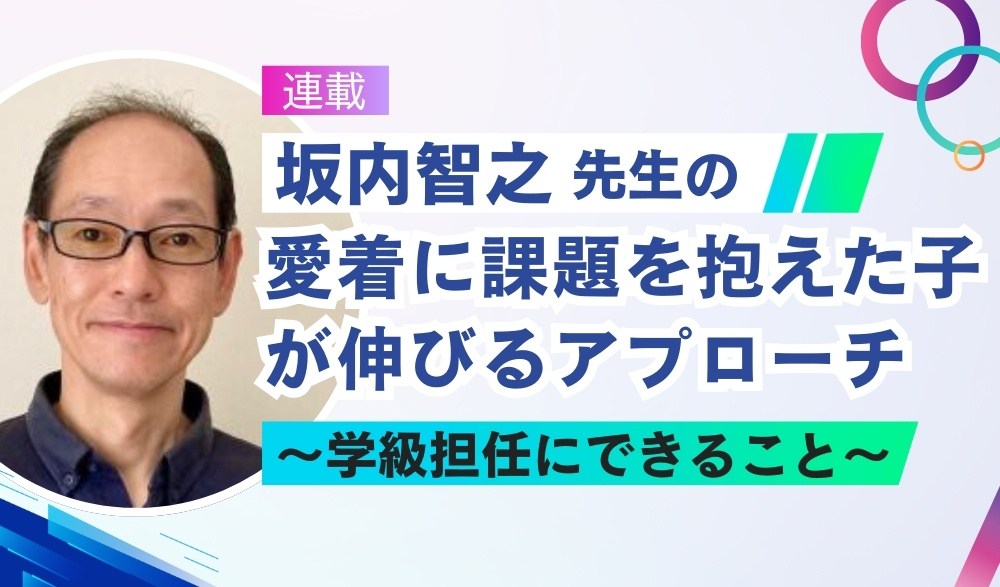
近年、教員たちが対応に苦慮し、学校現場を根底から揺るがしている「愛着障害に苦しむ子どもたち」。そうした子どもたちによって荒れた学級を何度も立て直してきた坂内先生が、今、学級担任に何ができるのかを提案し、これからの学級のあり方について考えていく連載第6回。今回は実践編の第2回。いよいよ授業による具体的なアプローチについて提案していきます。
執筆/福島県公立小学校教諭・坂内智之
目次
はじめに
私の授業スタイルは主に共同(協働)※型の学習です。子どもの主体性を基盤に、学習課題の解決を展開していくスタイルです。近年の子どもの変化を敏感に捉えることができたのは、私の授業が子どもの主体性、つまり子どもの探索機能を活用した授業スタイルだからです。
以前でしたら、子どもに課題を投げかけると、子どもは一斉に探索(探求)に走り出しました。ところが近年ではこうした授業が成立しにくくなってきたと感じることが多くなり、それが子どもの変化について捉えるきっかけとなりました。
学校生活の大半は「授業」の時間です。文部科学省による「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の最新データによると、現場での観察通り、小学校3・4年生で問題行動が増えてきています。私はその最も大きな原因として、授業に課題があるのだろうと考えています。
今回はこの「授業」に焦点を当て、愛着の観点から、現状の授業の何が問題なのか、授業をどう改善していけばよいのかを考えていくきっかけになればと思います。
※「共同」とは、共通する目的のため、クラスみんなで同じことを行うことを指し、「協働」は、立場や活動が異なりながらも、共通の目的を達成するために、それぞれが協力して働くことを表します。
1 なぜ授業なのか
繰り返しお伝えしてきたように、近年の小学校現場では3・4年生のクラス運営がとても難しいものとなっています。特に3年生は、私が見聞きし、担任してきた中で今、最も難しい学年だと感じます。
これまで私が4年生の担任をすることが多かったのは、3年生での学級の不安定さから学級経営が安定せず、その立て直しとしてバトンタッチされてきたからです。
では、なぜ3年生の学級経営が難しいのでしょうか。私はその最も大きな原因が「授業」にあると考えています。学校生活の大半の時間は授業です。もし、この授業が子どもの心によい状態をもたらすものであるならば、学校でのトラブルはほとんど起こらないでしょう。そう考えると、3・4年生の授業の中に、何か子どもの問題行動を助長する要因があるはずです。
1・2年生とは何が違うのでしょうか。私は、二つの大きな要因があるのではないかと考えています。
その一つは学習内容の定着の強化(いきすぎた学力向上対策)です。
そして二つ目は学習教科や学び方、子ども同士の関係の広がりです。
学校における生徒指導関連の各種データが明確に悪化し始めたのは、全国学力状況調査の結果が可視化され、学校評価や競争を用いた各自治体における学力向上の取組強化の時期と重なります。
近年では全国学力状況調査とは別に、ほとんどの都道府県で独自の学力テストを行うようにもなりました。それは6年生だけでなく多くが3・4年生の段階から実施され、数値を上昇させることが教師の評価にもつながるようになってきています。
現場では、学習の定着のため、より強い指導や大量のプリントによる知識の定着が図られるようになりました。さらには「家庭との連携が大切だ」と、宿題も徹底されるようになりました。
こうした知識・理解の強化は、厳格な授業規律や、より強い指導(言葉)へとつながっていきます。
そうなると、愛着の課題を抱え、不安感の強い子どもたちは、授業に不適応を起こしがちになります。
特に教師の望むような学力を満たせない子どもや認知にゆらぎのある子どもにとっては、安心が満たされず、授業は苦痛そのものになっていきます。授業から逃げ出す子ども、授業をあきらめてしまう子どもが増えてくるのも、3・4年生という「学力が見えやすくなる」この時期と重なっています。
また、この時期には課題に取り組むことをあきらめ、ノートや教科書を開かず、授業中何もしない子どもも目立ち始めます。学力が低く、内容を理解できない子どもたちは、不登校となる割合が高くなり、それは中学校進学後にさらに顕著になっていきます。近年の学校ではこうした「授業に耐えられない」という不安を抱える児童や生徒がかなり多いのではないかと推測されます。
実際、不登校の子どもの中には、学校の中に、個別対応で安心できる学びの環境があると、登校できるようになる子がいます。そうした子は決して学習そのものが嫌で学校に登校できないわけではなく、授業というシステムに課題があるために適応できないのだろうと考えられます。
心の基盤の弱い子どもたちは、「どうせやっても無理」「どうせみんなと同じようにできない」という感情から、他の子の学習を妨げたり、課題に取り組まなかったりという姿を、授業の中で見せているのです。
また、3年生では新たに理科や社会科、総合的な学習の時間などが加わり、教科の数が増えます。これまで具体を中心としていた学習内容に、目には見えない抽象的な概念が加わり始めます。
愛着形成に課題のある子どもたちは、新しい教科や抽象的で分かりにくい概念への対応がうまくできず、不安を感じやすいように見受けられます。なぜなら、教科が広がり、抽象的なものに対応するには、愛着でいう「探索機能(探究)」がとても重要になるからです。
「安全」や「安心」の基盤が弱い子どもたちは、こうした学習の広がりに対して不安や苦痛を感じてしまいます。理科や社会科、総合的な学習の時間という教科では、自分で調べてまとめるなど、自律的な学びが要求され、探索する力も必要になります。
併せてグループやチームなど、集団での活動も多くなります。そのためクラスの仲間と協力・協調していかなければなりませんが、愛着形成の弱い子どもは、他者よりも自分の感情を優先させてしまい、トラブルになることが増えていきます。
このように、学習内容の広がりは、不安を抱える子どもの授業からの逃避や妨害、または無反応な姿となって表れてきます。
また、そうした子たちは不適切な言動を繰り返し、周りの友達が困っていたとしても、それを理解しにくいという特性も持っています。こうしたことが重なり合い、授業はどんどん混乱していきます。
私は、これらの理由から、3年生以降、学校への不適応の問題が大きくなっているのだと分析しています。もちろん、その問題は早ければ1・2年生でも起こり始めますし、改善されなければ5・6年生、そして中学校へと続いていきます。
私たち教師がまず改善すべきなのは、こうした課題を抱える授業そのものなのです。

坂内智之プロフィール
ばんない・ともゆき。1968年福島県生まれ。 東京学芸大学教育学部卒業。福島県公立小学校教諭。協働学習の授業実践家で「学びの共同体」から『学び合い』の授業を経て、20年以上にわたり、協働学習の授業実践を続ける。近年では「てつがく」を取り入れた授業実践を行う。 共著に『子どもの書く力が飛躍的に伸びる!学びのカリキュラム・マネジメント』(学事出版)、『放射線になんか、まけないぞ!』(太郞次郎社エディタス)がある。

