不要物を学校に持ってくる生徒にどう指導する?<中高教員の実務>
- 連載
- 中高教員の実務
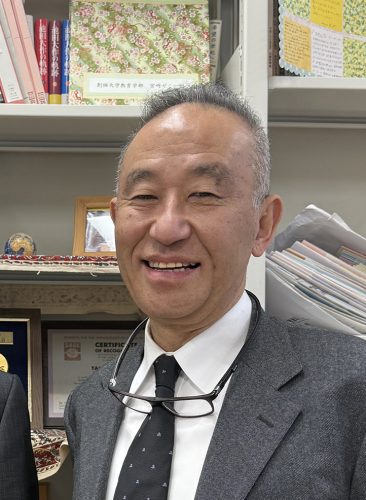

もしも生徒が不要物を持ってきてしまった場合には、今後同じことが起こらないように注意することはもちろん、生徒個人への指導や、これからどうしたらよいか考えさせることを徹底しましょう。
編著/小泉博明・宮崎 猛
【特集】中学校・高校教師 実務のすべて#20
教室内に、たまに落ちているアメやスナック菓子の包み紙。これって、ちゃんと指導したほうがいいですよね?
学習に不要なものは学校に持ってこないのが原則。校内にアメやスナック菓子の包み紙が目立つようになったり、特定の生徒が不要物をくり返し持ってきたりするようであれば、その事実を学級や学年全体に話し、集団の規範意識を高めるようにします。
目次
生徒個人に指導する
不要物を見つけたときも、感情的にならずに落ち着いて話します。
1.なぜ持ってきて(食べて)しまったのか、理由や状況を聞きます。

2.「少しくらいならいい」「バレなければ構わない」など、ルールを守ろうとする意識が低い場合が多いので、なぜいけないのかをきちんと話します。
3.これからの生活について、頑張ることの大切さを話し、目標をもたせます。

指導しても改善されない、また、ルール違反の意識が希薄である場合には、保護者に事実を伝え、不要なものを学校に持ってこさせないよう家庭の協力を求めることも考えられます。
指導のポイント
小事が大事
個人でも集団においても、小さいルールを守ることが大きな崩れや乱れを防ぐことにつながる。だから、アメやスナック菓子など小さなルール違反でも、見逃すことはできない。
決まりを守って、みんな楽しく
みんなが決まりを守る集団は、楽しく過ごしやすい。
我慢することを覚えよう
学校や社会など、多くの人が生活する集団では、一人のわがままは全体に迷惑がかかる。我慢することを覚えよう。
これから頑張ることが大事
一人の頑張りは、自分自身が成長するだけでなく、周りの人によい影響を与える。
生徒に考えさせる
生徒の問題行動をきっかけに、よりよい集団に高めていきましょう。
イラスト/タバタノリコ・畠山きょうこ

