問題の見いだしって難しい!? 【理科の壺】

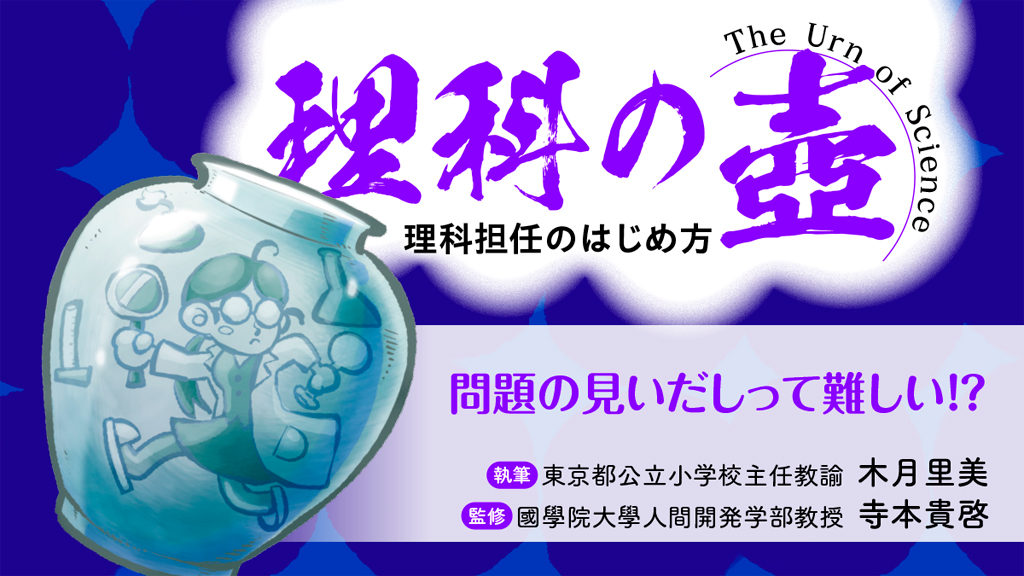
問題を見いだす導入場面をやっても、先生の思い通りの問題に寄せることができず困ってしまう⋯という声をよく聞きます。その理由として、問題になる視点が拡がってしまうということ、検証不可能な疑問レベルの問題で止まっているということがあります。今回は、検証可能か確認しながら問題の設定をする授業アイデアです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/東京都公立小学校主任教諭・木月里美
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
問題解決のスタートはやはり、問題を見つけるところから。でも、子どもが自ら問題を見いだすのって難しい? そんなことはありません。子どもたちは「なぜだろう」「不思議だな」を見つけるのは大人よりもずっと得意!
「理科の問題は『~だろうか』の文脈で検証可能なものにすべきでは?」
なんて最初から考え過ぎてしまうと、授業づくりが難しくなってしまいます。子どもたちが問題を見いだす力をいきなり育てようとせずに、まずは、子どもたち一人一人の「知りたい」を大切に、授業をスタートしてみませんか。
問題の見いだしは、3年生で主に育てたい問題解決の力とされています。しかし、4年生だって、5年生だって、6年生だって、問題解決のスタートはやっぱり問題の見いだしから。付箋を使って子どもたちが見つけた「知りたい」「調べたい」を基にしながら、授業を進めていくアイデアを紹介します。

