【シリーズ】高田保則 先生presents 通級指導教室の凸凹な日々。♯6 不登校は特別支援教育の対象ではないのか?
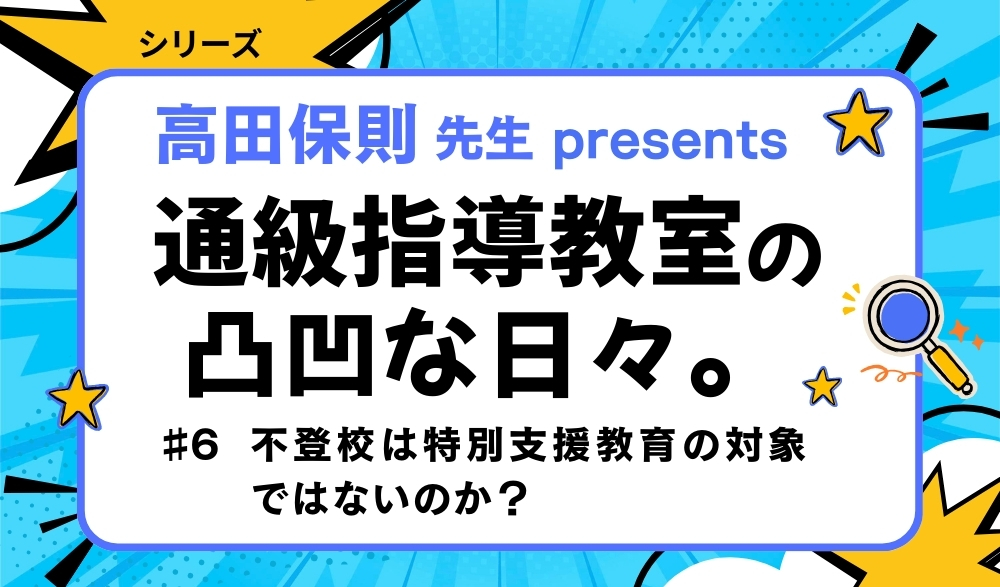
通級指導教室担当・高田保則先生が、多様な個性をもつ子どもたちの凸凹と自らの凸凹が織りなす山あり谷ありの日常をレポート。情熱とアイデアでいっぱいの実践例の数々は、特別支援教育に関わる全ての方々に勇気と元気を与えるはずです。今回のテーマは「通級指導教室に別室登校する子どもたち」です。
執筆/北海道公立小学校通級指導教室担当・高田保則
目次
はじめに
北海道のオホーツク地方の小学校で、通級指導教室の担当をしている高田保則(たかだやすのり)です。日々、子どもたちと向き合ってきた中で、感じた事や考えた事を記していきたいと思います。
なお、通級指導教室で出会った子どもたちの事例は、過去の事例を組み合わせた架空のものであることをご承知おきください。
今回は、『不登校』をテーマに記してみました。登校渋りや頻繁な遅刻と欠席、“まだら登校”や長期欠席、引きこもりなど、登校意欲が低下して起きる子どもの不適応の表れ方は様々です。その中でも、別室登校についてエピソードを記したいと思います。別室登校をしている子どもの居場所として、通級指導教室が活用されるケースがあるのです。ご感想をお寄せいただけますと、嬉しいです。
1.学校不適応のラスボスとしての不登校
私は通級指導教室の担当と校内の特別支援教育コーディネーターを兼務してきました。様々な教育相談や校内支援に携わる中で、子どもを救う手だてが見つからないケースがありました。それは、学級崩壊と不登校です。これらは、子どもが示す不適応の2大ラスボスだと感じています。
学級崩壊と不登校への特効薬なんてありません。担任と子どもの関係が修復不可能になっているのが学級崩壊で、子どもが学校との関係を断ち切ろうとしているのが不登校なのだと見立てています。どちらも一度ハマったら抜け出せない底なしの沼です。教職員ができる唯一の有効な手立ては、予防的対応しかないと思っています。
文部科学省の統計によれば、不登校の児童生徒数は35万人に達しています。私が住むオホーツク管内の全人口が26万人です。ものすごい数だと思います。
今回は、教職員が対処に苦慮するラスボスの一つの不登校について、関わった実践と思うところを記したいと思います。

