<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #14 徳島県石井町立石井小学校5年3組③<後編>

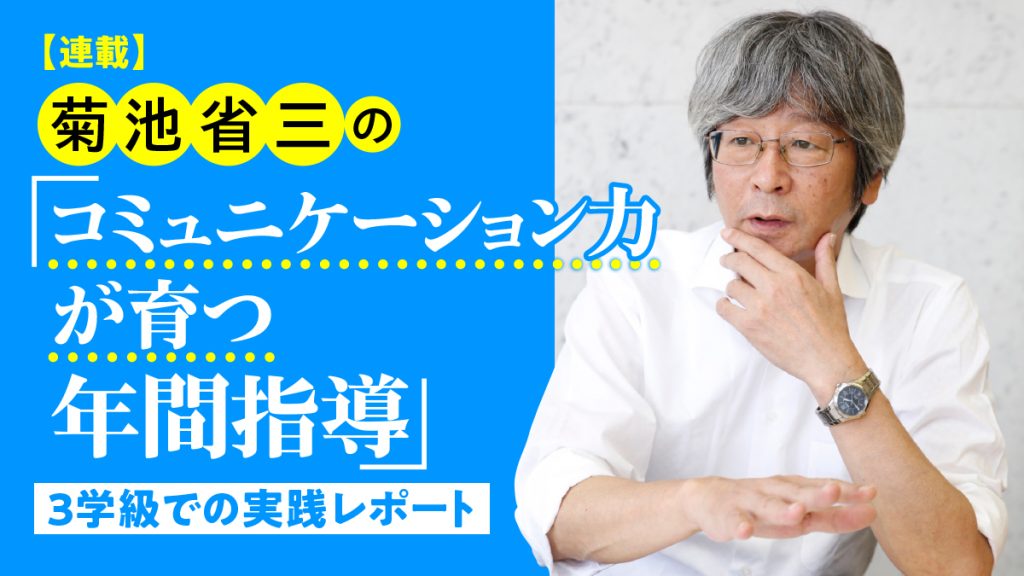
菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする連載。今回は、徳島の堀井学級(5年生)における、11月下旬の授業レポートの第2回です。菊池先生と堀井先生による、2時間続きの「熟議」の合同授業です。

目次
たくさん出した意見の中から、「一番解決したいこと」を話し合う
<自分や相手のことをもっと理解するためにはどうすればよいか>について熟議をしている子供たち。それぞれが問題を出し合い、その中から班ごとに「一番解決したいこと」を決めることにした。
「一番解決したいことが決まったら、具体的にどうするかを考えていきます。例えば、さっきみんなが取り組んできた『ほめ言葉のシャワーのときにはこうする』『質問タイムのときには、こんな交流をする』とルールを考えたり、ポスターを作ったりしながら、具体的な解決のアイデアを考えていきます。
まず自分の考えをピンク色の付箋紙に書いて出し合いましょう」
堀井先生の指示に、子供たちは自分の考えをピンク色の付箋紙に書き込み、再び、顔を近づけ合いながら模造紙に貼り出していった。
堀井先生が班を回りながら、子供たちの話し合いに耳を傾ける。
「さっき、『質問が出たら、もう一歩踏み込んだ質問を続ける』という意見があったね」と堀井先生が聞くと、女子が、
「あ、それって、(堀井先生が話していた)『質問を重ねる』ということですか?」と尋ねた。
「そう。質問したことを、他の人がもう一歩踏み込んで、さらに質問することだったね。それについて答えたら、次の人がさらに掘り下げて尋ねればもっと深まる。一つのことをつなげてずっと質問していくのが、『質問を重ねる』ということなんだよ。だから、単に『質問タイムの仕方を工夫する』と提案するだけじゃなくて、『こんなシステムに変えたら、もっと掘り下げられる』という新しいルールを考えたり、やり方を変える提案があったりしてもおもしろいかも。連動させるルールにするとかね」
堀井先生のアドバイスにうなずく子供たち。
「男女関係なく、3人以上と交流する」
「温かい聞き合いをする」
「質問タイムのとき、相手の長所を質問する」
友達の意見に、大きな声で「いいねえ!」と声をかけ合いながら、子供たちは模造紙にピンクの付箋紙を貼り足していった。
![]()
コミュニケーションは、「一緒に楽しい時間を過ごそう」と思う、相手軸視点が欠かせません。相手を理解するには、「聞く」ことが大切なポイントになります。
ところが、教室で話し合い活動を行うと、教師は「話す」指導に傾きがちです。知的な学び合いも一緒に成長し合うことも、「話す」「聞く」=「聞き合う」ことが大切なのに、「聞く」ことはおざなりになってしまう。「話す」行為は自分中心になるため、相手軸に立って考えるところまではなかなか行きません。そのため、このような話し合いで問題点を出し合ったとき、マイナスの要因を「相手」に持って行きがちになるのです。
青い付箋紙で問題点を出し合ったとき、多くの子供たちが、問題点を「相手」に持っていきました。しかし、熟議での話し合いを通して、聞き合うことができてくれば、それがひっくり返ります。相手ではなく、自分の中に問題があることに気づく。そのように当事者意識を持つことができれば、“日本一” の話し合いにより近づいていきます。
担任は、ピンクの付箋紙の内容がどう変わっていくかを注視しながら、言葉をかけていくことが大切です。
「一番解決したいこと」が決まったら、具体的な解決策を話し合う
ピンクの付箋紙を貼り出し終えたら、発表準備。「どうすればいいか」出し合った具体策を1~3個に絞っていく。
<興味を持っていない>ことを課題に挙げた班では、子供たちが意見を出し合っていた。
「私は、相手に興味を持つことだと思う。1人でもその人に興味を持てば、次の人も『この人のことを知りたいな』となるかもしれないから」
「『あまり関わりない人にも興味を持つ』という意見とつながるね」
「少しでも誰かの個性や性格に興味を持てば、知ろうとするから、質問するようになると思う」
「『質問タイムで掘り下げる』は、掘り下げること自体が興味を持とうとすることだと思う」
「『興味を持っていない』ことが問題なのに、『興味を持つようにする』が答えだと、何をすればいいのか伝わらないね」
「質問タイムのとき、質問される人は、自分の長所を質問された方が、『自分に興味を持ってくれている』と思うのでは」
「相手の側に立った、いい意見だね。『相手の長所を質問する』っていう具体的な意見が出たね」
話し合いながら具体策が決まったら、新しい模造紙に発表項目を書き込み、発表の準備に取りかかった。

