「がん教育」とは?【知っておきたい教育用語】
国立がん研究センターの情報によると、現在、日本人の2人に1人は一生のうちに何らかのがんになるといわれています。全ての人にとって身近な病気であるがんについて正しく学ぶ「がん教育」の重要性が高まっています。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・宮崎猛
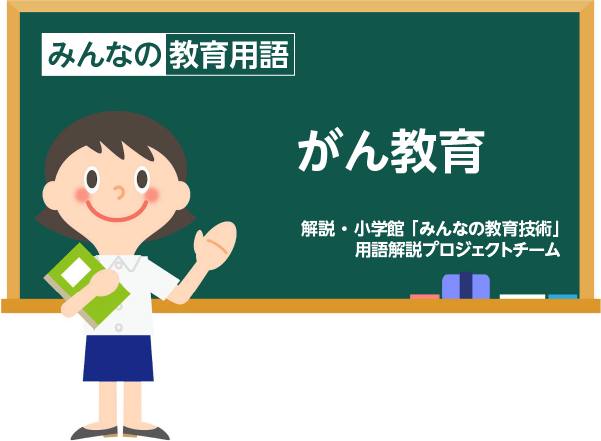
目次
がん教育とは
【がん教育】
がんに関する正しい知識と理解を深め、予防・早期発見・治療、さらには生存者支援へとつなげるための教育。医療現場や学校、地域など多様な場で実施され、科学的根拠に基づいた情報提供を通じ、個々人の健康管理意識を高め、社会全体でのがんに対する理解と支援体制の構築をめざしている。
近年、がんは罹患率・死亡率ともに増加しており、国民の健康に大きな影響を与える疾患として社会的関心が高まっています。一方、インターネットやマスメディアを通じた情報発信の拡大により、誤情報や偏った認識が広がるリスクも浮上してきています。また、治療法の進歩や早期発見による生存率向上が実現する一方で、患者や家族が直面する心理的・社会的課題も深刻化しています。
こうした背景から、がんに対する正確な知識を普及し、予防行動や適切な受診を促す教育の必要性が強調され、学校教育や地域活動、医療連携を軸とした、がん教育プログラムの導入が進められています。各機関が連携し、偏見を解消しながら正しい情報提供に努める取組が、社会全体でのがん対策において不可欠と認識されてきたのです。
がん教育の目標と内容
がん教育の主要な目標はがんに関する正確な知識を普及し、予防意識および早期発見の重要性を啓発することにあります。具体的にはがんの原因やリスク要因、生活習慣との関連、最新の治療法やケアの方法について、科学的根拠に基づく情報を提供することです。
これにより、一人一人が日常生活で適切な健康管理を実践し、異変を感じた際には早期に医療機関を受診する行動変容を促すことを目的としています。また、がん患者やその家族への理解と支援の向上、さらには地域社会全体でのサポート体制の構築も重要な課題です。
学校現場では講義やワークショップ、体験学習を通じ、子どもたちにがんに対する正しい知識と自己管理能力を養うプログラムの実施が奨励されています。さらに、医療機関や専門家による最新情報の提供、ディスカッションやグループ学習を通じた相互理解の促進、そしてがんに関する倫理的・社会的問題への考察も取り入れられています。
これらの取組によって、がんに対する不安の軽減と偏見の解消につなげ、個人の健康意識の向上のみならず、社会全体でのがん対策の強化に寄与するものと期待されています。
学習指導要領との関連
学習指導要領では健康教育の一環として、がんを含む生活習慣病予防や早期発見の重要性が明確に位置づけられています。学校でのがん教育は単なる知識の伝達にとどまらず、自己管理能力や情報リテラシーの育成を通して、子ども自身が健康リスクを正しく認識し、日常生活での予防行動を実践できるよう促すことを目的としています。
具体的な指導内容としてはがんの原因や予防策、治療の現状などの科学的情報を学ばせるとともに、健康に関する実践的な活動やディスカッション、地域連携イベントなどが取り入れられています。助成を活用した外部講師の招聘なども奨励されており、作成された教材や各地での実践事例なども文部科学省のホームページに紹介されています。
学校現場でのがん教育は子どもが正確な知識を身につけ、予防意識や健康リテラシーを向上させる重要な機会です。授業や実践的な学習を通じ、がんに対する正しい理解を深め、偏見をなくす取組が求められます。教育現場での積極的ながん教育の実施は、未来の健康社会の礎となるでしょう。
▼参考資料
がん情報サービス(ウェブサイト)「がんという病気について」国立がん研究センター
文部科学省(PDF)「学校におけるがん教育の在り方について 報告」「がん教育」の在り方に関する検討会、平成27年3月
文部科学省(PDF)「がん教育推進のための教材」平成28年4月(令和3年3月一部改訂)
文部科学省(PDF)「山梨県におけるがん教育の実践について」山本晃司、小池賀津江
文部科学省(PDF)「鹿児島県におけるがん教育の実践について」松元徹、三好綾
新潟県教育委員会(PDF)「学校におけるがん教育の手引き」平成31年2月

