【シリーズ】高田保則 先生presents 通級指導教室の凸凹な日々。♯4 算数を「嫌いすぎる」子を、どう支援する?
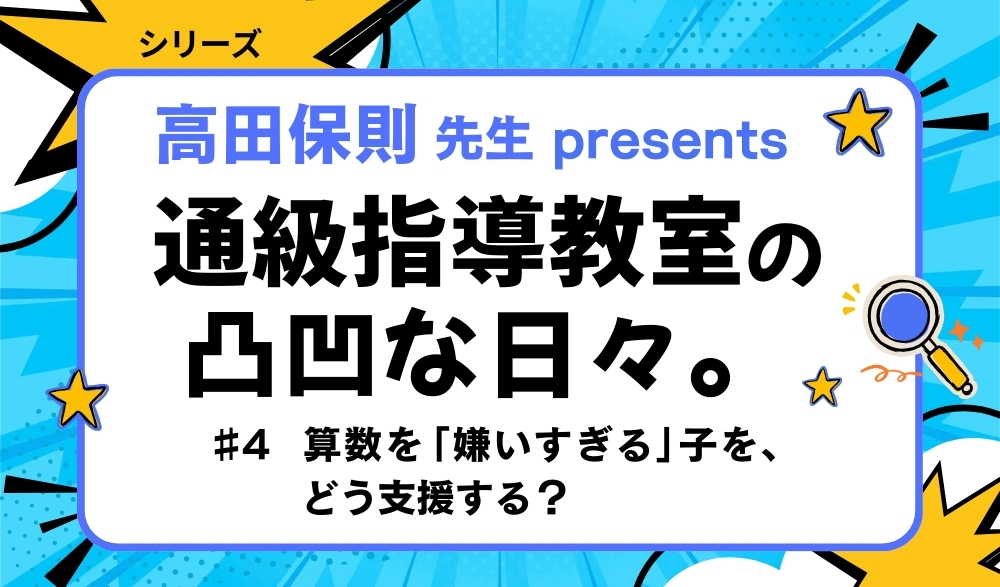
通級指導教室担当・高田保則先生が、多様な個性をもつ子どもたちの凸凹と自らの凸凹が織りなす山あり谷ありの日常をレポート。アイデアあふれる実践例の数々は、特別支援教育に関わる全ての方々に勇気と元気を与えるはずです。今回のテーマは「学習意欲を伸ばす支援」です。
執筆/北海道公立小学校通級指導教室担当・高田保則
目次
はじめに
北海道のオホーツク地方の小学校で、通級指導教室の担当をしている高田保則(たかだやすのり)です。日々、子どもたちと向き合ってきた中で、感じた事や考えた事を記していきたいと思います。
なお、通級指導教室で出会った子どもたちの事例は、過去の事例を組み合わせた架空のものであることをご承知おきください。
今回は、『学習面の困りに寄り添う』というテーマで記してみました。学習面の苦戦を通級指導教室に訴えてくる子は多いです。特に算数が苦手な子は、授業が苦痛で仕方ないようです。積み重ねが大事という理由で、できないと放課後に居残りの補充指導が待っていたりします。
算数が嫌い過ぎて、時々学校を休んでしまっている女の子のcoolなエピソードを紹介します。私の実践の中で、最高にぶっ飛んだエピソードかもしれません。もちろん架空の事例です。エピソードを通して、子どもの学習意欲について考えてみました。ご感想をお寄せいただけますと、嬉しいです。
0.指を使っちゃダメですか?
低学年の算数の授業の様子をフラフラと入り込んで観察します。すると、指を折って一生懸命計算している子がいます。私が近づくと、気配に気づいて、サッと机の下に手を隠します。そういう子、いませんか? 算数の授業で、「指使っちゃダメ!」と教員が釘を刺す光景は、さすがに見られなくなりました。子どもは、具体物から半具体物、そして念頭操作で計算するようになります。指計算は、半具体物から念頭操作に至る橋渡しとなる子どもの計算の発達の大切な過程です。それを根拠もなく否定していた昭和世代の教員は、さすがに現場から居なくなりました。居るのかな? 居たら怖いなぁ。
そんな指計算派のmさんのエピソードを紹介します。

