小5特別活動「5年生になって」指導アイデア

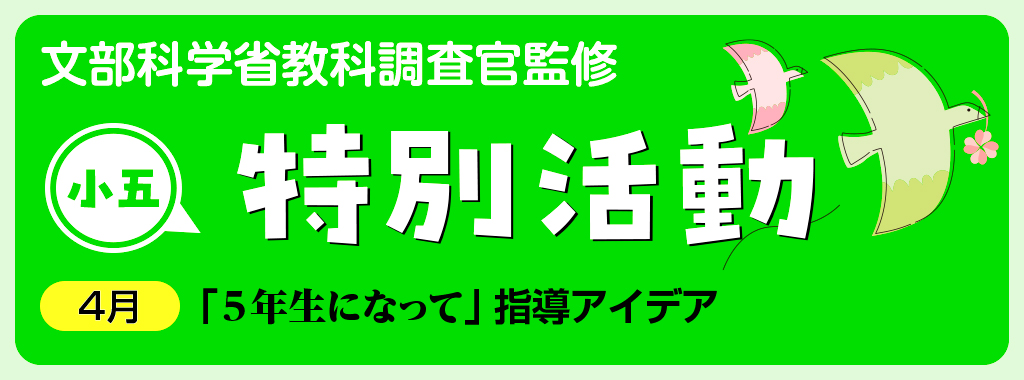
文部科学省教科調査官監修による、小5特別活動の指導アイデアです。4月は、学級活動⑶「5年生になって」の実践を紹介します。
新しい学年に進級し、期待に胸を膨らませている5年生。進級時にはクラス替えをする学校も多いことでしょう。新たな出会いにどきどきしながら、「高学年として頑張るぞ!」という気持ちと「大丈夫かな?」という気持ちが入り交じっている子供たちを温かく受け止め、5年生の学校生活に期待を抱くような場や機会を創出していきたいものです。
高学年としての新たな一歩を踏み出した5年生の子供たち。4月スタートにあたり、夢や希望をもってこれからのよりよい学校生活を目指していくことの意義や、自己の生き方を考える時間を設けることで、楽しく豊かな学級や学校の生活づくりに主体的に関わることができるような実践が大切となります。そこで、「なりたい自分」に向けて、自分に合った目標や具体的な実践方法を意思決定する実践を行います。
執筆/青森県公立小学校教諭・久田麻子
監修/文部科学省教科調査官 和久井伸彦
青森県公立小学校校長・河村雅庸
目次
年間執筆計画
4月 学級活動⑶ ア 5年生になって
5月 学級活動⑶ イ 自分からできることを
6月 学級活動⑴ 雨の日の遊びを決めよう
7月 学級活動⑴ Go!5!クラス運動会をしよう
9月 学級活動⑵ ウ メディアの使い方
10月 学級活動⑴ 交流会の思い出を伝えよう
11月 学級活動⑴ 絆祭りをしよう
12月 学級活動⑵ ウ すいみんプロジェクト
1月 学級活動⑴ 高学年パワーアップ会をしよう
2月 学級活動⑵ イ 気持ちのよい接し方・言葉遣い
3月 学級活動⑴ 思い出会をしよう
本題材のねらい
5年生は、学校行事や委員会活動等で6年生とともに学校生活をよりよくするために活動する場面が多くなります。期待と不安をもつ子供たちが、これまでの成長や自分のよさに気付くことで自信をもち、高学年としての「なりたい自分」を思い描きながら「学校生活をよりよくしていくために、どんなことをしたいのか」「どんな1年を過ごしたいのか」などについて学級の話合いを生かして考えを深め、具体的な目標を決めていきます。

