小1特別活動「みんなでなかよくあそぼうかいをしよう」指導アイデア

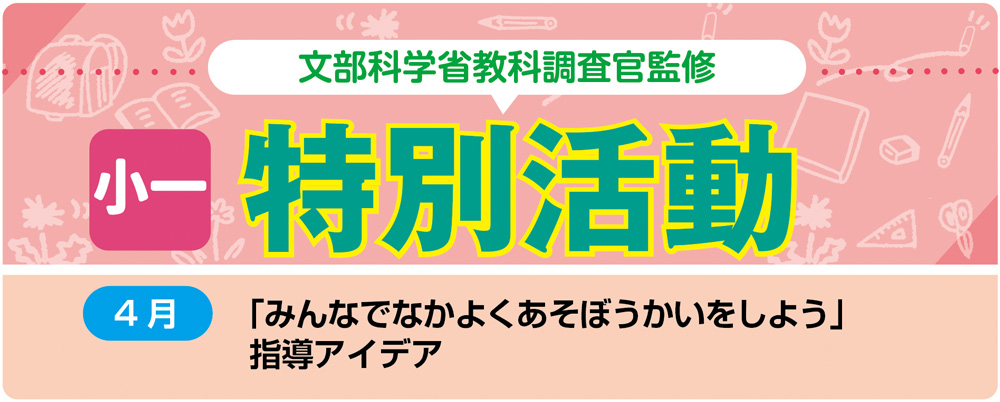
文部科学省教科調査官監修による、小1特別活動の指導アイデアです。4月は、学級活動(1) 「みんなでなかよくあそぼうかいをしよう」の実践を紹介します。
入学して1週間くらいすると、子供たちは学校生活に少しずつ慣れてきます。友達同士の関わりも入学前の園が同じだったり、座席の位置が近いことがあったりすることをきっかけに関わりが増えてきている様子が見られます。その一方で1人でいる子供や、関わり方がうまくいかずトラブルが生じやすい子供も見られます。そこで、子供たちが友達と滑らかに、穏やかに関わることができるようにすることを目指して、学級会を行っていきます。これが、“入門期の学級会”のスタートになります。
執筆/埼玉県公立小学校校長・野村佐智夫
監修/文部科学省教科調査官・和久井伸彦
埼玉県公立小学校校長・野村佐智夫
目次
年間執筆計画
04月 学級活動(1) なかよくあそぼうかいをしよう
05月 学級活動(2)ア がっこうのきまり
06月 学級活動(1) くらすのおしごとをきめよう
07月 学級活動(1) 1学期がんばったね会をしよう
09月 学級活動(1) すきなことはっぴょうかいをしよう
10月 学級活動(3)ウ 本となかよし
11月 学級活動(1) クラスのうたをつくろう
12月 学級活動(2)エ たべるのだいすき
01月 学級活動(1) クラスのすごろくをつくろう
02月 学級活動(3)ア もうすぐ2年生
03月 学級活動(1) 思い出集会をしよう
読者の皆様へ
夢いっぱいで期待に胸を膨らませて入学してきた1年生の学校生活がいよいよスタートします。「学校は勉強をするところ」というイメージや、「先生はやさしいかな?」「お友達がたくさんできるかな?」という不安ももっていることと思います。ただでさえ、3月までと場所が変わり、人が変わり、生活が変わっているので、みんなが不安を抱えています。そこで学級会の出番です! 「1年生だから、特に1年生の4月だから学級会はできない」ということは、まったくありません。幼児期の教育において、先生と一緒に様々な話合いや遊びを通した学びをしてきています。従って1年生の最初は先生と一緒に話合いをすることで、円滑な接続につながります。
学級会の継続的な実践を通して、自然に友達と協力できたり、温かな雰囲気に包まれたりと、学級経営の充実を図ることに寄与していきます。ぜひ、この1年間、こちらのページをご覧いただき、1年生の学級活動を一緒に勉強していきませんか?
2~6年生の担任のみなさんの中で「学級活動の指導は正直よく分からなくて……」という方にも、指導のイメージをもったり、参考にして実践してみたりするのにお役に立てるかもしれません。よろしかったら、ご自分の担任しているページと合わせてご覧になってみてください!
学級会ここがポイント! その1【入門期の学級会】
・1年生にも分かる言葉で「進める人」「指す人」「書く人」「貼る人」「ノートに書く人」という役割を示す。
・これらの役割を教師がモデルとしてすべてを行う。子供たちが進め方を理解できてきたら(めやす:2学期頃から)先生が取り組んでいた仕事の一部を任せる。その後、一緒に仕事をしてみるなど、段階を経て、子供たちに任せるところを増やしていく。
・はじめは教師が議題について提案を行い、活動を積み重ねていく中で子供たちから「今度はこんなことがしたいな!」という声が出てきたら、それらを取り入れていくようにする。
・1単位時間の前半に話合いを行い、後半はその話合いで決まった遊びなどを行う。楽しかったという実感を伴った経験を重ねることで、友達と関わることの楽しさや喜びを感じることができるようにする。
・教師がすべての役割を行うよさは、「だれもが不安なく参加できるようにする」「子供たちに学級会のイメージを湧かせやすくする」「役割ごとにすることのモデルを示すことで子供の興味や意欲を高める」などがあります。
・座席配置は、子供たちがよりまとまって話合いを進めることができるよう、机といすを教室の後方に移動させ、床に座って(さらに、丸くなって)行うことも効果的です。
「がっかつ」という時間割の言葉に「何をするのかなあ?」と口々に言っている子供たちと、記念すべき第1回学級会を行っていきます。
この時間では、オリエンテーションも行います。何より「みんなが仲よくなるようにみんなで話し合い、みんなで協力して活動する時間だよ」ということに実感をもてるように、実践後の感想などから価値付けることも大切です。

