いじめ【わかる!教育ニュース #62】
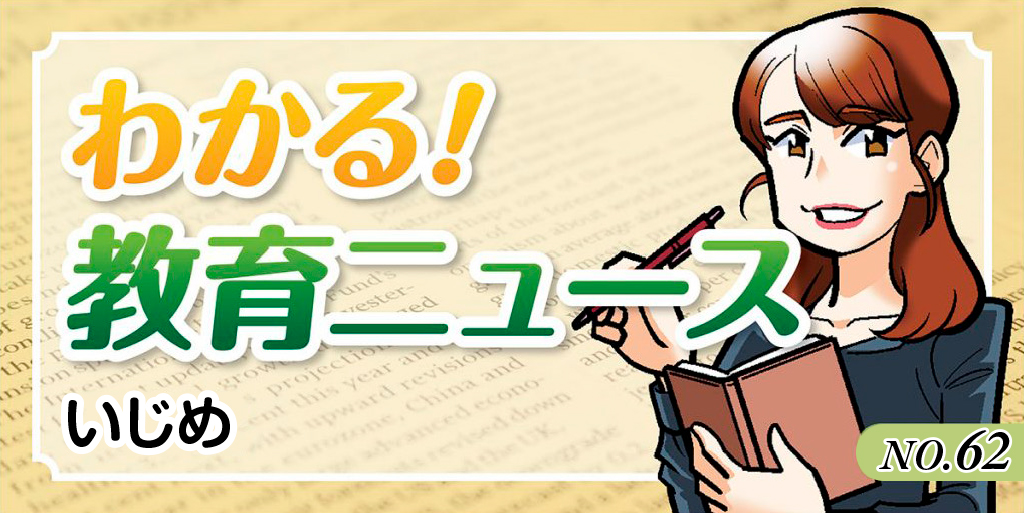
先生だったら知っておきたい、様々な教育ニュースについて解説します。連載第62回のテーマは「いじめ」です。
目次
追跡調査での「仲間外れ、集団無視」、子供回答は約70%、教員回答は10%台
文部科学省の調査のたびに件数が増える、いじめ。昔より多いとは限らず、いじめを見付けようとする学校側の努力の表れとも言えます。ただ、見逃しやすいいじめがあることは、理解しておいたほうがいいでしょう。
国立教育政策研究所(国研)が行った「いじめ追跡調査」の結果を、文科省の「問題行動調査」の結果と比較したところ、いじめ被害の多い内容が、子供と大人で食い違うことが分かりました(参照データ)。
追跡調査は、国研が同じエリアで時期を変えて行っています。今回は2019~22年、ある地方都市の16小中学校の小4~中3の4000人超に実施。各年6月と11月、4年間で計8回調べました。調べたいじめの形は「冷やかし、からかい、悪口」「金品をたかられる」など、問題行動調査と同じ8つの行為です。
両者の結果を分析すると、子供が回答する追跡調査で70%近くに上る「仲間外れ、集団無視」が、教員が答える問題行動調査では、10%台。同様に、「軽くぶつかられる、遊ぶふりで叩かれる、蹴られる」も子供回答が40%台に対し、教員回答は10~20%台と開きがあります。他にも、問題行動調査で10%に満たない「ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする」が、追跡調査では20~30%台に上りました。

