【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第69回】今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その10) ─不登校、苛め過去最多・「良薬口に苦し(中)」─

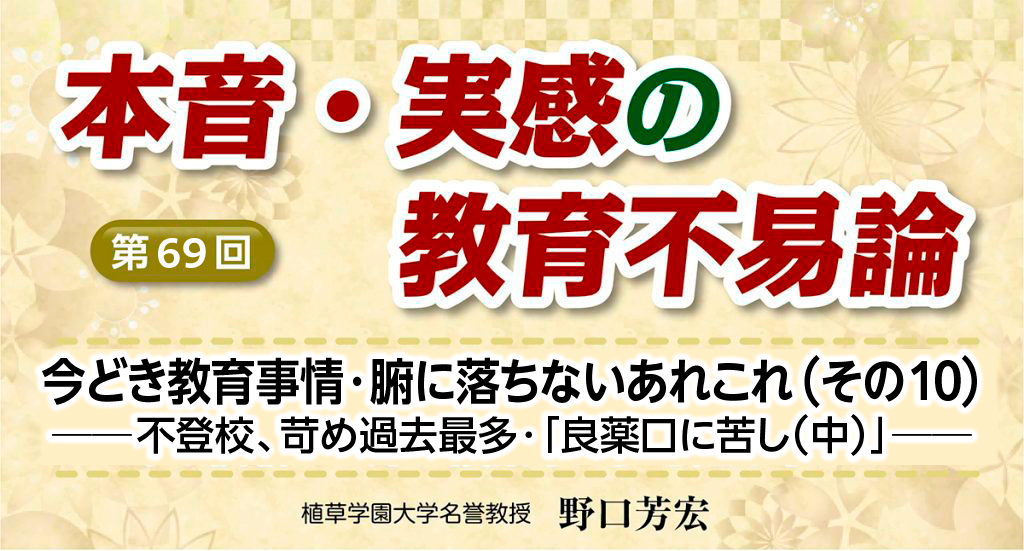
国語の授業名人として著名な野口芳宏先生が、65年以上にわたる実践の蓄積に基づき、不易の教育論を多様なテーマで綴る硬派な連載。今回は、中央教育審議会の答申への疑問から書き起こし、いじめ、不登校、小中高生の自殺者数が増え続けて止まらないことへの警鐘を鳴らします。次期学習指導要領の改訂に向け、大いに議論すべき問題提起です。
執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、65年以上にわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。

目次
4、中央教育審議会の答申への疑問
現行の学習指導要領は平成29年7月に告示されたもので、実施、実践に移されて7か年が経過している。言うまでもないが、これは平成28年12月の中央教育審議会の答申を踏まえて改訂されたものである。 以下の引用は、『小学校学習指導要領(平成29年度告示)解説 総則編』の3ページ②「育成を目指す資質・能力の明確化」に書かれた冒頭一文の書き出しである。
中央教育審議会答申においては、予測困難な社会の変化に主体的に関わり、感性を豊かに働かせながら、①どのような未来を創っていくのか、②どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかという③目的を自ら考え、④自らの可能性を発揮し、⑤よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力を身に付けられるようにすることが重要であること、
(ひとまず以下略。傍線は野口)
中教審の「主要所掌事務」の⑴は「文部科学大臣の諮問に応じて教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に関する重要事項を調査審議し、文部科学大臣に意見を述べること。」とある。上記の⑴は、当面は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の教育全体を対象とする事務内容であるから、そのままがそれぞれの校種に直結するわけではない。それぞれの校種にふさわしく砕いて示すのは文科省の初中局の仕事になるのだろうが、囲みに引用した「答申」の部分を読んで皆さんはどのように思い、受けとめられたであろうか。
学習指導要領は、ほぼ10年先の社会を見通し、それに耐えられる子供の教育のあり方を示すものである。その「10年先の社会」さえも、「予測困難」と答申では述べている。その「予測困難な社会の変化に主体的に関わり、感性を豊かに働かせながら」
① どのような未来を創っていくのか、
② どのように社会や人生をよりよいものにしていくのか、
③ という目的を自ら考え、
④ 自らの可能性を発揮し、
⑤ よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力を身に付けられるようにすること、(が重要である。)
ここに引いた、「という目的を自ら考え」るのは誰なのだろうか。子供だろうか、教師なのだろうか、保護者なのだろうか。
「自らの可能性を発揮」するのは、子供なのだろうか、教師なのだろうか、保護者なのだろうか。
「よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力を身に付けられる」のは子供か、教師か、保護者か。文末は「ようにすることが重要である。」と結ばれているところを見ると、教師か保護者に求めているようにもとれるし、両方に求めているともとれる。よくは分からないが、いずれにせよ「答申」に書かれていることは申し分なくその通りであり、立派である。間違いなど全くない。理想的であり、神のお告げに近いとさえ言えよう。
だが、しかし、「立派すぎ」て、「だから、できない」のだ。
前回の「良薬は口に苦し(上)」のタイトルだけでも思い起こして貰いたい。
1、不登校児童生徒34万6千、過去最多
2、いじめは73万3千件、過去最多
3、「過去最多」と「11年連続で増加」
これが、現実の学校と子供の実態なのだ。そしてこの現実は、現行の学習指導要領の実施中の姿であり、中教審の「答申」に基づく実践下の現実なのだ。
「だが、指導要領の根幹となる中央教育審議会の『答申』は、私の主張とはかなり隔たりのある『この世離れ』した内容のように思われるのだが、」──と私は前回稿で述べ、「それは次回で述べたい。」と結んだのだった。それを今述べようとしているところである。
5、子供と学校の身辺事情2、3
令和5年度、精神疾患で休職した公立学校の教員は7119人(前年比580人増)で、過去最多更新と、文科省は報じた。一ヶ月以上の病休取得者を加えると13,045人(前年比848人増)とのことだ。休職者の要因としては子供の指導上の問題がほぼ26%で最多、次が職場の人間関係でほぼ24%とは、某県教委の実状とのことである。
学校現場の教員不足は深刻である。真偽の程は分からないが、某県では新規採用者の6人が一週間から二週間で退職したとも聞いた。この中には院卒者もいたそうだ。
教員不足の頼みの綱は新規採用者だが、全国的に志願者が激減していることが話題になっている。また、学習塾大手の河合塾の調査によると、「国立大教育学部で定員減──新年度入学、志望者も前年度割る」と報じている。定員は他の学部に振り替える所が多いそうだ。私大の中には教育学部の募集を停止した所も出ているらしい。
書きたくないことだが、某紙は「(令和5年度の)小中高生の自殺者、昨年513人──過去最多水準で高止まり」と報じた。
厚労省の令和6年度版の「自殺対策白書」によると、小学生13人、中学生153人、高校生347人で、この傾向はほぼ前年と同じで年を重ねるにつれて多くなっている。但し、自殺者の総数は2万1837人で、これは前年より減少している。つまり、子供の自殺が増えていることになり、これも大いに気がかりである。
子供の自殺の要因としては、学校段階が上がるほどうつ病などの健康問題が増加し、中学生は学業不振や友人関係などの学校問題が38%強(女子)で最多とのことだ。小学生では保護者のしつけや叱責による家庭問題が最多となった由である。
これらの一つ一つをじっくり分析し、考え合ってみたいところだが、もう一つ気になった言葉を紹介して話を先に進めたい。気になったのは、某紙に載った次の言葉である。皆さんはこれらに対してどのような受けとめ方をされるだろうか。
① 家庭の経済格差が生み出す、子どもの教育格差。
② そのせいで、未来を諦めるしかない子どもがいる。
③ 周囲の子には当たり前である塾に通うことができない。
④ 親の代わりに家事や弟妹の世話をしなければならない。自分の勉強時間がない。
⑤本人の努力に関係なく家庭の収入格差がそのまま子供の教育格差に繋がっている。
手っ取り早いところで、①~⑤のような考え方、受けとめ方、見方に対して賛成なら◯を、おかしいぞ、この発言の仕方は、と思う人は✕をつけていって貰いたい。隣や近くの方との異同を確かめつつ、それぞれの妥当性を話し合ってみて貰いたい。
以上、今の学校や子供や教員の身辺事情の一端を記したが、いずれも多事多難、まさに「教育氷河期」の観を呈する思いである。
このような「身辺事情」に対して、中教審の文言はあまりにも高尚で非の打ち所のない御託宣のようには思えないだろうか。
その御託宣を「踏まえ」る文科省の「改訂」が同様に高踏的になるのは当然である。私はそれも「この世離れ」と感じてしまうのだ。
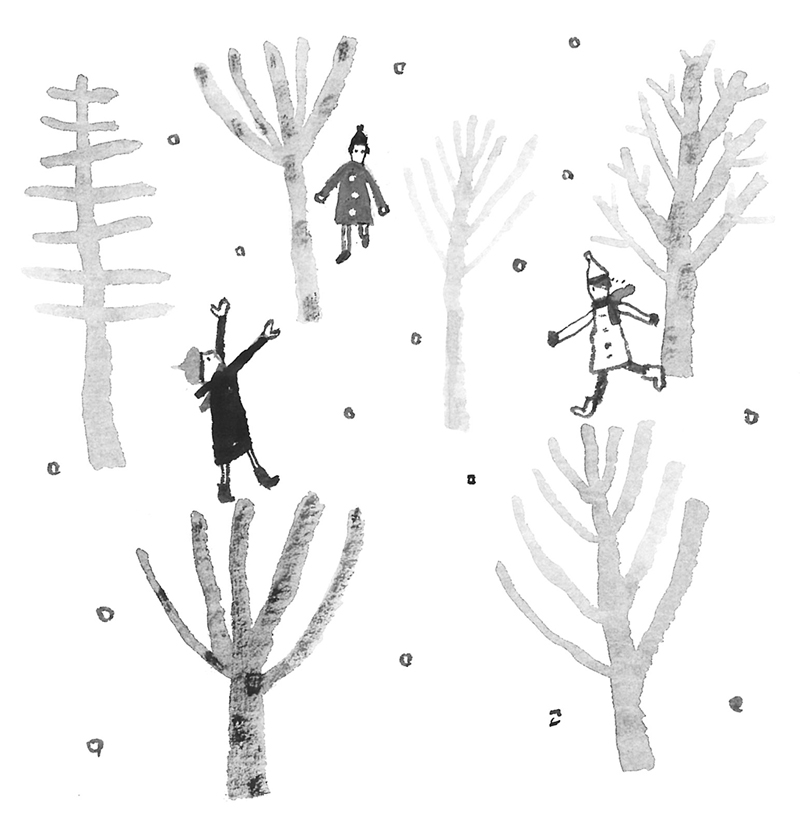
6、「教学聖旨」の背景は現代に酷似
唐突の感を拭えないが、「教学聖旨」に触れておきたい。明治天皇は五箇条の御誓文によって日本の近代化を神に誓われ、教育令等によってその実りを望まれた。その実状を知るべく自ら国内の諸地方を巡幸され、親しく小学校、中学校、師範学校を視察された。その結果、教育の実態が極めて憂慮すべきものであることを痛感された。維新後の文明開化が専ら欧米流に急変され混乱の様相さえ呈し、このまま進めば、政府の意図する文教政策から逸脱するかの感があった。
明治天皇は、政府の国民教育に関する根本精神を明らかにし、教学の本義がどこにあるのかを侍講の元田永孚(もとだながざね)に命じて起草させ、「教学聖旨」を完成させられた。
その要は次の通りである。(野口抄訳)
教学の要は仁義忠孝を明らかにし、智識才芸を究め、大道を正すことだ。だが、現在は智識や才芸ばかりを尚び、欧米の真似に酔い、文明開化の枝葉に走り、品行を破り、風俗を乱す者が少なくない。維新の始めの頃は、旧習を改め、世界に学ぶ気風が日々新たの進展を見せたが、やがてそれに染まるの余りか忠孝、仁義を忘れ、洋風にのみ憧れ、君臣父子の大義を軽んじている。
これは大変な誤りだ。以後は、日本人としての誇りを取り戻し、本末を弁え、本物の学びによって我国の独立を世界に示さなければならない。それによって日本の新たな夜明けを世界に示そう。
文科省のサイトで「教学聖旨」を検索すれば誰でも格調高い原文が読める。これを示した私の意図は次の五点にある。
⑴ 明治天皇が親しく地方の実情を視察され、実感に基づいて示された策であること。
⑵ 右の巡幸で天皇が感じられた実状は、日本の現状と酷似した事態と思われること。
⑶ 美辞麗句の虚飾や、理想論的な机上論ではなく、明治天皇の本音、実感の吐露であること。
⑷ これによって、時の文部政策が大きく変えられ、「報本反始」に目覚めたこと。
⑸「この世離れ」ならぬ「この世直し」の心の底からの悲願からの発露であること。
明治天皇は、大日本帝国憲法の規定によって、①大日本帝国は、万世一系の天皇が統治する。②(略)。③天皇は神聖であって侵してはならない。──という訳で、名実ともに最高の権威、権力を持ち、日本の国家と国民にとっての全責任を負う立場にあられた。それは、想像を絶する重責を負う立場であられたに違いない。時に明治天皇の御年は弱冠28歳(数え年)である。
さて、文科省は、こと教育という国家の営為については、最高、最大の権限と責任を持つ立場にある。不登校者も、苛めの件数も「11年間連続して増加」を続け、「過去最多」という事態、事実の最大の責任者は文科省の他にはない、と考えるのはごく当然のことだと私は思うのだが如何か。
たとえはよくないが、これがもし、戦争であれば、連戦連敗で年々戦死者が増えている、ということになる。そうなれば最高司令官の「更迭」もまた当然ということになる。──あくまでも「よくない」「架空の」「たとえ」ではある。笑えない、笑い話だ。
中央教育審議会の「答申」は、少なくとも十年先の国家、国民の教育をリードする重責を担う。「予測困難な社会の変化に主体的に関わり云々」の実現、実行、実践は現実的に可能なのか。「どのように社会や人生をよりよいものにしていくのか」などということの実行、実現、実践は、誰に期待するというのか。
いずれも、「神の御託宣」のように難しい。初等、中等普通教育は本来「基礎教育」である。「予測困難な社会の変化」への抽象論よりも、目の前の不登校や苛め等の打開、解決という根本策をこそ答申すべきではないか。

イラスト/すがわらけいこ 写真/櫻井智雄

