特別支援学級のコミュニケーションの実践は、授業+学級づくりで取り組もう
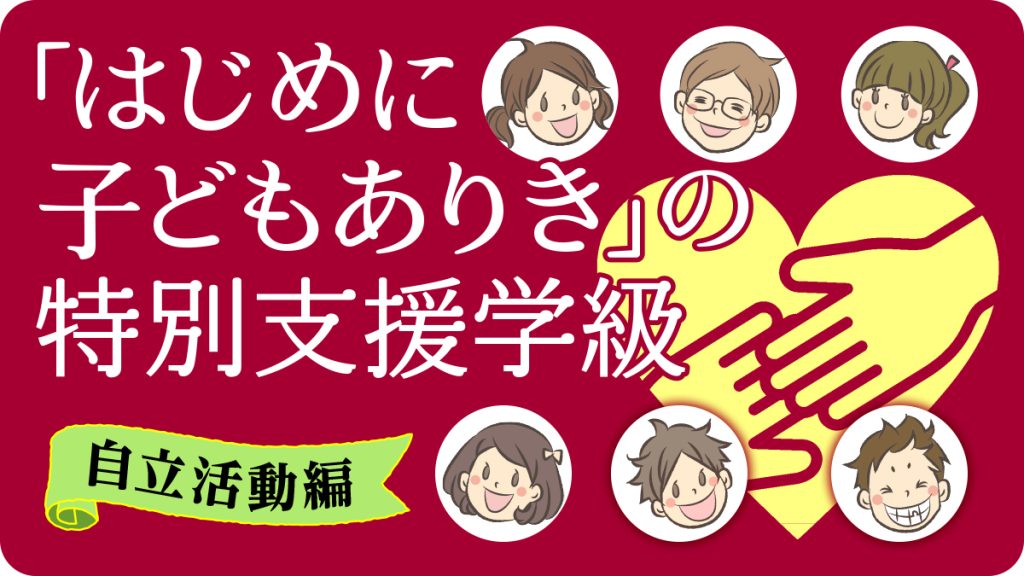
今回は、自立活動6区分の中で、「コミュニケーション」の授業実践について紹介します。
コミュニケーションを授業で取り扱うに当たり、意識して頂きたいことがあります。それは、学級づくりの視点も大切であるということです。「心理的安全性」という言葉を最近よく耳にしますが、「授業+学級づくり」で自立活動(コミュニケーション)は成立するものと捉えています。世間話で盛り上がることができる、弱音を吐いたら誰かが拾ってくれる、ここぞという場面で応援してくれる。 このようなクラスの雰囲気も、合わせて大切に作っていきたいものです。
【連載】「はじめに子どもありき」の特別支援学級 〜自立活動編〜 #08
執筆/埼玉県公立小学校教諭・奥山 俊志哉
「コミュニケーション」の項目には、大きく分けて5つの項目が設定されています。
⑴ コミュニケーションの基礎的能力に関すること
⑵ 言語の受容と表出に関すること
⑶ 言語の形成と活用に関すること
⑷ コミュニケーション手段の選択と活用に関すること
⑸ 状況に応じたコミュニケーションに関すること
この5つの項目を、年間通して身につけていく必要があります。
クラスの子どもたちは、好きなことや得意なこと、休日にしたことなど、自分のことを話すことが大好きです。また、ゲーム、昆虫、電車など、自分の興味がある内容については、たくさん知っています。目をキラキラさせて教えてくれますし、タブレットで写真や動画を見せて話をしてくれることもたくさんあります。しかし、コミュニケーション(=相手とのやりとり)は苦手です。
●話したいという気持ちが先行してしまい、友達が話している途中に割り込みをしてしまう。
●興味関心のあることを延々と話し続けてしまう。
●表情や感情を読み取れず、相手に失礼なことを言ってしまう。
●言っていいことと悪いことの分別がつきづらい(=相手の気持ちに立って考えることが苦手)
などの場面が見られ、トラブルに発展することもあります。このような子どもたちに注意や指導・支援をするだけではなく、自立活動の時間を通して、コミュニケーションをすることの楽しさを実感させたいと考えるようになりました。
また、コミュニケーションの楽しさを子どもたちが実感することができれば、一方的に発言をしてしまうような行動が、少しずつ減っていくのではないかとも考えました。
以下に授業で取り組んだ内容を紹介します。
今回は「すごろく」を授業で取り組んでみました。以前に昔遊び(生活単元学習)ですごろくに取り組んだことがあり、自立活動(コミュニケーション)でもすごろくを行うと、コミュニケーションを楽しむ経験ができ、コミュニケーションを楽しんで行おうとする態度が子どもたちに育成できるのではないかと考えました。
今回は3学期の初日に行いました。
コミュニケーションの力を身につけさせたいので、今回はこのように特別なルールを設けました。
① 友達や先生・支援員さんにお題を言う(=質問をする)
② 友達や先生・支援員さんが質問に答え、話を広げる。
③ 友達や先生・支援員さんが同じ質問をする。
④ 自分自身が質問に答え、話を広げる。
このようにアレンジを加えて、すごろくをクラスのみんなでやってみました。時期にマッチした話題で楽しくコミュニケーションができるよう、すごろくのマスには、以下のようなお題(イベント)を配置ました。

