「きょうだい児」とは?【知っておきたい教育用語】
近年、ヤングケアラーの問題が取り上げられるなか、いままで世間的に認知度の低かった「きょうだい児」の問題も表面化されるようになってきました。今回は、きょうだい児が抱える問題や取り巻く現状などについて解説します。
執筆/「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム
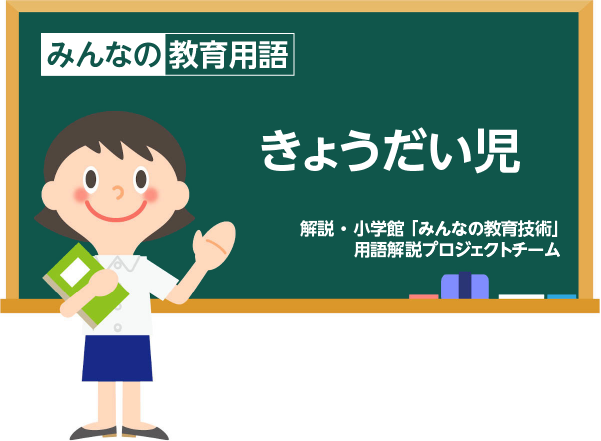
目次
きょうだい児とは
【きょうだい児】
障がい児や障がい者の兄弟姉妹のことで、ヤングケアラーのように幼少期から家庭内でケア的役割を担う場合がある。その結果、成長過程において必要以上の責任を負いがちになり、孤独や不安を感じるなど、心身に影響を受ける場合もある。なお、「きょうだい」と平仮名で表記するのは、兄・弟・姉・妹のいずれにも対応しているためである。
日本国内にきょうだい児がどのくらいいるのかは正確には把握されていません。しかし、国立成育医療研究センターによる「「こどものイマを考える 医療的ケア児」によれば、在宅の医療的ケア児の推計値(0歳~19歳)は、2019年時点で2万人を超え、年々増加傾向にあります。
小中学校における、きょうだい児の支援に関する研究では、同じ学校(特別支援学級)に通う障がいをもつきょうだいに対して、ケアをする側面が強いために自分自身を抑えているきょうだいや、行動への対応に苦慮しているきょうだい、両親から説明を受けていても校内で行動をともにすることを嫌がるきょうだい、理解はあるものの周囲の目を気にして家族であることを隠すきょうだいなどの姿があるとされています。
きょうだい児が抱える問題
親が1次的ケアラーとしての役割を果たす一方で、きょうだい児は2次的ケアラーとしての役割を与えられることが多く、その実態が見えにくいという問題があります。また、親も障がいがある子どもの養育に追われ、きょうだい児へのケアまで手が回らない、どうしても障がいのあるきょうだいを優先してしまうという場面も生じます。そうした過程で、きょうだい児は孤独感や疎外感を感じ、「親から愛されていないのではないか」といった感情を抱くこともあります。
さらに、幼少期から家事や、きょうだいのケアといった役割を果たすことで心身に影響が出てしまうことのほか、自分の感情をうまく出せない、悲しいことや辛いことがあっても我慢してしまうといった傾向が強くなります。
進路や結婚などのライフイベントにおいては、「きょうだい児であることを家族以外に打ち明けることができず、諦めてしまう」ことや、「きょうだいのケアがあるから自分の意思を優先できない」といった壁にぶつかるケースもあります。

