学校を変えられる教師のマインドセット|北海道教育大学・川俣智路先生講演@北の教育文化フェスティバル
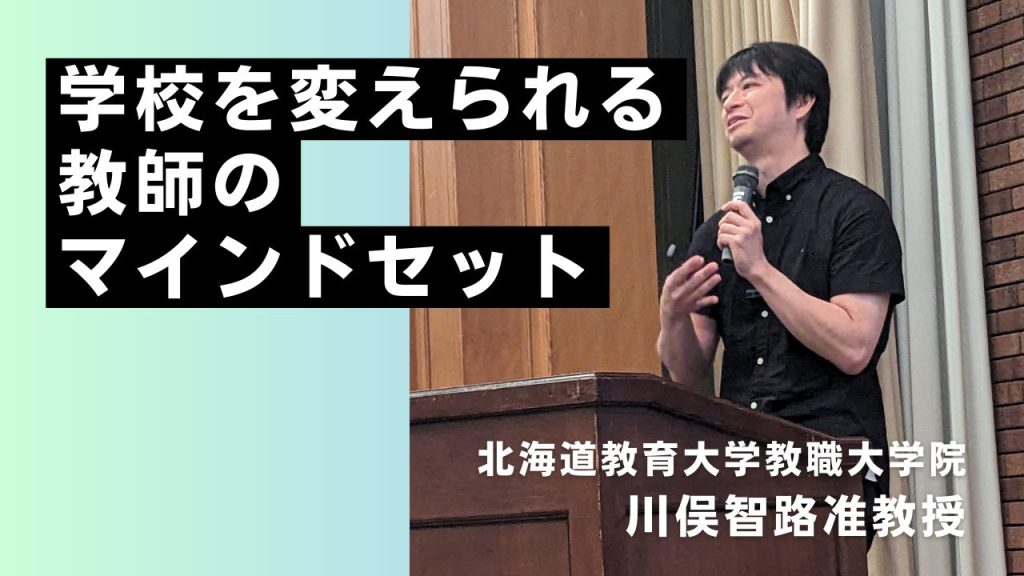
2024年8月10日に札幌市で開催された「北の教育文化フェスティバル」での、川俣智路先生によるUDLについての講演の内容を2回に分けてお届けします。今回はその後半。UDLの考え方に基づく教師像、子供の見取り、マインドセットの変更などについてお話いただきました。
取材・構成/村岡明
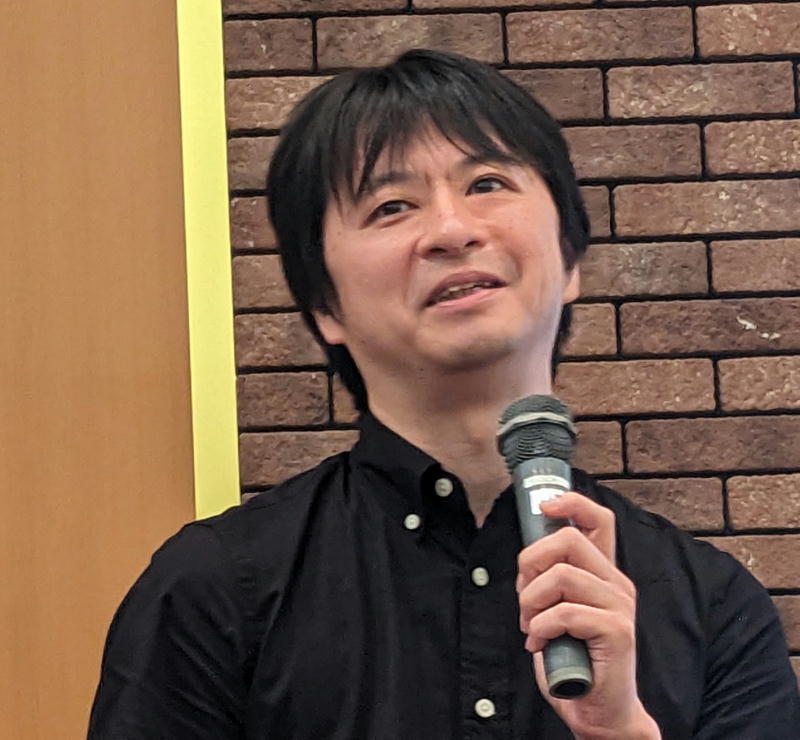
川俣智路(かわまた ともみち)
北海道教育大学教職大学院准教授。北海道大学教育学部卒。2017年より現職。
現在の専門分野は、教育心理学, 臨床心理学, 特別支援教育。
「学びのユニバーサルデザイン(UDL)の枠組みによる、 主体的な学習者の育成」を主な研究テーマとしており、臨床心理学の立場から学校現場で子どもや保護者と関わっている。
前半のお話はこちら:
UDLの授業でできることは何か|北海道教育大学・川俣智路先生講演@北の教育文化フェスティバル
目次
自分の学習を舵取りする
前半のお話でも述べた通り、UDLの核心は、学習者のエージェンシー(自らの学習を舵取りすることができる力)を育てることにあります。ここでいう学習は、単に教科の課題ができるという狭義の意味ではありません。
例えば、「合唱コンクールで様々な経験を得る」とか、「部活動で大会に向けて一生懸命練習したが思うような成果が出なかったとしても、その先練習を継続することに意義を見出す」とか、「定期テストで良い点数が取れず、⾃分はもっと練習問題をしないとならないなと気がついた」といったことは、狭い意味での学習の成果は出ていないかもしれませんが、⾃分の成⻑・発達について考える機会になっていると考えられます。
UDLで言う学習には、学習者としての成⻑・発達の意味合いがあります。ですからUDLが授業において⽬指すところは、自己決定できる学習者(自分で自分の発達の舵取りをすることができる学習者)を育てることとなります。例えて言うなら、学校はその自分の発達や学習を舵取りできる、教習所のような存在なのです。
学習者の自己決定を阻む3つのバリア
学習者の自己決定を阻む要因として、以下の3つが挙げられます。
教師の思い込み
- 「子どもにはできない」という固定的な考え方
- 子どもの可能性を過小評価する傾向
- この思い込みが子どもの成長機会を制限している
方法論の欠如
- 自らの学びを舵取る方法を教えていない
- 「できるようになって」と言うだけでは不十分
- 外的な働きかけを要するところから自らできるようになるまで段階的な援助が必要
過度な介入
- 常に誰かが指示を出し続けている状況
- 子どもの自主性を育む機会を奪っている
- 適切な距離感を保った支援の必要性

