UDLの授業でできることは何か|北海道教育大学・川俣智路先生講演@北の教育文化フェスティバル
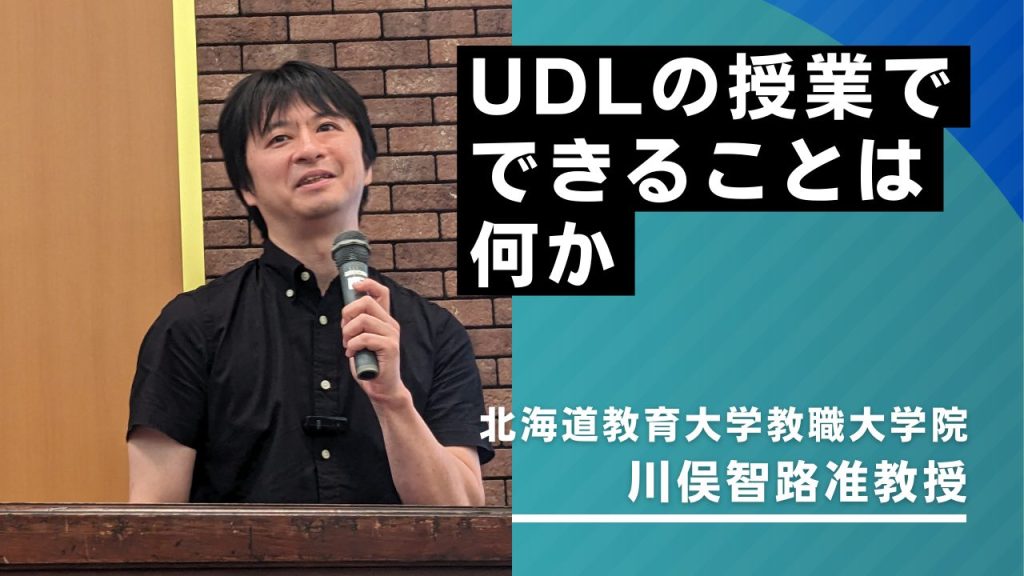
2024年8月10日に札幌市で開催された「北の教育文化フェスティバル」での、川俣智路先生によるUDLについての講演の内容を2回に分けてお届けします。今回はその前半。UDL(Universal Design for Learning)の概要と考え方、重要性などについてお話いただきました。
取材・構成/村岡明
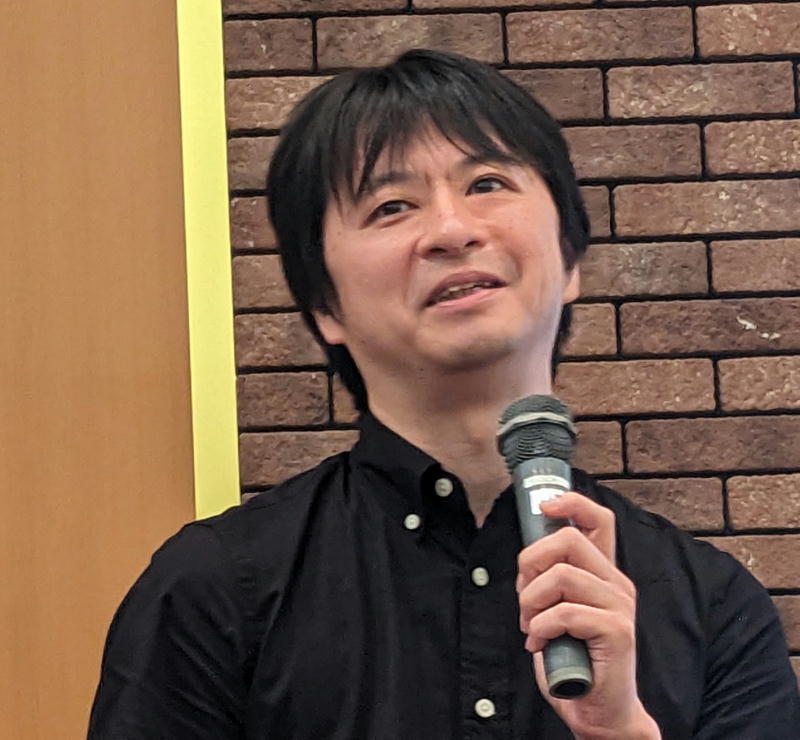
川俣智路(かわまた・ともみち)
北海道教育大学教職大学院准教授。北海道大学教育学部卒。2017年より現職。
現在の専門分野は、教育心理学, 臨床心理学, 特別支援教育。
「学びのユニバーサルデザイン(UDL)の枠組みによる、 主体的な学習者の育成」を主な研究テーマとしており、臨床心理学の立場から学校現場で子どもや保護者と関わっている。
目次
学びのユニバーサルデザイン(UDL)とは
UDL(Universal Design for Learning)は、アメリカの教育機関であるCAST(Center for Applied Special Technology)が提唱している学習環境デザインです。神経心理学的な観点から学習を以下の3つの要素で捉えています。
- 何を学習するか
- どのように学習するか(学習方略や方法)
- なぜ学習するか(感情的な部分)
これら3つがきちんと機能していることが、学習が成立するための前提となります。これらの要素のどこかに、あるいは複数の箇所につまずきがある場合、従来は学習者に適応を求めがちでした。UDLでは、学習環境の側を調整することで解決を図るアプローチを取ります。
例えば、視覚に障害のある参加者がいる授業を考えてみましょう。スクリーンに単語を示すだけの授業では、視覚に障害があると学べません。この場合、見ることでしか学べない方法に限定した学習環境デザインに問題があるとUDLでは考えます。学習環境デザインを工夫すれば、全員が参加できる授業が実現できるのです。
自律的な学習者の育成
UDLが目指すのは、単に全員が参加できる環境を作ることだけではありません。UDLのゴールは、学習者エージェンシー(学習者による学びの舵取り)であり、学習者が、目的と内省力をもち、効果的にリソースを活用し、戦略的に行動できることである。(原文:The goal of UDL is learner agency that is purposeful & reflective, resourceful & authentic, strategic & action-oriented.)つまり、自分で自分の学びの舵を取れる自律的な学習者の育成が最終目標です。
ですから教師は、「今やっていることが学習者を発達させることにつながっているかどうか」を常に考えることが重要です。この「学習者として発達する」という視点が、日本の学校や社会構造を変えていく上での重要なカギになります。

