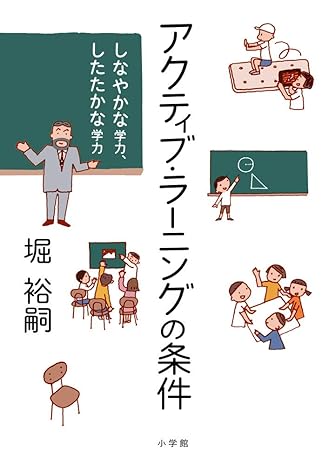【新連載】堀 裕嗣 なら、ここまでやる! 国語科の教材研究と授業デザイン ♯1「文学的文章の詳細な読解」は、無意味だったのか?~文脈を読む力について~

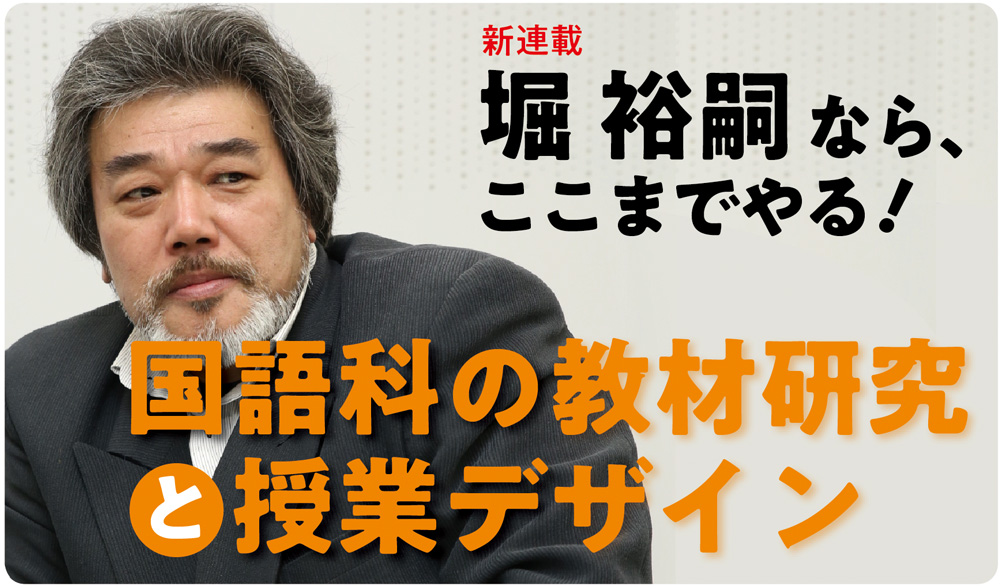
国語科・道徳科において、確固たる理論的裏付けに基づくクリエイティブな教材開発、教材研究、授業実践に定評のある堀 裕嗣先生。50代後半にして時代の最先端を創造的に疾走し続ける実践者(中学校)の1人です。そんな堀先生の待望の新連載(毎月1回公開予定)が、今月から満を持してスタートします。記念すべき第1回では、「文学的文章の詳細な読解が何を培っていたか」について、日本社会全体を視野に入れた考察が展開されます。
目次
1. 羊の顔していても心の中は狼?
1976年だから、私が小学校4年生のときのことだ。真夏のさなか、ピンク・レディーが颯爽とデビューした。同級生の女の子たちは瞬く間にピンク・レディーに夢中になり、教室といい廊下といい、休み時間の学校は「ペッパー警部」を歌って踊る女子たちであふれた。それから50年が過ぎようとしているが、その後あれほどの現象を見たことがないし、おそらく今後も現れないだろう。
ピンク・レディーのセカンドシングルは「S・O・S」である。「ペッパー警部」同様の大ヒット。ピンク・レディーが少なくとも数年は時代を席巻するであろうことを決定づけた曲である。
この曲にこんな歌詞がある。
男は狼なのよ 気をつけなさい
年頃になったなら つつしみなさい
羊の顔していても 心の中は
狼が牙をむく そういうものよ
歌詞を読むと、どうということもない歌詞に見える。よくあるフレーズの連続とさえ思える。しかし、当時の私、10歳の私には、どうしても「羊」が聞き取れなかった。別にミーちゃんやケイちゃんの滑舌が悪かったわけではない。当時の映像をYouTubeで観ても二人ははっきりと「ひつじ」と発音している。私がこれを聞き取れなかったのは「羊の顔をしても心の中は狼」という慣用表現を知らなかったからだ。要するに当時の私に知識がなかったのであり、当時の私の語彙の問題だったわけである。
しかし、話をこれで片付けるわけにはいかない。「●●●の顔していても」の後には、「心の中は 狼が牙をむく」と続いている。要するに後段は「狼」の話に展開するわけだ。とすれば、「●●●」が動物の名前であることくらいは予想されるはずなのだ。要するに、文脈からここにも動物の名前が入るのではないかと予測さえできれば、多少時間がかかるにしても音韻から「羊」は当時の私にも思い浮かんだはずなのである。ミーちゃんとケイちゃんがこの「●●●」を、「イ段・ウ段・イ段」の語として発音していたことは私にも聞き取れていたのだから。
結局この問題は、仲の好かったクラスメイトの秀樹くんに尋ねることによってすぐに解決した。しかしそのとき、「えっ、堀、羊の皮をかぶった狼って知らないの?」と驚きの表情で問い返されたことをもよく覚えている。彼は決して私を馬鹿にしたのではない。ただこんな当然のことを知らない私に、彼は単純に驚いたのである。このとき感じた、羞恥にまみれた小さな瑕(きず)を、私はそれから半世紀近く経ったいまでもはっきりと想い出すことができる。教室の窓側、一番後ろの席、窓からは札幌の冬には珍しいあたたかな日差しが差し込んでいた。
2. 男がいて女がいてゴリラがいるの?
かつて、倉田まり子という美しく清楚な女性アイドルがいた。歌も上手く、将来を嘱望されたが、スキャンダルでテレビから消えていくことになる。そんなアイドルだ。
その倉田まり子に「HOW!ワンダフル」というヒット曲がある。グリコポッキーのCMソングで、そこでは倉田まり子が満面の笑みでポッキーを片手に踊っていたのをよく覚えている。サビはこんな歌詞である。
男がいて女がいて 恋ができるの
あなたがいて私がいて キスができるの
ある日のことである。私の五つ下の妹がこの歌を口ずさんでいた。
男がいて女がいて ゴリラがいるの
これを聞いた母の「?」という表情をいまでも思い浮かべることができる。横には父もいたから、おそらく日曜日の朝方のことだった思う。母は「そんな歌があるわけがない」と、私に「兄ちゃん、この歌知ってる?」と訊く。私が知ってると応えると、「ほんとはどんな歌詞?」と尋ねる。私が「男がいて女がいて 恋ができるの」だと説明すると、両親ははじけるように嗤った。「なんでゴリラがいるんだ」「ゴリラなんているわけない」と。妹は泣きそうな顔をしている。
調べてみると、倉田まり子の「HOW!ワンダフル」は1979年のヒット曲である。となると、このエピソードは私が中学1年生、五つ下の妹は小学校2年生のときのことということになる。「恋」という概念を持たぬ小学校2年生の妹には、「恋ができるの」は前後の文脈から「ゴリラがいるの」に聞こえてしまったのだろう。「恋」は知らなくても「ゴリラ」は知っている。小学校低学年らしい微笑ましいエピソードである。大爆笑するいまは亡き両親を尻目に、私は妹のこの勘違いに笑えなかったことをよく覚えている。それは3年前、自分がピンク・レディーの歌詞を理解できなかったのと同じ構造だったからだ。
ただあのときと違うのは、その頃の私はもう、文脈概念を獲得していたことである。妹は「男がいて女がいて ゴリラがいるの」とは歌っていたが、その後の「あなたがいて私がいて キスができるの」は正しく歌っていたのである。なぜ「あなた」と「私」の「キス」の直前に「ゴリラ」が出得るのか。この疑問についてあれこれ考える程度には、私も成長していたわけである。どう考えてもこの文脈に「ゴリラ」は邪魔だ。幼いということは、文脈を読み取れないということである。当時、そう結論づける自分がいた。ちょうど私が10歳の冬に「羊の顔した狼」を文脈から読み取れなかったように。
かつて向田邦子は、「荒城の月」の「春高楼の花の宴 めぐる盃かげさして」を「春香炉の花の宴 眠る盃かげさして」と覚えていたと言う。そして晩年に至るまで、自分自身としてはその方がしっくり来ると感じていたらしい。それは客を連れて帰った父親が泥酔の後に盃の横で眠り込む姿と呼応しているとのこと。また、来客のために娘時代の向田邦子がよく香炉の香をたかされたことにもよると言う(『眠る盃』東京新聞・1978年10月9日)。情念の女流作家にして言葉とはこうしたものであることに、私は深い感慨を抱く。
3. 受信者の意図こそが大事?
堀 裕嗣 先生のご著書、好評発売中です!
↓「スクールカーストの正体ーキレイゴト抜きのいじめ対応―」
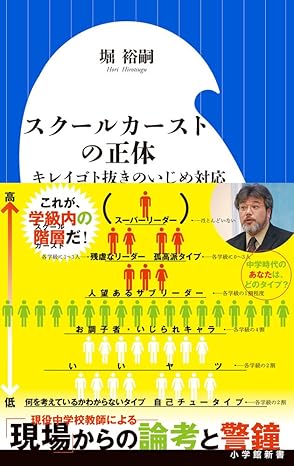
↓「アクティブ・ラーニングの条件ーしなやかな学力、したたかな学力-」