<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #4 高知大学教育学部附属小学校2年B組①<後編>

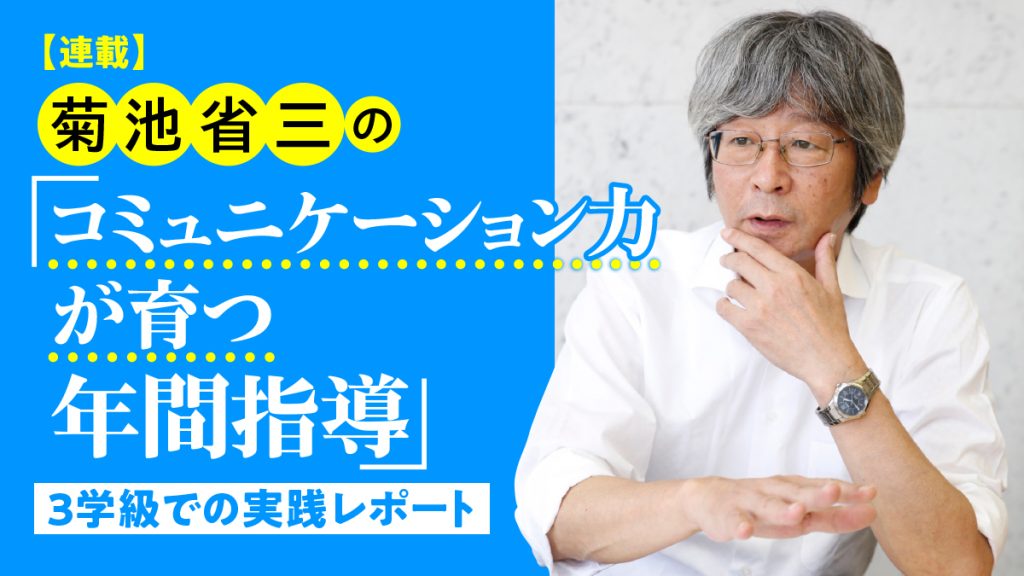
菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする連載です。3学級の担任は、徳島の堀井悠平先生、高知の小笠原由衣先生、千葉の植本京介先生。それぞれの学級をローテーションでレポートします。 今回は、高知の小笠原学級における、6月上旬の授業レポートの後編。菊池先生の「叱り方」について学べる必読回です。

目次
「考えがどう変わったか」を考える振り返りで、対話を深める
<アンパンマンとばいきんまんは、ともだちか?>
予想外の問いに、子供たちから、
「えーっ!?」
と驚きの声があがった。
「友達であるという人は○、友達ではないと思う人は×を書きましょう」
菊池先生の問いに、子供たちはノートに素早く書く。○派の数が多い結果となった。
次に、同じ意見の子同士で集まって意見交換し、そのままの位置で発表タイム。
×派
●悪と正義だから
●倒し合っているから
●いつもケンカしている
●アンパンマンの大切な仲間をいじめているから、アンパンマンがたたいて捕まえる
●いつもいっぱいたたいている
○派
●アンパンマンを倒してから帰るはずなのに、 ばいきんまんは倒さずに負けて帰っているから
●友達じゃなければけんかをしない
●いつもばいきんまんとドキンちゃんが変装してアンパンマンのところにご飯を食べに行っている
●エピソードの中では、時々仲間になっている
●仲良しだから、わざとケンカする
●赤ちゃんの頃、仲良しだったから
●ばいきんまんが恥ずかしそうに「勘弁してやるからな」と言ってるから
●戦わずに帰っているから
発表後、いったん自分の席に戻ると、菊池先生が、
「『○だったけど×に行きたい』という人がいます。どうしてか聞いてみましょう」
と、ある女子に発表を促した。
「いつもケンカしているから、何か友達じゃないような気がした…」
とその女子は小さな声で発表した。
![]()
子供の考えが変わるのは、子供同士が聞き合っている・考え合っている証拠です。
●AからBに変わった
●AからA′、BからB′に変わった
●分からなくなった
対話を通して、子供たちは次の3つの方向で自分の意見を掘り下げていきます。
①内容について考え方が深まり、変化する。(ときには、考えすぎて分からなくなることもある)
②友達のC君やDチームの発言を聞いたことで、考えを深める
③友達の発言や内容を受けて、自分の中で考えていることが変わっていく
内容の深化、相手の発言の影響、そして自分自身との対話。その3方向で、「変わった」「深まった」「分からなくなった」などと、自分の答えを見つけていくのです。
活動型の授業は、①活動の価値・目的ややり方の説明、②それを踏まえて活動、③振り返り の3つをセットに進めていきます。
活動の時間が延びてしまい、振り返りの時間を十分に取れないことも多々ありますが、
「考えがどう変わったか」を考える振り返りは、その後の対話を深める上で重要です。
そういう振り返りの視点を子供たちが持てるように、教師は年間を通し意識して指導していくことが大切です。
経験や知識をもとに、子供たちは自分の意見をつくり出す
「アンパンマンを作った人の名前を知っている人?」
と菊池先生が尋ねると、何人かが元気に手を挙げた。
「じつはやなせたかしさんが、アンパンマンとばいきんまんについて話しているそうです」
と菊池先生が話すと、一人の男子が手を挙げ、
「先生、理由を言ってもいいですか?」
と尋ねた。前に出てきたその男子は、やなせたかしの写真を指差しながら、
「この写真は、アンパンマンとばいきんまんがケンカしているから、友達じゃないと思う」
と、自分の意見を強引に主張しようとした。
「じゃあこれは?」
と菊池先生が新しい絵を出した。アンパンマンとばいきんまんがニコニコしながら寝転がっている絵だ。さらにジャムおじさんの絵を見せながら、
「ジャムおじさんは、『2人は友達だ』と言います。どうして『2人は友達』と言っているのでしょうか? 予想でいいから、分かる人?」
と問いかけた。手を挙げた数人が席を立った。
一人の男子が、
「最初に言っていい?」
と尋ねると、菊池先生が、
「どうぞ」とうなずいた。
●ケンカするほど仲がいいというから
それを聞いた後、菊池先生は、
「はい、どうぞ」
と声をかけ、それまでに立ち上がっていた子供たちが順に答えていった。
●ばいきんまんもパンだから
●みんなが知らんところで、もしかしたら一緒に遊んでいるかもしれない
●仲がいい絵があるから、前は友達だったけど、今はちょっとだけ仲が悪くなってケンカしている
●私もお姉ちゃんとケンカするから、もし2人がきょうだいならケンカするんじゃないか
![]()
「パンも菌でつくる」という知識、「いつもばいきんまんはアンパンマンを倒していない」という作品に対する理解力、「悪と正義。お互いがいるからこそ、お互いが引き立つ」という洞察力。
子供たちは、自分の経験や知識をもとに、多様な意見を出しました。子供たちの答えには、いくつかの層がありますが、B組のレベルは高いと言えるでしょう。
だからこそ今後、もっとお互いが聞き合うことができれば、話し合いが充実していくはずです。
たくさん発言させるのは、聞き合うため。聞き合うのは、活発に考え合いをさせたいからです。 多くの教室では、子供たちに発言させるだけで満足していますが、目的はその先にある「聞き合う・考え合う」ことです。教師は、そこに重点を置くことが大切です。

