ダイバーシティ! 本当に腹落ちして経営してる?【連載|管理職を楽しもう #9】
- 連載
- 管理職を楽しもう

前例踏襲や同調圧力が大嫌いな個性派パイセン、元小樽市立朝里中学校校長の森万喜子先生に管理職の楽しみ方を教えていただくこの連載。いま管理職の先生も、今後目指すかもしれない先生も、自分だったらどんなふうに「理想の学校」をつくるのか、想像しながら読んでみてくださいね。
第9回は、<ダイバーシティ! 本当に腹落ちして経営してる?>です。
執筆/元小樽市立朝里中学校校長・森 万喜子
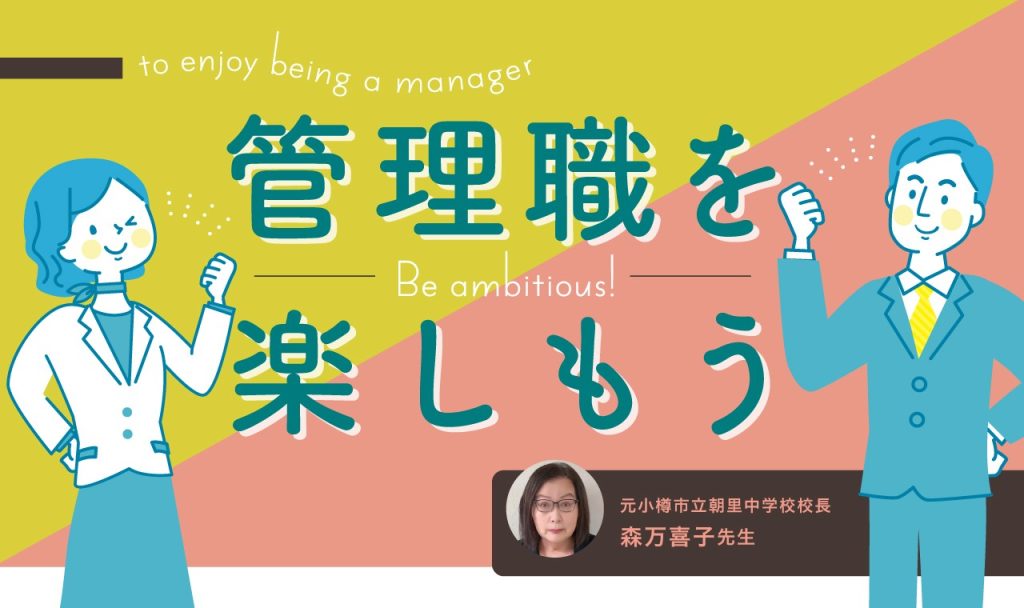
目次
2024年が半分終わりました
みなさんこんにちは。
なんと、2024年も半分が終わってしまいました。時間が過ぎるのが早すぎて、ヨタヨタとついていくのが大変、と実感していますが、季節は確実に夏!
忙しい学校現場のみなさん、ボーナスはもらった? 夏休みまであと数週間! 元気を出して進もう。
この節目に、半年を振り返り、次なる半年のわくわくの布石を打ちましょう。
そして、今回から私のコラムもタイトルが変わりました。お気づきでしょうか。そうです、「女性」の文字が外れたのです。
多様性の時代、分けることは差別につながる。今、朝の連続テレビ小説でもこのあたりがテーマになっていて、私も楽しみに観ています。
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」
ドラマの中で法律事務所の壁に力強く書かれたこの日本国憲法第14条を何度も目にして、公教育のあり方と自分のあり方を再確認する夏です。
多様性という「強み」
ダイバーシティ、多様性という言葉を聞くようになってからずいぶん時間がたちます。さて、あなたの学校、職場では多様性が尊重されていますか?
私は長らく公立中学校で勤務し、自分自身も地域の小学校、中学校、市内の高校、実家から通える大学というローカルな公立学校で学びました。特に地域の小中学校で過ごした時間は、自分にとって多様性と出合う場でした。今は国際化も進み、多様性の幅はもっともっと広がっています。
一方、学校、職場としての学校はどうだろう? まだまだ同質性が高いように感じるのです。
『多様性の科学 画一的で凋落する組織、複数の視点で問題を解決する組織』(マシュー・サイド著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2021年)という本には示唆に富むアイデアや事例がたくさん書かれていて、おすすめの一冊です。そこでは、同質性の高さが危機管理の甘さにつながり、重大な問題を未然に防げない、そんな具体例を挙げて多様性の強みを示しています。
多民族国家アメリカのことを「人種のサラダボウル」と比喩的に表すことがあります。つまり、人種や民族など多様な集団それぞれの伝統や文化の優れた部分を生かし、認め合うことで素晴らしい国を創ろうじゃないかという心意気のこと。実際はそう簡単にはいかない、大変なことも多い。でも、いろいろな人がいるのは強みなのです。日本の学校はまだサラダボウルまでには至らず、どちらかといえば折詰めの寿司というイメージです。多様性よりは指示に従順で行儀のよい子を育てるのが優れた教員という価値観がまだ強いんじゃないかな……全員がそろっている入場行進、話し方のマニュアル、生活における所作や作法、もちろん基本は大事。教えてもらわないと分からないし、繰り返すことで定着するのも事実、だけど守破離の守だけで満足だったら令和の学びの場ではないと考えています。多様性を大切にするためには、覚悟と本質の理解が必要なのですね。

