「夏休みだからできること~様々な教育のかたちに触れよう~」インクルーシブ教育を実現するために、今私たちができること #5

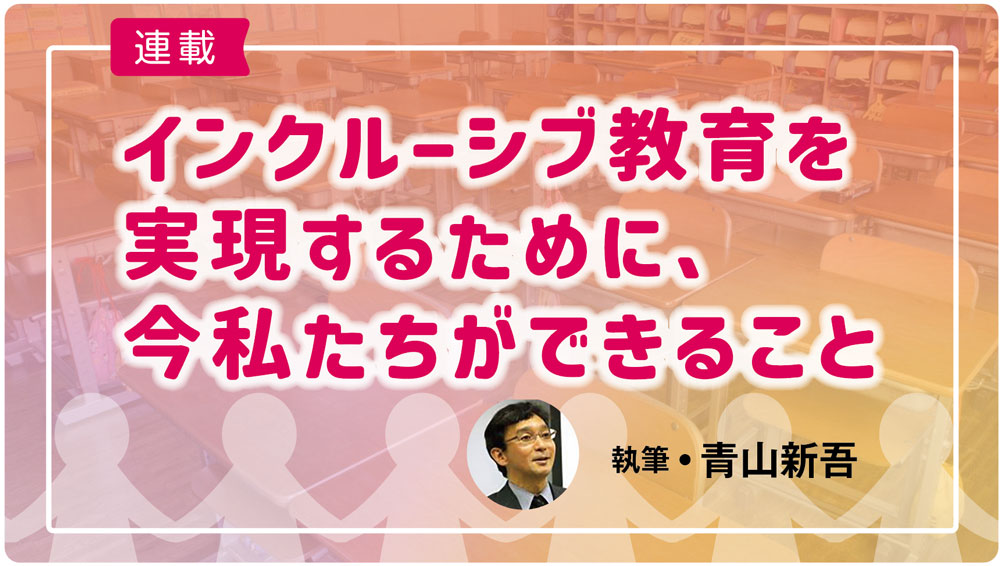
「インクルーシブ教育」を通常学級で実現するためには、どうすればよいのでしょうか? インクルーシブ教育の研究に取り組む青山新吾先生が、現場の先生方の悩みや喜びに寄り添いながら、インクルーシブ教育を実現するために学級担任ができること、すべきことについて解説します。
本連載では、インクルーシブ教育を、貧困状況にある子どもや性的マイノリティの子ども、外国にルーツのある子ども、不登校の子ども、障害や病気のある子どもなどのマイノリティ属性を含むすべての子どもが対象だとしています。そして、すべての子どもたちが包摂される教育を目指すプロセスがインクルーシブ教育であり、そのためには通常学級の教育が変わっていくことが求められているという前提に立っています。
今回は、夏休みだからこそできることについて考えてみましょう。
執筆/ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授・インクルーシブ教育研究センター長・青山新吾
目次
夏休みを迎える~1学期を終えた価値を大切に~

1学期はいかがでしたでしょうか。
1年前になりますが、ある場所で、先生方とお話をする機会がありました。学級の中に、複数の落ち着かない子どもたちがいることで、どのように指導すればよいかを悩み続けた1学期であったと聞きました。
「いろいろな方からアドバイスをもらえてありがたかったです。ただ、言うことがみんなバラバラで……。様々な見方があるとは分かっているのです。でも、自分に余裕がなくて、訳が分からなくなってしまいました。もう、つらくて……」と元気なく話されたのでした。
その時のクラスの様子を具体的にここに書くわけにはいきません。かなり混乱しているのは事実であり、また、苦戦している子どもたちの数も決して少なくはありませんでした。そういった状況から考えれば、その若い先生が、いろいろな工夫をしながら、なんとか1学期をしのいで子どもたちと一緒に進んできたことはすごいことだと思えました。
僕は、
「うーん、本当にがんばってきましたよね。まずは、とにかく本当にがんばってきたことがすごいと思うのです。子どもたちの状況がかなり難しい中で、あきらめずにがんばってきたわけでしょう。大きな事故も起こさずにやってきたことがすごいね……」
と率直に申し上げました。若い先生の目から涙がポロポロとこぼれ落ちたのでした。
終業式に子どもたちの前にいること
通知表を子どもたちに手渡せること
「夏休みが終わったらまた会おう。待っているよ」と語ること
これらのシンプルな言動には、とても大きな意味があると思うのです。子どもたちに与えるメッセージとしてもですし、教員不足に悩む多くの学校現場における貢献度の高さという意味もあるでしょう。
もちろん、いろいろな課題もあるでしょうし、これから調整していく必要もあるのでしょう。しかし、まずは、子どもたちと一緒に1学期を終えたこと自体の価値を大切に考えたいと思うのです。

