保護者との懇談での「やさしいどうして?」のまなざし|インクルーシブ教育を実現するために、今私たちができること #4

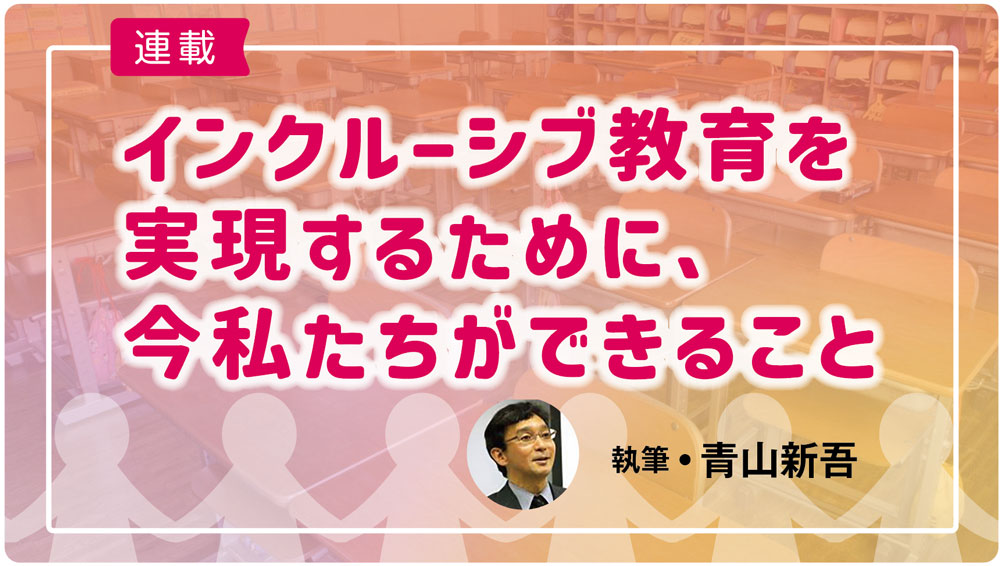
「インクルーシブ教育」を通常学級で実現するためには、どうすればよいのでしょうか? インクルーシブ教育の研究に取り組む青山新吾先生が、現場の先生方の悩みや喜びに寄り添いながら、インクルーシブ教育を実現するために学級担任ができること、すべきことについて解説します。第4回は、「保護者との懇談での『やさしいどうして?』のまなざし~徹底した個への関心~」について考えます。
執筆/ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授・インクルーシブ教育研究センター長・青山新吾
目次
これまでの本連載について
本連載では、インクルーシブ教育とは、貧困状況にある子どもや性的マイノリティの子ども、外国にルーツのある子ども、不登校の子ども、障害や病気のある子どもなどのマイノリティ属性を含むすべての子どもが対象だとしています。そして、すべての子どもたちが包摂される教育を目指すプロセスがインクルーシブ教育であり、そのためには通常学級の教育が変わっていくことが求められているという前提に立ちました。
ここまで連載の中で3つのテーマについて書いてきました。
そのテーマは、
・第1回 徹底した子どもへの関心をもって子どもと一緒に過ごすことが大切
・第2回 子どもを見つめる際に「見方」を変えてみることで、その子どもが違って見えることがある
・第3回 「やさしいどうして?」のまなざしについて
でした。
今回は、前回考えた「やさしいどうして?」のまなざしを子どものご家族に向けてみましょう。
※「やさしいどうして?」……日常の子どもたちの言動に対して、「どうしてそのようにしたのかな?」「どうしてそのように言ったのかな?」などと、その背景要因にまなざしを向けること。青山先生が学生たちと作った造語。
行動に時間がかかる
かなり前の話です。ある学校で先生からお悩みを聞いて一緒に考える機会がありました。
そこで登場したのが、行動に時間がかかる小学生の話でした。ここでは、細かい話は書かず概要だけ記述します。
学校に登校しても、母親と離れられないというのです。そもそもギリギリの時間か、少し遅れて登校してくるとのことでした。やっと離れても、教室になかなか行けず、子どもは担任に一緒にいてほしい様子だけれど、「そのようなことは無理です」と、担任の先生は言いきっておられました。
また、学校生活のいろいろな場面で時間がかかるので、手がかかっているそうです。給食もなかなか食べられないので、限界まで待って、そこで止めさせているとのことでした。
朝、登校の際に、自分が門のところまで迎えに行こうと思うので、もっと早く来てほしいと保護者に頼んでみたところ、よい返事がなかったそうです。家庭の協力が得られないと子どもの支援もうまくいかないので、家庭の協力を得られるようにするにはどうすればよいのかを教えてほしいと僕に言われました。

