「小1プロブレム」とは?【知っておきたい教育用語】
小1プロブレムとは、小学校に入学後に学校生活に適応できない状態が続くことを表した言葉です。何が原因なのか、どのように克服していくのかを考えてみましょう。
執筆/文京学院大学名誉教授・小泉博明
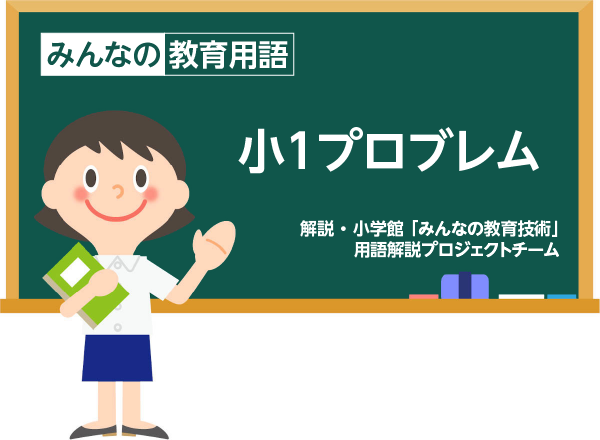
目次
「小1プロブレム」の要因とは
【小1プロブレム】
幼稚園や保育園から小学校にあがった際、子どもたちが小学校での授業や生活に馴染めず、問題行動を継続的に起こしてしまうこと。問題行動には、先生の話や指示を聞くことができない、集団行動をとれない、授業中、席についていられないなど、様々な問題があります。
ベネッセ教育情報サイトによれば、子どもが幼稚園・保育園から小学校へ入学すると次のような変化が生じるとあります。
・遊び中心から勉強中心に
ベネッセ教育情報(ウェブサイト)「『小1プロブレム』を知っていますか? その原因と間違えやすい予防方法」2021年3月1日
・集団生活、集団行動が求められる
・自律的な行動が求められる
・1クラスの人数が増える
子どもは、このような急激な環境変化に対応できず、学校生活に適応するまでに時間を要します。そして、小学校に入学後に、学校生活に適応できず、問題行動を起こしてしまいます。
また、子どもが、保護者から「もう1年生なんだから」「1年生にもなって」などの急き立てる言葉や、一方的な指示を受けると、子どもにとってはストレスが蓄積し、小学校で問題行動となって発散するようになります。単純に「しつけ」が不十分であるという問題ではありません。
そこで、家庭での適切な入学準備が必要となりますが、規律や時間を守ることだけを何回も教えても、子どものストレスとなるだけです。子どものストレスを軽減させるには、保護者が子どもの話を「聞く」「共感する」「考えさせる」「励ます」という共感的な会話が大切です。教育学者である汐見稔幸氏は、頭文字を取って、KKKH、野球用語でKが三振、Hが安打なので、「4打数1安打の会話術」と呼んでいます。
「小1プロブレム」を克服するには
文部科学省は、2022年に「幼保小の架け橋プログラム」を推進していくことを決定しました。義務教育開始前後の5歳児から小学校1年生の2年間のことを「架け橋期」といいます。幼保小連携とは、幼稚園または保育園から小学校へこどもが円滑に移行できるように、相互に連携することです。
共働きの家庭の保護者にとって、小学校へ入学すれば「手がかからない」ので、「働きやすくなる」と考えがちですが、この課題を克服しなければ両立が困難になりかねません。小学校に入学してからの方が働きづらくなります。
そこで、幼保小だけではなく、家庭や地域、関係団体、地方自治体など、子どもに関わる全ての関係者が、連携し協働することが必要です。さらに、「10の姿」(幼児期の終わりまでに育ってほしい姿)を正しく理解し、架け橋期における教育を実現させることで、子どもの学びや生活の基盤をつくることができます。

