「教師の指導と自治的活動でいじめを防ごう」対話型授業と自治的活動でつなぐ 深い絆の学級づくり #4

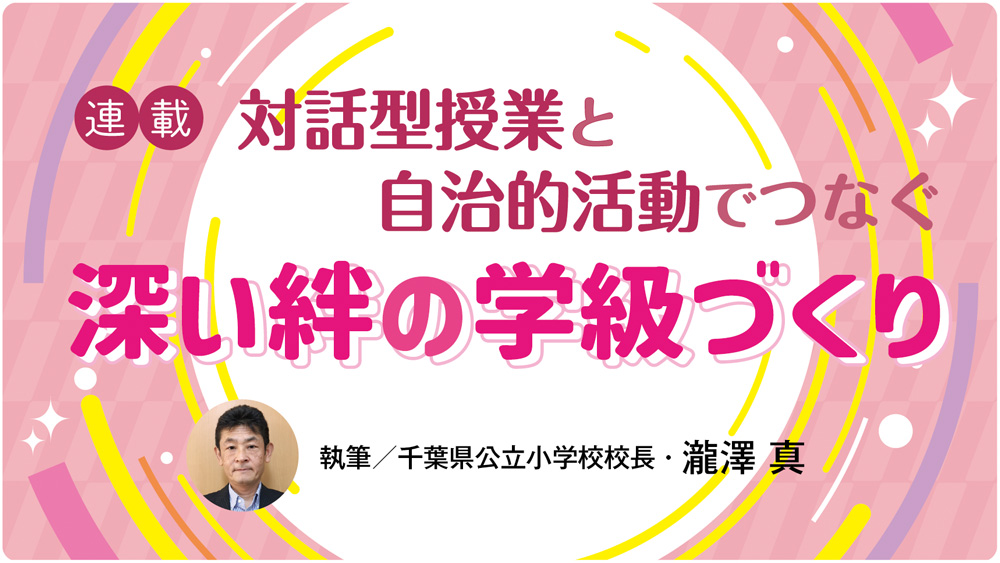
コロナ禍以降、コミュニケーションに苦労する子供や人間関係の希薄な学級が増えていると言います。子供たちが深い絆で結ばれた学級をつくるには、子供同士の関わりをふんだんに取り入れた対話型授業と、子供たちが主体的に取り組む自治的な活動が不可欠です。第4回は、いじめを防ぐ取組についての提案です。
執筆/千葉県公立小学校校長・瀧澤真
目次
4月から行っているいじめを防ぐ取組を見直そう
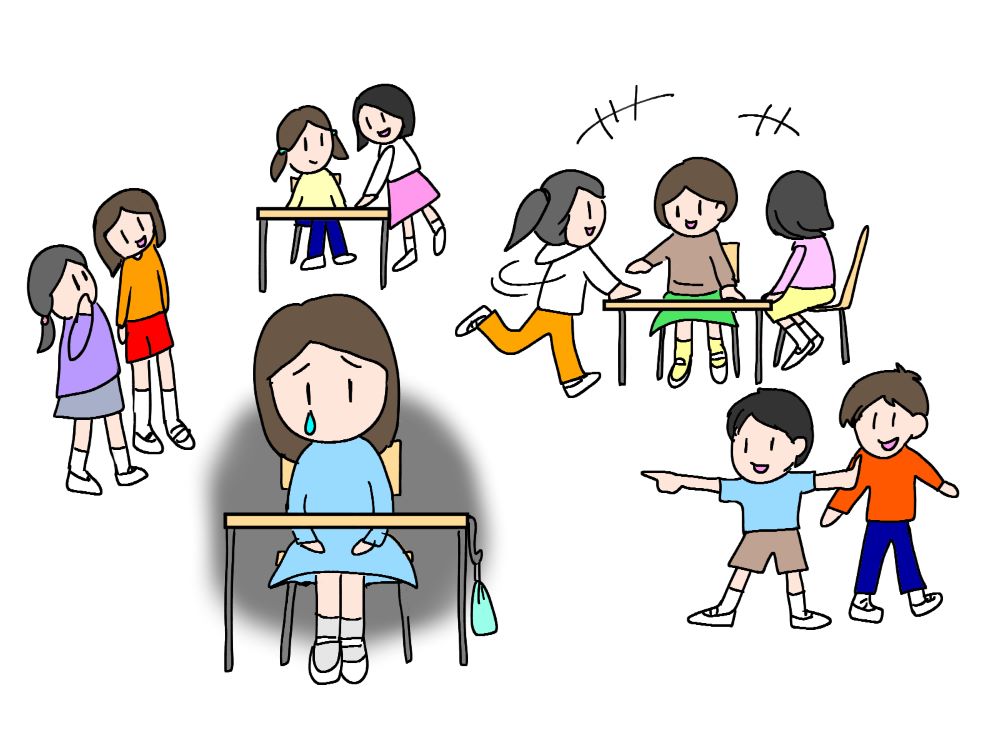
いくら子供たちの絆を深めようと思っても、いじめがあるようでは、その土台が崩れていますよね。もちろん、いじめはいけない、許されないという指導は4月から行っていると思います。しかし、それでいじめが起こらないならば、全国的にこんなにいじめが話題になることはありません。
そこで、再度、いじめを防ぐ取組を見直しましょう。
自治的活動や親和的な雰囲気となる対話型授業を充実させていくことが、結局はいじめ防止になるのですが、その効果がすぐに出るわけではありません。
そのため、まずは教師主導で以下のようなことを再確認してみましょう。
教師の思いを再度伝える
4月に伝えているとは思いますが、再度いじめに対する教師の思いを熱く語りましょう。何度でも繰り返すことで、それほど大切なことなのだということを子供に理解させます。

例えば、こんなメッセージを伝えます。
残念なことに、日本全国で「いじめ」の問題が、新聞やテレビで取り上げられています。
先生は、「いじめ」を絶対に許しません。先生はこのクラスで、「いじめ」が起きないように全力を尽くします。ですから、みなさんも「いじめ」の問題を、真剣に考えてください。
人をいじめることは、どんな理由があっても、絶対に許されることではありません。
もし、今、いじめられている人がいたら、勇気を出して誰かに相談してください。あなたは一人ではありません。あなたを守ろうという人は必ずいます。それを信じて、お家の人、先生、友達、誰でもよいですから相談してください。
もし、今、周りに、いじめている子やいじめられている子がいたら、見て見ぬふりをしないで、必ず家の人や先生に教えてください。教えたことによって、あなたがいじめを受けることは絶対にありません。
みなさんが大事にしなければならないことは、相手の立場に立って、心の痛みを感じることができるかどうかということです。そして、自分がされていやだと思うことは、人に対して絶対にしないことです。
みんなで、次のことを考えて行動していきましょう。
①いじめる人を絶対に許しません。
②いじめを受けたときは、「助けて」と声をあげます。
③いじめを見たときは、そのことを大人に伝えます。
④命は、かけがえのない大切なものです。

