モノを食べたり舐めたりする子にはどう注意すればいい?

鉛筆や消しゴムなどを舐めたり食べたりする子への対応は? 友達に嫌なことをする子への対応をその場限りの指導とならないようにするには? 不適切な行動をとる子への注意の仕方について悩んでいるという先生から、 「みん教相談室」に相談が寄せられました。ここでは、大阪府公立小学校教諭・松下隼司先生からのアドバイスをシェアします。
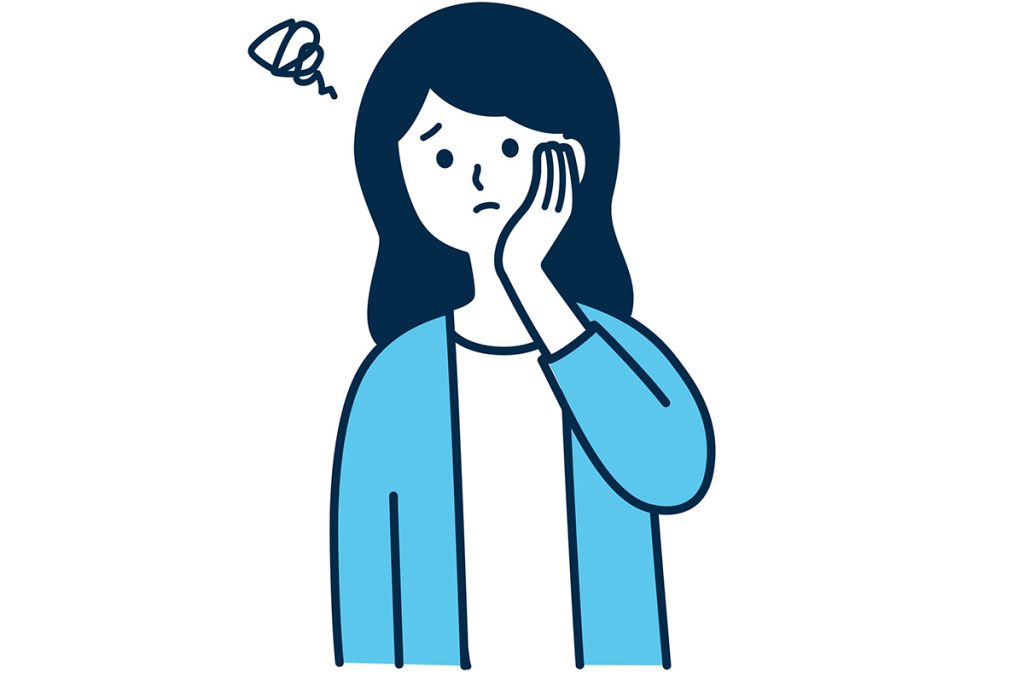
目次
Q.不適切な行動をとる子への注意の仕方をどうすればいいか困っています
こんにちは、初めまして。私は今年、3年生を担当することになったのですが、私のクラスは半分の子が鉛筆、名札、消しゴムなど舐めたり食べたりしています。
一番びっくりしたのが、上履きの裏を舐めていたことです。その子は基本椅子もちゃんと座れず、友達の嫌がることもしています。口も悪く、私も「掃除をやろうよ」と言ったら「うるせぇ!」と言われました。お友達にもそんな口の利き方をします。
そこで、聞きたいのですが、
①食べてはいけない物を食べる、舐めることは、注意をちゃんとした方がいいのでしょうか?
②友達に嫌なことをする子にはどんな対応をしたらいいのでしょうか?(何度も注意をするのですが、その時は謝ってあとは繰り返しているので、指導が入ってないのかなと思います)
もし宜しければ、お返事よろしくお願いします。
(蓮先生・20代女性)
A.①注意する前に、その子の行動をよく観察する
3年生でクラスの半分ぐらいの子どもが、物を舐めたり食べたりするというのは、多いですねー!
実は、私も子どもの頃、よく鉛筆を噛んでいたので、なんとなく理由が分かります。鉛筆を噛む理由は、私の場合、鉛筆の噛みごたえが気持ちよかったからです。木でできた鉛筆を噛むと少し弾力があって、歯形が残るのが気持ちいいのです。そして、少し味もするのです。
これは、私の理由であって、子ども一人一人、理由が違うかと思います。
何かに集中すると噛んだり舐めたりする子どももいれば、逆に不安なことがある時に噛んだり舐めたりする子どももいます。(低学年では、ハナクソを食べたり自分の髪の毛を噛んだりする子どもも多くいますよね)。
そこで、舐めたり噛んだり食べたりするのを注意する前に、その子の行動をよく観察することから始めてみることをおすすめします。
例えば、以下のようなことです。
- どんなときに(何の教科の授業、何の活動、何時間目など)にその行為をすることが多いのか
- 舐めたり噛んだり食べたりをする時間はどれくらいなのか
- 舐めたり噛んだり食べたりをするのを自らやめるのは何かきっかけがあるのか
- 「舐めているよ」「噛んでいるよ」「食べているよ」と肩や背中に優しく触れて気づかせると、やめるのか
例えば、その子の苦手な教科の授業の時間に行為が増える、といった傾向が分かれば、その状況に合った指導法を検討することができます。
やみくもに注意をするのではなく、子ども一人一人の実態を理解した上で、その子どもに合った対応法を考えていくのがよいと思います。
A.②友達に嫌なことをする子への対応
言葉のサンドイッチ
友達が嫌がることをする子どもへの対応で感情的になりすぎ、失敗したことが私にはあります。必要以上に、強く・長く叱ってしまって、子どもの心を傷つけてしまったのです。
子どもが悪いことをしたら、正しく叱ることも大切ですが、ここでは、教師が必要以上に感情的にならずに済み、加害児童も素直に教師の指導を聞いてくれるようになるような対応法を紹介します。
まずは、
「あなた(子どもの名前)は、本当はそんなことをする子じゃないよ」
「あなた(子どもの名前)は、本当は優しい子だよ」
と、最初に話しかけます。
それから、トラブルの内容を確認し、指導します。
そして最後にもまた、
「あなた(子どもの名前)は、本当はそんなことをする子じゃないよ」
「あなた(子どもの名前)は、本当は優しい子だよ」
と話します。
あたたかい言葉がけのサンドイッチで、トラブル対応の雰囲気が、がらりと変わるかと思いますよ。
事前指導を丁寧に
私は、「注意」でなく、必要以上に厳しく叱りすぎてしまうことがあります。そして、叱った後に、「厳しすぎやな」と反省します。さらに、嫌なことをされた側の子どもに、私が代わりに謝ることすらあります……。
起きてしまったトラブルにどう対応するかはもちろん大切ですが、私は、事前指導を丁寧にしておくことも心がけています。
例えば、図工の時間に絵の具を使うとします。
「絵の具の準備をします」
と言うだけだと、筆洗に水を入れに行った手洗い場で、トラブルが起きてしまうかもしれません。
そこで、
「準備で気をつけることは何ですか?」
と聞きます。すると子どもたちから、
「授業中なので、静かに準備します」
「すぐにします」
「ふざけません」
など出るかと思います。子どもたちの中から出なければ、
「人の嫌がることは、しま……?」
と聞きます。すると子どもたちから
「(人の嫌がることは、しま……)せん!」
と返ってきます。
また、一斉に水場に行かせると、人数が多いので混雑するため、トラブルが起こる可能性が高くなります。だから、号車ごとに行かせたり、複数の水場に行かせたりして、トラブルの原因を回避することもできます。
そして、トラブルなく行動できた瞬間を見逃さずに、子どもを褒めましょうね。
「みん教相談室」新規受付停止のお知らせ
長い間、この企画を応援してくださり、ありがとうございます。
今後「みん教相談室」は新規のご相談受付を停止し、現在開発中の新たな取り組みの中に、これまで大切にしてきたコンセプトを活かしていきたいと考えております。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

