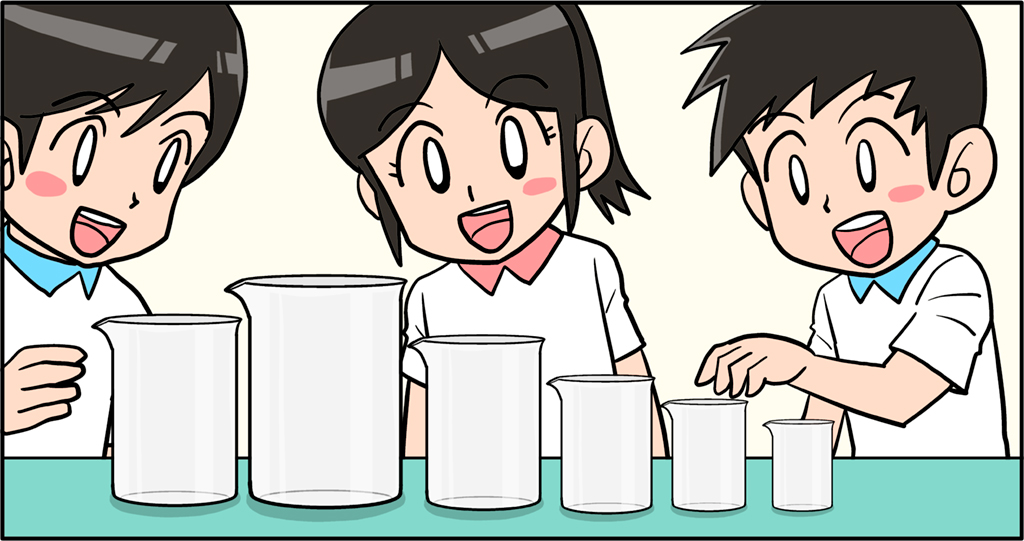小学校理科で、子どもたちが主人公の観察・実験にするためには? 【理科の壺】

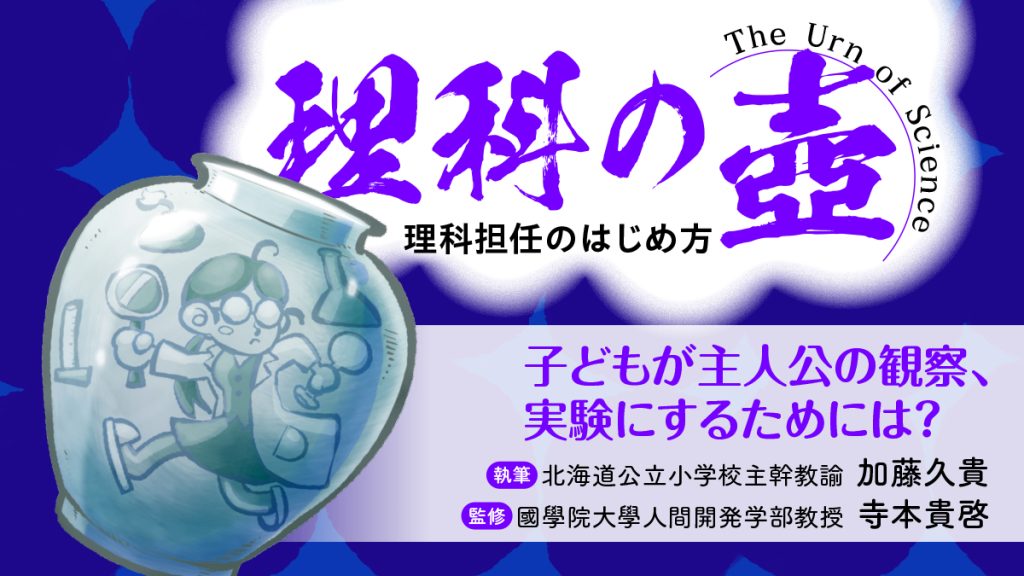
理科の授業を進めるにあたり、教師の誰もが「子ども一人一人の思いを大切にしたい」「子ども主体の観察、実験をさせてあげたい」と願うことでしょう。
しかし、指導の中には、子ども自身ができるはずのことまで教師がやっていることも少なくありません。そうすると、観察、実験が「教師が用意したもの」「教師から与えられたもの」になってしまい、子どもが学びの主人公から遠ざかってしまうことになってしまいます。 優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法やアイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/北海道公立小学校主幹教諭・加藤久貴
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1 観察、実験に必要な器具は「何を使えばいいかな?」
観察、実験の計画を立てる際に、「必要な実験道具はこれです」と言って実験道具を説明していませんか?
いつも教師が提示した実験道具で実験を行っていると、子どもは「実験器具の準備は教師がしてくれるもの」と認識し、自分たちで実験計画を立てる力が育成されません。
そこで、観察、実験に使う器具は子どもと一緒に決めていくことを強くお勧めします。
例えば、 第5学年の「ものの溶け方」の学習で、50mLの水に食塩を溶かすとしましょう。その際に、適切な実験器具は何かを子どもに選択させるのです。
どのように確かめたらいいかな。
ビーカーを使ったらいいと思います。
ビーカーの大きさはどうしましょう?
50mLの 水なんだから50mLのビーカーでいいんじゃない?
それだと、食塩を入れてかき混ぜたときにあふれてしまうかもしれないよ。
それじゃ100mLにしてみよう。
こうして自分たちで選択した実験器具を活用することで、適切な実験器具を選択する力が身に付き、この経験を繰り返すことで、自ら考えながら問題を解決しようとする力を育成することにつながるでしょう。
なお、子どもたちの力では思いつかないものや、新しい実験器具を活用する際も、一度子どもに実験方法を考えさせてから紹介するようにします。
そうすることで、その器具を使うことの意味や器具の便利さなどにより気づくことができるでしょう。