「教育振興基本計画」とは?【知っておきたい教育用語】
教育基本法に基づき策定される「教育振興基本計画」をおさえておくことは、教育の今後を見通すうえで欠かせません。では、教育振興基本計画とは、具体的にどんな計画であり、どのような教育を目指すために策定されるものなのでしょうか。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・宮崎猛
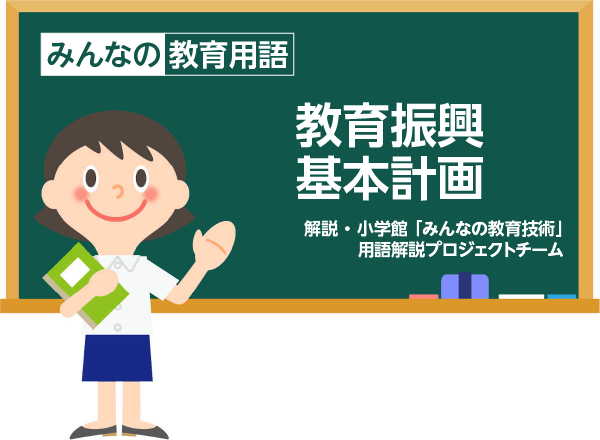
目次
教育振興基本計画とは、教育基本法に基づいて政府が策定する教育計画
【教育振興基本計画】
平成18(2006年)に定められた教育基本法に基づき、政府が策定する教育に関する総合計画。5年おきに国の教育政策全体の方向性や目標、施策などを定めており、令和5年度~9年度における第4期の教育振興基本計画は、令和5年(2023年)6月16日に閣議決定された。計画のコンセプトとして、持続可能な社会の創り手とウェルビーイングの向上が主たるテーマとなっている。
平成18(2006)年に全面改正された教育基本法では、教育の振興に関する施策の方針や必要事項を定める「教育振興基本計画」の策定が国に義務づけられることになりました。その条文が以下の通りです(「教育基本法」より該当部分を抜粋して紹介します)。
(教育振興基本計画)
第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
この条文に基づき、教育振興基本計画が策定されるようになりました。また、地方自治体においても「○○県教育振興基本計画」や「○○県教育ビジョン」など、国の教育基本計画を参考に独自の基本計画を作成することが求められるようになりました。
平成20(2008)年7月に初めての教育振興基本計画が策定され、以降5年おきに計画が策定されています。現在の教育基本計画は第4期であり、令和5年(2023)度から令和9年(2027)度の取組となっています。
総括的なコンセプト・基本方針
第4期教育振興基本計画では、そのコンセプトともいうべき総括的な基本方針として「持続可能な社会の創り手の育成」および「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」を掲げました。
文部科学省「第4期(令和5年度~令和9年度)教育振興基本計画」によれば、以下のことが求められています。
持続可能な社会の創り手の育成
文部科学省(PDF)「第4期(令和5年度~令和9年度)教育振興基本計画」
●将来の予測が困難な時代に、未来に向けて自らが社会の創り手となり、持続可能な社会を維持・発展させていく人材を育てる
●主体性、リーダーシップ、創造力、課題設定・解決能力、論理的思考力、表現力、チームワークなどを備えた人材の育成
日本社会に根差したウェルビーイングの向上
●多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、地域や社会が幸せや豊かさを感じられるものとなるよう、教育を通じてウェルビーイングを向上
●幸福感、学校や地域でのつながり、協働性、利他性、多様性への理解、社会貢献意識、自己肯定感、自己実現等を調和的・一体的に育む
コンセプトの背景には、前期(第3期)の教育振興基本計画の取組の成果と課題を鑑みたことにあります。
成果としては、初等中等教育段階における、GIGAスクール構想による1人1台端末と高速通信ネットワーク等のICT環境の整備が飛躍的に進展したこと、高等教育段階において大学の認証評価のための法改正、大学設置基準の改正など、学習者本位の教育への転換に向けた取組が大きく推進されたことが評価されました。その一方で、課題として、不登校・いじめ重大事態などの増加、学校の長時間勤務や教師不足などの問題が指摘されました。
さらに、現代は「VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)」の時代、つまり将来の予測が困難な時代といわれています。こうした教育をめぐる現状・課題・展望を踏まえ、第4期教育振興基本計画では、2040年以降の未来の社会を見据えた教育政策が示されたのです。
また、上記の2つのコンセプトに基づき、以下の5つの基本的な方針が定められました。
①グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成
文部科学省(PDF)「第4期(令和5年度~令和9年度)教育振興基本計画」
②誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進
③地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進
④教育デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進
⑤計画の実効性確保のための基盤整備・対話
この5つの基本方針を実行していくことで、子どもはもちろん、教師をはじめとする学校全体のウェルビーイングの向上を目的としています。そして、子どもたちのウェルビーイングの向上が、家庭や地域、社会にも多大な影響を与え、日本の教育全体をよりよい方向に導いていくことが期待されます。

