「実務家教員」とは?【知っておきたい教育用語】
実務家教員とは、企業や官公庁等における実務経験を通して培われた知識やスキルなどを生かして、大学および大学院(専門職大学、専門職大学院を含む)、短期大学、高等専門学校などの高等教育機関において、教育や研究等の職務に従事する教員のことです。法令上の用語ではなく、社会人教員とも呼ばれています。
執筆/文京学院大学名誉教授・小泉博明
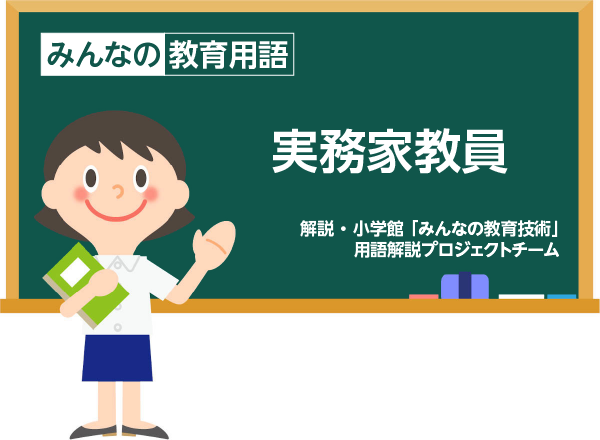
目次
実務家教員が求められる背景
文部科学省「持続的な産学共同人材育成システム構築事業」によれば、実務家教員が求められる背景を次のように説明しています。
グローバル化が進み、知識経済が到来する中、人口減少社会となった日本にとって、人材育成の質の向上は、コロナ禍前からの懸案です。日本経済の長期低迷や、G7中最下位の労働生産性といった現状に鑑み、人材育成の変革は、我が国にとって喫緊の課題です。ところが、日本の高等教育には、授業外学習時間の少なさや、社会人の学び直しの低調さなど、大きな課題があります。
以上のような背景から、今日、学生も社会人も学び続けチャレンジし続ける社会の実現のため、中心的役割を担う「実務家教員」への期待はかつてなく高まっています。求められる実務家教員は、学びと人をつなぐことにより、学生の動機づけを高めるとともに、社会人をリカレント教育へ引き付ける「教育者」です。
文部科学省(ウェブサイト)「持続的な産学共同人材育成システム構築事業」
以上の説明にあるように、現代社会において産学が往還し、高度な経験と最先端の知識を併せ持つ実務家教員が求められています。
大学設置基準の改訂
「大学設置基準」の改訂が行われ、「教授の資格」は次のように規定されています。ここでは、文部科学省「『実務家教員』関係規定等」より一部抜粋して紹介します。
第十四条
教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
———————————————(略)———————————————–
六 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
第十四条の六項が追加されたことにより、実務家教員の採用が容易に行われるようになりました。
また「専門職大学院設置基準」(平成15年文部科学省令第16号)には、「専攻分野における実務経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする」とあり、専門職大学院では実務家教員を必ず置くこととされ、専任教員のおおむね3割以上(法科大学院では2割以上)は、専攻分野における実務経験と高度の実務能力を有するものでなければなりません。
「文部科学省告示第53号」(平成15年3月31日)には、「専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とする」とあります。さらに、法科大学院においては「実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する専任教員は、法曹としての経験を有する者を中心として構成されるものとする」とあります。したがって、実務家教員には、実務能力、研究能力、教育指導力、の3つの力が求められるのです。
●実務能力
知識や理論だけでなく、実際の現場での仕事の遂行能力や問題解決などの知見を学生たちに指導することが求められる。
●研究能力
研究者教員のような論文の執筆、研究の発表に加え、自身の実務経験やスキル、知識を応用した研究活動を行うことが求められる。
●教育指導力
実務経験によるスキルだけでなく、それらの知見を学生たちに効果的に指導できる能力が求められる。
上記のことから、実務家教員は、実務経験による知見を研究活動に発揮すると同時に、単に授業を行うだけでなく、学生たちが課題に直面した際の解決に向けた手法やアプローチ、プロセスなどを実践的に指導できることが必要とされます。

