「学習者用デジタル教科書」の現状と課題~どうしたら活用していけるのか~(中編)
令和6年度より、全国全ての小学5年生から中学3年生に、英語の学習者用デジタル教科書が導入されます。一部の小中学校では、「算数・数学」でも導入される予定です。いよいよ本格導入が見えてきた学習者用デジタル教科書。しかしこの先には活用へ向けての課題も横たわっています。
本記事では、教科書会社の担当者や学習者用デジタル教科書を活用している先生方への取材から浮かび上がった現状と課題をもとに、元教科書編集者/元教育ソフト開発者としての筆者の視点から、活用に向けた考察と提言を3回に分けてお届けします。今回はその第2回です。
取材・文/村岡明
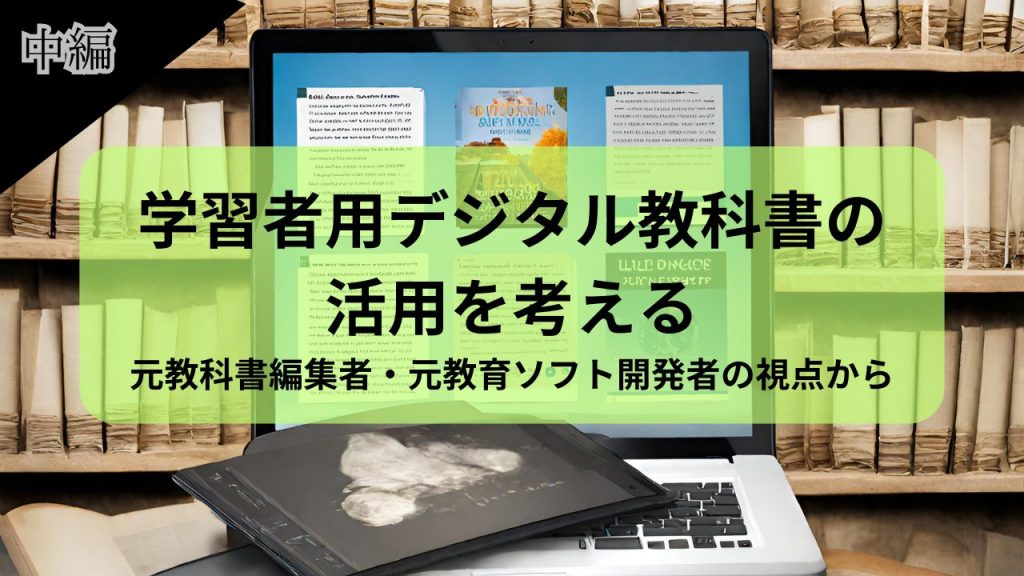
【前回の記事はこちら】
いよいよ本格導入へ!「学習者用デジタル教科書」をめぐる現状と課題~どうしたら活用していけるのか~(前編)
目次
メリットを実感してもらうために
前回の記事で述べてきたように、学習者用デジタル教科書を使ってもらうためには、まず先生方に「使いたい」と思わせる明確なメリットが必要です。しかし、今回取材をした中で「メリットを感じない」とおっしゃる先生は少なくありませんでした。
なぜメリットを感じないのでしょうか。その意見を深掘りすると、大きく次の4つに集約されます。
- 操作が分かりにくい
- コンテンツに魅力がない
- 教科ごとに操作方法が違う
- 動作が遅い
以下順番に、その意味するところを考えてみます。
操作性が分かりにくい
逆説的な言い方になりますが、ほとんどのソフトウエアは「操作が分かりにくい」ものです。若者に「使いやすい」と評判のiPhoneでさえ、多くの高齢者は「使いにくい」と感じます。日本人の多くが「分かりやすい」と感じる街角の標識も、外国人には「分かりにくい」ものだったりします。
つまり、「使いやすい・使いにくい」「分かりやすい・分かりにくい」は絶対的なものではなく、「慣れ」の要素が大きいのです。このことは、多くのUX(User Experience)の専門家も指摘しています。
ただ、確かに使いにくい操作性になってしまっている場合もあります。たとえば、デジタル教科書をすぐに使いたいのに、いったんプラットフォームを開いてからでないと起動できない教科書があると聞きました。これでは授業のリズムが崩れてしまいます。
こうした明らかに「使いにくい」と感じることがあった場合は、ぜひサポートセンターに連絡してあげてください。その際、「使いにくい機能の操作手順や場面」を端的に説明できるようにしておくと、声を取り上げてもらいやすくなります。また、周囲の人も同様に感じているようなら、その点を伝えることも重要です。

